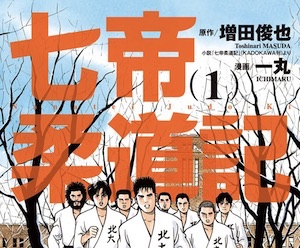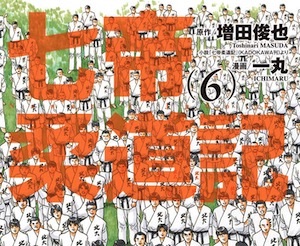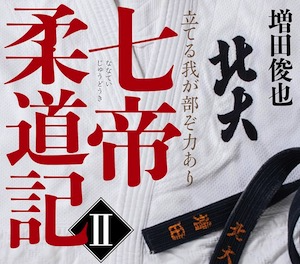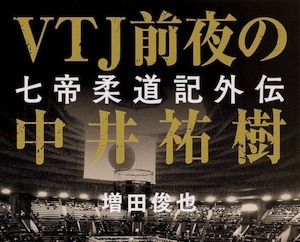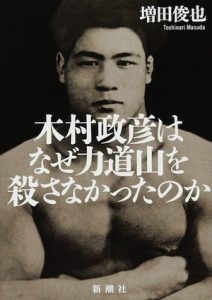七帝柔道記
増田俊也著
角川文庫
文体は引っかかるが内容はユニークで魅力的
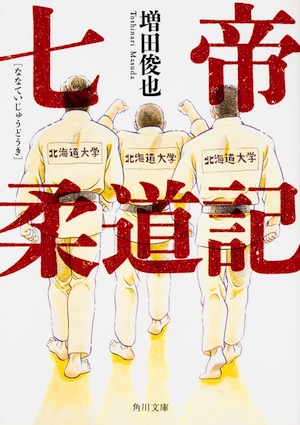
北海道大学の柔道部に入った主人公が、部の中で奮闘していく2年間を描いた小説。
著者は、『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』の増田俊也で、初出は『月刊秘伝』という雑誌。おそらく著者の学生時代をそのまま描いた自伝的小説だろう。
二浪して北海道大学に入学した主人公(増田)は、当初の予定どおり柔道部に入部する。北大の柔道部は、現在一般的である講道館柔道とは異なる、戦前の高専柔道を踏襲した寝技中心のスタイルを持つ、いわゆる「七帝柔道」を採用しており、その「七帝柔道」の大会が毎年夏に行われる七帝戦(全国七大学総合体育大会)。その七帝戦を目指して日夜地獄の特訓を続ける日々が描かれる。
ちなみに七帝戦とは、旧帝大の7大学(北海道大、東北大、東京大、名古屋大、京都大、大阪大、九州大)が参加する体育大会で、僕など学生時代にこの大会の存在を知ったときは、エリート意識が鼻についてあまり良い気持ちがしなかったが、本書によると、七帝戦というのは元々、戦後も高専柔道を続けるために(旧制高等学校を継承した七大学が主催して)開かれた柔道大会だったのが、他の運動部も参加してきて今の形になったということなので、元々はエリート意識などとは無縁な純粋な動機で始まったものだったようだ。
この七帝柔道、先ほども言ったように寝技中心で、しかも寝技中に、講道館柔道のような「待て」がかからないため、時間切れになるまで延々と寝た状態が続くということが普通にある。そのため、相手が寝技をかけにくい体制(カメ)でずっと耐え続け、引き分けを狙うというような戦法も普通に存在する。試合は15人制の勝ち抜きであるため、引き分けを狙う「分け役」と、勝ち星を挙げることを目指す「抜き役」が存在し、トータルで勝ちを目指すことになるため、チームの一体性が非常に重要になる。こういったスタイルの柔道であることから、練習量がすべてを決めるらしく、そのためにどのチームもひたすら厳しい練習に明け暮れる。それは北大にも当てはまり、主人公は、毎日ゴミのようになりながら、しかも毎日何度も締め落とされる(地獄の苦しみらしい)日々が続く。練習後は30分間まったく動けなくなるほどで、日常生活もすべて柔道一色に染まっていく。
こういう苦しみから逃れたい、つまり部を辞めるという選択肢が常に頭の中に巡ってくるらしく、それは多くの部員に共通で、そのために若い学年の部員は次々に辞めていくのである。主人公自身もそういう葛藤を抱えながら、他では味わえない充実感、他のメンバーとの一体感を徐々に味わうようになるという、そういう青春小説である。
内容は非常に斬新で、こんな世界があるのかと思わせるような世界が展開される。次第に部活動にどっぷり浸かっていく様子は、万城目学の小説、『鴨川ホルモー』などとも共通するが、大学の体育会の魅力がこういうところにあるのかというのが何となくわかってくる。
ただ僕自身について言えば、大学生活にこういった不自由な環境をもたらすことに大変な抵抗を感じていたため、学生時代、体育会には一切近づかないようにしていた。この小説で描かれる世界も魅力的ではあるが、今でも自分の選択は正しかったと思っている。要はいろいろな人間がいるということである。
この小説は、特に後半になって、人間関係の部分などになかなか印象的な描写が出てきて、さわやかな青春小説として仕上がってくるんだが、先輩をすべて「さん」付けで記述するなど、日記風あるいは手記風な印象が全体的に漂っていて、小説としてはかなり興ざめな文体である。また登場人物が多く、判別しにくいのも難点である。ただ内容は相当ユニークで質も高いため、映像化されると魅力的な作品になるのではないかと思う。などと思っていたところ、すでにマンガ化されていたことがわかった。こちらも面白そうなんで、いずれ読むつもりである。