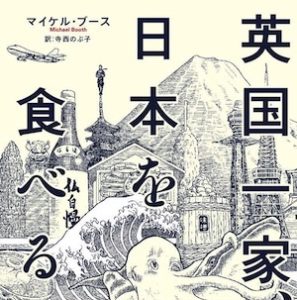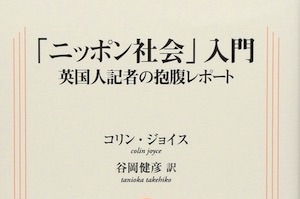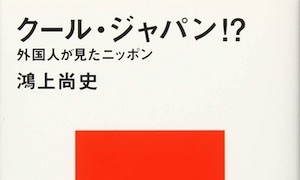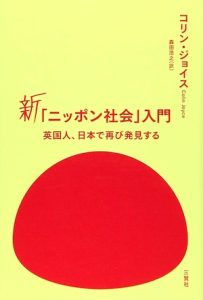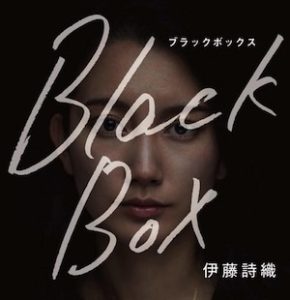イギリス人アナリスト 日本の国宝を守る
デービッド・アトキンソン著
講談社+α新書
忠言は耳に逆らえども……
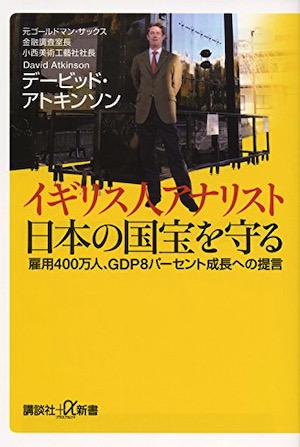
元ゴールドマン・サックスの金融アナリストで、現在、文化財修復企業、小西美術工藝社の社長を務めるという異色のイギリス人、デービッド・アトキンソンによる日本論。
外国人による日本論というと、概ね日本礼賛記事が多いが、このアトキンソン氏、かなり辛口。たとえば戦後の高度経済成長も、当時の状況(爆発的な人口増があり、同時に戦禍でインフラがなくなっていた)を鑑みれば、決して奇跡ではなく必然だったという分析で、日本人でしか起こり得なかったというようなものではないと一刀両断している。ま、聞いてみれば実に的を射た議論で、なるほどと思うが、多くの日本人にとってはこういう分析は不快で、「お前と話していると腹が立つ」などと言われることもあるらしい。
そのアトキンソン氏、先ほども言ったように、5年前から日本の職人集団のトップに立つことになった。中小企業ではあるが、そこには日本の社会、経済の縮図と言えるものがあった。そこで自分の理念に従って、問題点にことごとく大なたをふるって、それまでの赤字体質を大幅に改善したのであった。もちろん従業員にとって痛み(給与の削減)を伴うこともあったので反対もあったらしいが、少なくとも仕事の質の向上や後進の育成に成功し、何よりも黒字経営を実現したため、従業員の方も彼を信頼するようになったと言う。
このアトキンソン氏、つまり著者によると、彼の会社の社員、つまり職人たちは非常に真面目で自分の仕事に誇りを持っていたが、それをうまくまとめ上げ合理的に経営する能力が当時欠けていたという。そしてそれは他の業種でも同じで、日本の会社の社員たちは一生懸命がんばって仕事をしているが、上に行くほど、つまり経営側に近づくほどどうしようもなくなってくるらしい。アナリスト時代に日本の有名な銀行のトップと接していて、どうしてこんな人間がトップにいて経営が成り立つのかと感じたことが多いという。しかしその辺の指摘は、確かに思い当たるフシがあり、それは経営陣だけに限らず、行政に多大な力を持っている官僚なんかでも同じことが言える。日本の集団の体質に思いを馳せると、日本で権力を握るためには、愚かでなければならないのかとも思う。この間のオリンピック騒動しかり、東芝の粉飾問題しかりで、少なくとも普通の感覚の人間がトップにいれば、あんなバカバカしい事件は起こらないだろう。そういうことを考えると、著者の指摘は、日本人にとっては耳に痛いかも知れないが、説得力を持つ。ただし彼の主張は過剰に経済中心のようにも感じられて、そのあたりは少々反発を感じる部分である。
もう一つ、本書で触れられているのが、日本の観光業への提言で、政府が言っているようにこれから観光業に本格的に乗り込もうと言うんなら、まず何よりも文化財の維持に力を入れるべきだと言う。そもそも2014年現在の文化財保存修理費は年間わずか81億5千万円で、これはもう論外である。妙ちきりんな競技場に3000億出すとか出さないとか言っている国が関わっている予算とは思えない。僕自身、この額を今回初めて知って驚愕した。
著者によると、日本の観光業は他国と比べるとまったく手つかずに近い状態で、伸びしろが非常に大きいらしい。そのため本気で力を入れたら、相当な収益、雇用が見込めるということで、日本の次世代の産業としてきわめて有望ということだ。やるなら本気でやるべきというのが著者の主張である。この本は著者のいろいろな主張が盛り込まれていて、この本の後、各論を別の本で書いていくというようなこともやっているが、この本は言ってみれば総論みたいな立ち位置である。内容は盛りだくさんであるが、これ一冊でもかなり得るものはある。