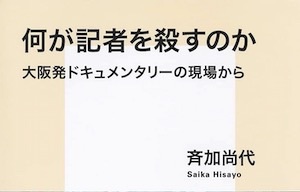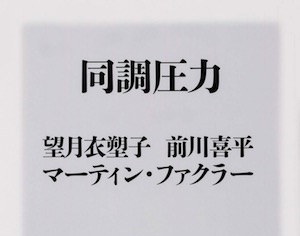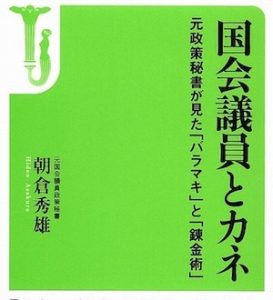さよならテレビ
阿武野勝彦著
平凡社新書
放送業界にも気骨のあるジャーナリストが存在した
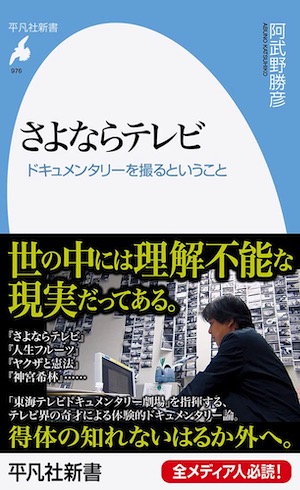
東海テレビのドキュメンタリーはすごいものが目白押しという風にこれまで思っていたが、「すごいもの」の多くは、本書の著者、阿武野勝彦が関わったものだった。
著者は、大学卒業後、東海テレビに入社して、アナウンサー(!)をやった後、報道畑に移り、やがてドキュメンタリー製作に携わるようになる。『ガウディへの旅』でディレクターデビュー(監督は松川八洲雄という人で、ディレクターの著者とも随分衝突があったらしい)し、『平成ジレンマ』、『長良川ド根性』あたりまでディレクターとして、それ以降はプロデューサーの立場で数々のドキュメンタリーに関わっていく。手がけた作品には、東海テレビ名物の司法シリーズの他、『ヤクザと憲法』や『ホームレス理事長』などがあり、数々の問題作を世に問うてきた。阿武野の作品リストを見ると、東海テレビの優れたドキュメンタリーは、ほとんどこの男の手を通じて出てきていることがわかる。
本書では、彼が手がけた作品群について、一本一本詳細な記述があり、同時にその背景や、著者の問題意識、当時の著者の周辺状況なども紹介される。新しい作品から過去の作品へという順でほぼ遡って紹介されており、結果的に、著者自身の経歴を過去に向かって辿っていくというような構成になっている。
阿武野作品には、均質化し異物を排除しようとする日本社会に対して異議を唱えるような作品が多く、近年発表したドキュメンタリーも、本書のタイトルと共通する『さよならテレビ』という作品で、このドキュメンタリー作品では、自身が所属する東海テレビの内部がドキュメンタリーの対象になっている。これは、ジャーナリズムである前に私企業になることを選択している現在のテレビ局の問題点をあぶり出すような作品で、非常に興味を抱かせるテーマである。撮影時、製作時、製作後に社内のいろいろな人々から激しいクレームを浴びせられたらしいが、自身の哲学を押し通し、ジャーナリズム精神に徹したらしい。その姿勢はまさにジャーナリストの鑑である。
他にも、自身が製作したドキュメンタリー作品が多くの人の目に触れるようにするため(一般的にドキュメンタリーは一度放送したらそれっきりで、しかもローカル局だと番組を目にする人の数も限られている)、全国の映画館で劇場公開できるシステムを構築したことについても記述がある。同時に興行界の閉鎖性もあぶり出されている。また、阿武野作品に晩年何度も出演した樹木希林についても紙幅が割かれている。こちらもファンにとっては関心のあるところだろう。
著者のような気骨のあるジャーナリストは、本書からは、今や絶滅危惧種になっていることが窺われるが、そういう意味では、これからもまだまだドキュメンタリー製作に携わっていただきたい人材である。会社にとっては危ない存在のようであるが、「危ない阿武野」であり続けてほしいものである。それが日本のジャーナリズムにとっての救いになる。