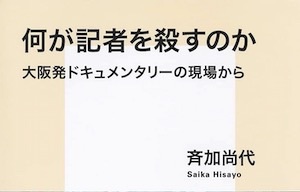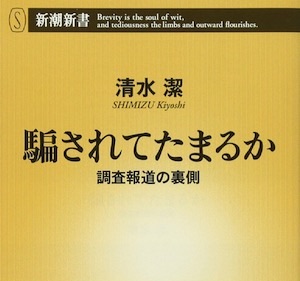同調圧力
望月衣塑子、前川喜平、マーティン・ファクラー著
角川新書
問題について何も報道しないマスコミには
存在価値がない
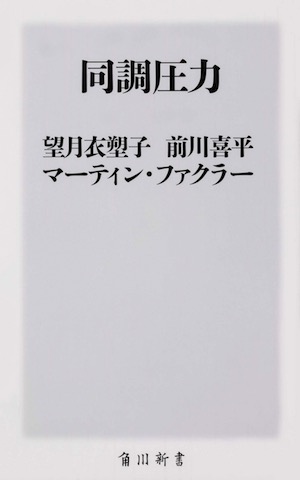
映画『新聞記者』で望月衣塑子、前川喜平、マーティン・ファクラーの対談がテレビ番組の1シーンとして随時登場していたが、その3人がそれぞれ日本の報道や政府との関わりについて意見を述べたのがこの本である。ちなみに映画の中に出ていた対談は元々映画用に撮影されたものらしいが、その対談は実際に行われたものであり、それが巻末付録として本書に収録されている。
第1章を望月、第2章を前川、第3章をファクラーが担当しており、それぞれが日本の報道や教育行政について自身の専門分野に合わせてその問題点を指摘している。第1章では、望月が、物言わぬ記者クラブの中で(同調圧力に従わずに)物を言ったことから政権によって敵視され嫌がらせを受けた経験や、映画『新聞記者』のエピソードなどを紹介している。
次の第2章では、文部科学省の事務次官を務めた後政府の不正を告発した前川が、省庁内部の実態を紹介する。その実態は驚くべきもので、公務員の仕事は「遅れず、休まず、働かず」がモットーであり、なんと仕事をなるべくしないことが原則とされるらしい。この項で呆れかえるばかりの公務員の実態が紹介されているが、現在は国家公務員の生殺与奪を政権に握られているため政権の意に反した行動をとるとあれやこれやの圧力がかけられるという。もっともそれ以前に省内に同調圧力があり(なんせ「働かず」が大原則だから)目新しいことができない上、実際にそういったことはやりにくいらしい。そのあたりの官庁の構造がここで暴露されていて、なかなか興味深いところである。
第3章では、ニューヨーク・タイムズの東京支局長を勤めたマーティン・ファクラーが、日本の報道の状況を米国の状況と比べて、非常に嘆かわしい状況になっていると報告する。ワシントンでは、記者が政権と闘うのは当然であり、それこそが読者に期待されることである(日本でもそうだったと思うが)。政権にすり寄らず調査報道に力を入れて真実(多くは政権の問題)を暴くことこそが理想的なジャーナリズムであり、それが読者の期待に沿うことになるというのだ。一時期部数が凋落傾向にあった大手新聞各紙(ニューヨーク・タイムズやワシントン・ポストなど)も、近年このような調査報道に力を入れて政権批判を展開していることもあって部数を著しく伸ばしているという話も語られ非常に興味深いんだが、一方の日本では、大手マスコミが記者クラブという制度に安住し、政権に近づき媚びて情報を与えていただくようなアクセス・ジャーナリズムばかりがはびこってしまっているという。日本の記者の危機感の欠如がその原因ではないかとファクラーは分析しているが、政権べったりの報道を繰り返しているようであれば、読者が離れていくのは目に見えている。テレビの報道もしかりで、昨今、新聞やテレビが市民にそっぽを向かれている状況が存在するのはそのせいではないかと語る(実際僕自身も、内容がひどくなったことから毎日新聞の購読をやめた)。
最後の対談もそれぞれのテーマが各自の口から述べられており、エキサイティングで面白い。望月の記者活動を取り上げたドキュメンタリー映画『i ―新聞記者ドキュメント―』を見ていれば、この本で目新しいことを感じることはそれほど多くないが、現在の日本のマスコミの有り様がよくわかるという点では読みどころの多い本である。