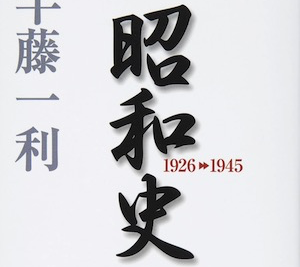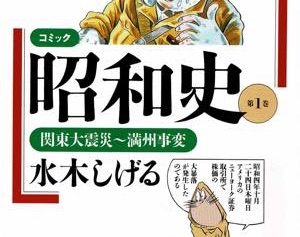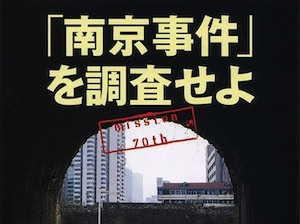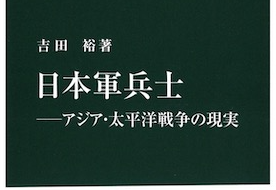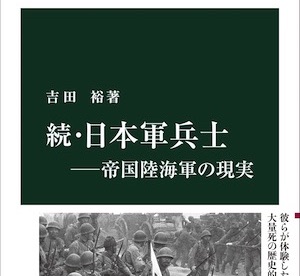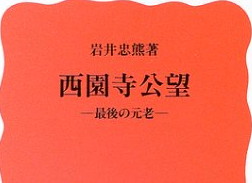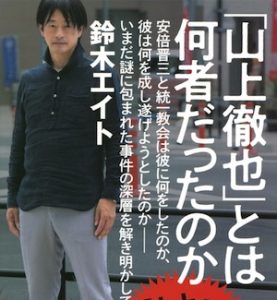テロルの昭和史
保阪正康著
講談社現代新書
暴力肯定の行き着く先
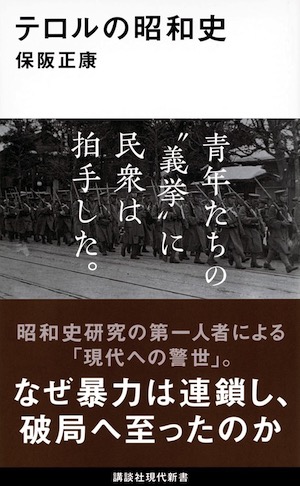
昭和5(1930)年の浜口雄幸首相刺殺事件から昭和11(1936)年の二・二六事件まで、要人に対するテロ事件(または未遂事件)が10件以上も発生し、その影響で、日本は恐怖政治、軍事独裁の道を歩むことになった。その暴力性は国内だけでなく対外にも向けられ、それが太平洋戦争の軍事的暴走、国家的崩壊に繋がったのだとするのが本書の主張である。本書では、それぞれのテロ事件について個別に取り上げ、その背景や性質を丹念に読み解く。
著者はかつて、事件に関わった生存者たちにもインタビューして、それを著書にもまとめた人で、日本近代史の分野では実績も名前もあるお方である。本書にもその聴き取りを反映し、それぞれの事件を冷静な目で捉えようという意図が感じられる。特に二・二六事件はきわめて残虐で、そこに至るまでに各テロ事件が前振りとしての役割を果たしているなど、鋭い歴史観がユニークである。
特筆すべきことは、五・一五事件の裁判で、減刑嘆願書が大量に法廷に届けられ、しかも法廷が被告人たちの思想の開陳の場になった、マスコミや裁判官までもがそれに同情的になり、結果的に軽微な処罰で済まされたことがその後の軍人によるテロの引き金になっているなどの指摘は非常に興味深い。一方で犯人たちの身勝手な理屈(襲撃された者たちは国賊であるため天誅を受けて当然)には非常に不愉快な思いもする。こういう自己中心的な理屈が一部でも肯定されてしまうと、自分の感情がすべてに優先されるべきという自己中心主義がはびこっていくのもある意味当然なのかも知れない。したがって、我々はこういった自己中心主義に対しては、本来断固とした態度で臨まなければならないのである。
本書では、教科書的な事実の羅列に終わらず、同時代的な視点が盛り込まれ、臨場感に溢れた記述が続くため、最初から最後まで引きこまれる。暴力が公然と容認され暴力がはびこる社会がどのようなものになるのか、本書を通じて追体験できるとも言うことができる。
著者は、安倍晋三殺害事件や岸田首相襲撃事件についても触れており、これに対する同情的な心情(特に安倍事件について)が溢れていることについても、テロを容認することは暴力の肯定に繋がるとして、警鐘を鳴らしている。今や世界中でこういった暴力肯定の風潮が溢れていて、空恐ろしさを感じるが、歴史を振り返ることでもう一度ことの問題性を整理することが重要であるとあらためて感じるのだった。