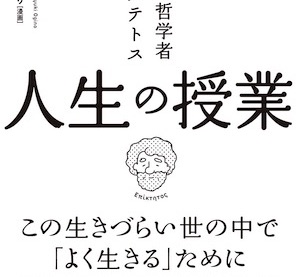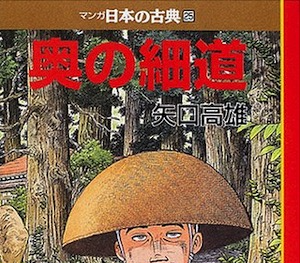純粋理性批判〈1〉
イマヌエル・カント著、 中山元訳
光文社古典新訳文庫
画期的な翻訳書の第1巻

『純粋理性批判』は、形而上学の難題に一つの決着を付けたエマニュエル・カントの代表作だが、日本語で読める版は、どれも翻訳が奇怪で、意味がさっぱりわからない。だが実際には、それほど奇矯なことが書かれているわけではなく、整理しながら読めば理解はできるはず。実際、僕自身は、すでに数冊のカント入門書に当たっており、カントの主張することはおおむね理解しているつもりである。しかし日本語版の『純粋理性批判』を読むと途端に首をひねってしまう。なにしろ突然「悟性」や「理性」などという単語が出てきて、理性は何となくわかるが悟性などという言葉は日常で使うこともないし、一体何を表現しているか見当が付かない。オリジナルのドイツ語版ではこの「悟性」という言葉、Verstand(つまり英語で言うUnderstand)になっていて、理解する能力のことかとなんとなく合点が行ったが、悟性という言葉がわかりにくいことには変わりない。本来であればこの用語から検討する必要があると思うが、日本の保守的な哲学界では、昔使われた翻訳語をそのまま踏襲するのが常で、日本語訳語の難解さは、そのまま残されたままである。以前も書いたが、カントはことさらに難解な書物を書こうとしたわけではなく、出版当時、わかりにくいという批判を浴びて何度も改訂版を出してわかりやすくするよう努めたと言われている。したがって、日本語版にしても、(多少難しいとしても)なるべく原書に近い感覚で読めるのが理想なのである。
そういう時代に一石を投じる出版物が、光文社の「古典新訳文庫」というシリーズで、この文庫シリーズ、「いま、息をしている言葉で、もういちど古典を」というコンセプトの下、さまざまな名著を翻訳し直している。結果的にそれが実現できているかどうかはともかく、読みやすい文章で翻訳し直すという姿勢に対しては拍手を送りたい。実際これまで何冊か読んでみたが、翻訳としてはどれもまずまずで、読みやすいかどうかは別にして、へんてこりんな日本語が出てきてうんざりするということはない。
このシリーズに『純粋理性批判』が登場したのはもう10年近く前になる。全7巻になるというのも驚きだった(岩波文庫版は全3巻)が、当時まだ第1巻が出てきたぐらいのところで、これからゆっくり配本していくという話だった。個人的には、そいういう悠長な話に付き合っていられないという感覚だったため、あまり関わることはあるまいと思っていた。とは言え、関心はあったため、第1巻を買ってみて、少しだけ読んだ状態で、積ん読が続いていたのだった。そうこうしているうちに年月は流れ、全7巻すべて発行され、いまや『実践理性批判』まで出ている。
そういういきさつがあったんだが、少し前にもう一度読んでみようかと思い立ち、読み進めることにした。1冊まるごと読み終えられるかどうかはわからないが、とりあえず時間のあるときに読んでみようということでスタートし、先日第1巻を読み終わったのだった。
この『純粋理性批判』だが、まず用語から見直しをしており、「悟性」を「知性」、「表象」を「心で思い描いた像」や「概念」、「統覚」は「自己統合の意識」などと言い換えている(「訳者あとがき」より)。かなり思い切った英断だが、結果的に読みやすさにつながっているように思う。また、原文だけではわかりにくいことから文章中に補足している箇所も非常に多いが、これもすべて[ ]で囲って明示しているため、原文から著しく離れるということはおそらくない。非常に良い配慮だと思う。さらに言えば、「大きなブロックごとに7冊に分けることにした」ということで、そのために全7巻構成になっているということなのである。それぞれの工夫に意図と配慮が感じられ、翻訳書として大変好感が持てる。
この第1巻は、(当然のことながら)『純粋理性批判』の冒頭部分になり、「超越論的な感性論」および序文(第二版)と序文・序論(初版)である。序文や序論は、これまでは飛ばしてきたが、今回、本文の後に配置されていたこともあり、内容が割合よく頭に入ってきた。このあたりも訳者の工夫のおかげと言える。序論でありながら、梗概みたいな役割を果たしており、後に配置するというのも筋が通っている。実際この序論を読んでみて、興味深い内容であると感じた。
この「超越論的な感性論」は、人間の認識機能について検討するという内容で、カントによると、人が現象を認識するとき、空間と時間という形式に従って感性がその表象(つまり「心で思い描いた像」)を獲得する、というようなしくみでそれぞれの機能が働くらしい。ちなみに空間と時間というのは、先験的(経験によって得られるものではないという意味で、本書では「アプリオリ」と表現される)なものであり、現象はあくまで実体としてではなく表象として得られるのだということ(だと思う)。このそれぞれの要素について、微に入り細を穿つように検討していくのである。
この「超越論的な感性論」と序文をあわせると大体250ページで、それに続いて130ページに渡る訳者による解説が出てくる。正直この「解説」が読みづらく、一応原文の参照ページは随時明記されているが、学術研究をやろうという人でなければ一々原文を参照したりしないだろうし、参照したところで読み直しを迫られることになる。しかも、表現がかえってややこしくなっていたりして、わかりにくさもひとしおである。わかりにくければ別に読む必要はないんだが、そうすると「この本を読んだ」と言えなくなるんではないかと思ってしまう。第1巻の内容の復習程度の役には立っているので、この「解説」を読んだことを別に後悔はしていないが、第2巻以降は、解説は読み飛ばすかも知れない。
いずれにしてもなかなかに意欲的な訳書で、第2巻も続けて読んでみるつもりである。もちろん『純粋理性批判』の内容は大体理解しているつもりではあるのだ。それでも直接著作に当たってみるということも大事だと思う今日この頃であるため、時間を見つけて何とか行けるところまで行ってみたいと思う。