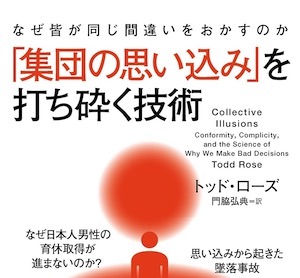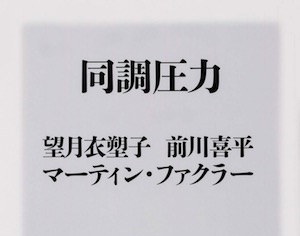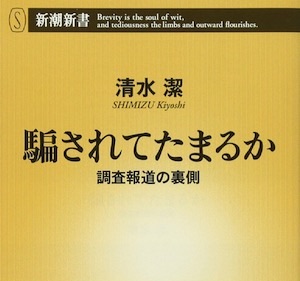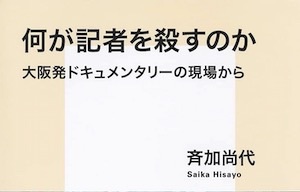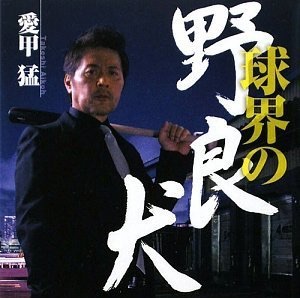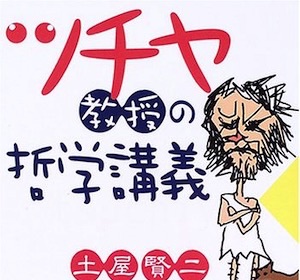ストーリーが世界を滅ぼす
物語があなたの脳を操作する
ジョナサン・ゴットシャル著、月谷真紀訳
東洋経済新報社
あなたの思考は誰かの言説によって操られている

人の考え方や行動の仕方は、他人が発したナラティブ(語られたストーリー、物語)によって影響を受ける。これは太古から受け継がれたもので、社会学的な観点では、この機能によって、社会の結束が強まったり、相互間の関係性が維持されたりすることになるという。
こういうナラティブが小さいコミュニティで共有されている分には問題はあまりないが、これが現在のようにグローバルに展開するといろいろと問題が出てくるというのが本書の主張である。中には、嘘だらけのナラティブもあり、それを信じ込む人々も少なくないわけで、それが現在のような分断を生み出しているというのが、本書のテーマである。
広く受け入れられやすいナラティブは、敵・味方(悪玉・善玉)が登場して、(悪玉が、容認できないほどひどい仕打ちをするなど)聞き手に激しい情動を生み出すようなドラマチックな展開があり、最終的に善玉がその悪玉に勝利するというようなわかりやすいものになる、と著者はいう。その際、悪玉が聞き手に大きな憎しみを生み出すほど、そのナラティブは影響力を増すらしい。「驚き、畏怖、恐怖、不安、希望といった活性化する感情をより強く」もたらすものがより強いインパクトをもたらすということで、キリスト教が広く普及したのもそういった要素を持っていたためだとする。また、レーニン、ヒトラー、毛沢東、金日成もこの類の「ストリーテラー王」であると断定しているあたりはなかなか痛快で、同時に鋭い洞察であると思う。
書かれている内容は、このように斬新で面白い内容が多いが、全体的に語りが冗長かつ雑談風で、もう少しポイントをしっかり押さえた書き方にしてもらいたいものだと、読みながら終始感じていた。ノンフィクションであるにもかかわらず、記述がエッセイ風と言えば良いのか、あるいはそれが著者によるナラティブなのかも知れないが、読んでいて、冗長さが少し苛立たしく感じる。
ただ著者が主張している、成功するナラティブ(物語)の形式をしっかり把握しておけば、それが情報の取捨選択を行う上で非常に有効なツールになるのは確かである。多くの人々がこういうことに気づいていれば、馬鹿げた言説に踊らされることも少なくなるのではないかと思う。また、勝手な思い込みで誰かを悪者にすることが1つのナラティブの影響に過ぎないということが理解できれば、世界を多様な観点で見られるようになるのではないかとも感じる。そういう点で、本書の主張は非常に有用である。この主張自体が、世界中の人に知ってもらいたいナラティブと言うこともできる。