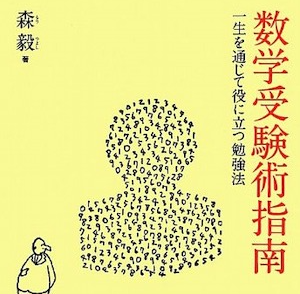知能指数
佐藤達哉著
講談社現代新書
IQがいかにいい加減なもので、
誤った使われ方をしているか、
その歴史から説き起こした本。
真摯な本だが、少し退屈。
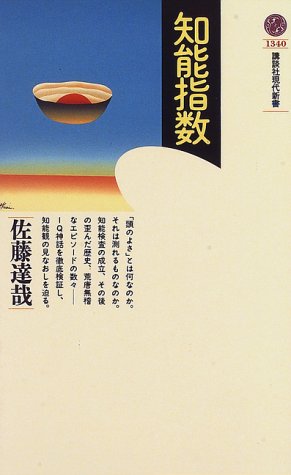
IQ、つまり知能指数は、一般的に頭の良し悪しの基準として世間で利用されている。自分のIQが150以上であることを自慢気に語っている芸人などもいて、見ていると非常に不快さを感じるが、そもそも頭の良い人(そういうものがあると仮定して)のIQが高いと思い込んでいること自体、あまり頭が良くないんじゃないかと感じるのは僕だけか。
大体、知能指数という指標自体、相当怪しい……ということは、実はこの本をかつて読んで知ったわけだが(今回読むのは二回目なのだ)、頭の良し悪しというのが本当にあるのか、あったとしてその頭の良し悪しを図る指標が存在するのか、万一存在するとしたらその指標がどの程度信頼できるのか、などと本来であればいろいろ疑問に感じるべきところなのである。頭の良い人というのが本当にいるのならば、そういう疑問を抱く人こそ頭が良い人ということになるんじゃないかと思うが如何。
という具合に知能指数には、いろいろと怪しさがつきまとっていて、強いて言えば占いみたいなもの……というふうにこの本を読んだ今では思える。
本書によると、人の知能レベルを外的基準で判断しようという試みは、過去いろいろな人間によって試みられてきたが、現在の知能指数の直接的なルーツと言えるのは、フランスの心理学者、ビネが作った知能検査ということになる。ビネは、学習障害児童を、一般の児童と分けることで彼らに対して適切な教育を施すべきと考え、そのために一般的な児童と比較して思考力や認識力の未発達度を測る目的で知能検査を作った。
その後、この検査は世界中で受け入れられ普及していくが、ひとり歩きするがごとく、別の意味あい、つまり人の優等性と劣等性を見極めるための基準として使われるようになる。たとえば、アメリカで黒人の集団と白人の集団に知能検査を施し、白人の集団の方が結果が良好だったことから、白人の方が優等で黒人が劣等であると結論付け、差別の助長に利用されるということも行われた。こうして、知能検査は、初期の目的から徐々に逸脱していく。ちなみにこの白人・黒人に関する試験結果については、現代の科学的な観点であれば、環境など他の要因も勘案しなければならないのは火を見るより明らかである。要は、差別を助長するために意図的に使われたのであった。
このような歴史的経緯を経て、知能検査、そしてそこから算出される知能指数は、人の知力を客観的な指標で計測できるかのように信じられるようになり、人の知力の優劣を測定する目的で使われるようになった。その過程で、知能検査の正当性や正確性などは検討対象から外され、既定事実になってしまったのが現状……というのが著者の主張である。
つまり、あるかどうかわからないものを、正当に測れるかどうかわからない道具を使って調べ、それが絶対的な指標であるとされているのが現在の状況ということである。そしてその指標が、ともすれば差別や選別に利用されているというのであれば、社会レベルで根本的に疑義を呈すべき事柄なんだが、本書が最初に出版(1997年)されてからも、状況は一向に改善していない(本書は現在絶版中)。
「頭が良い」ということに対する過剰な信仰が世間に蔓延して、中には有名大学の学生のことを「天才」などと呼んでいるテレビ番組まで出てきて(学校の勉強ができるのと「頭が良い」というのは別物だとしか思えないが)、そういう現状を見ると、世間全体の(あるいはマスコミだけかも知れないが)知能が劣化しているようにも見える。当たり前だと思われているものごとを根本から検討し直すことで、日本を今一度洗濯いたすのも良いんじゃなかろうかと思う今日この頃である。