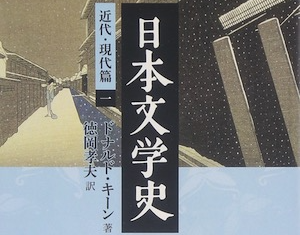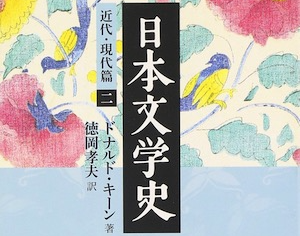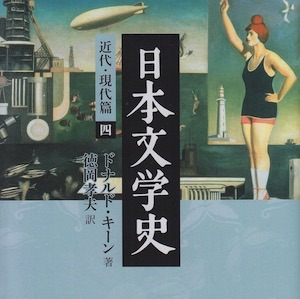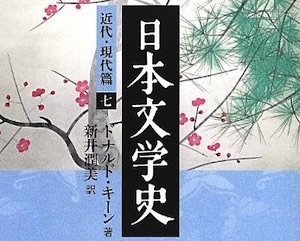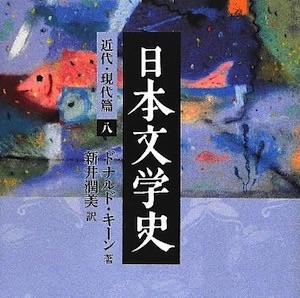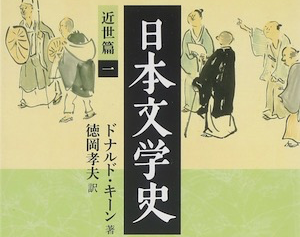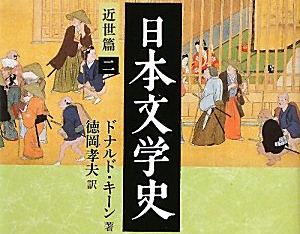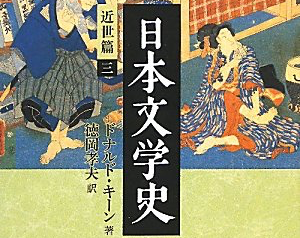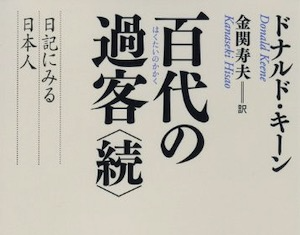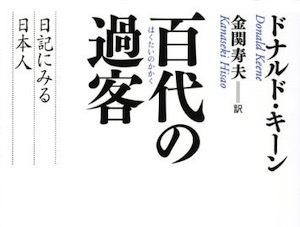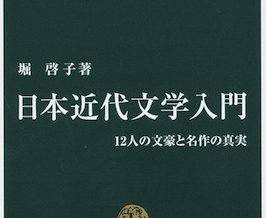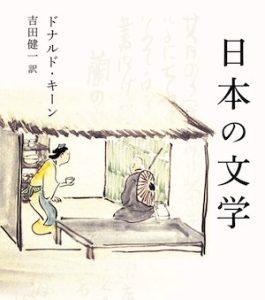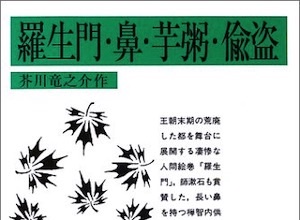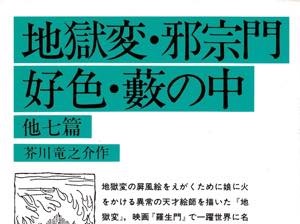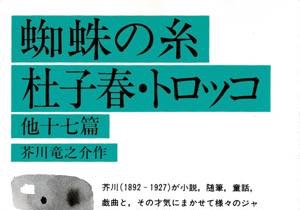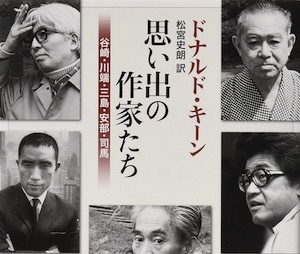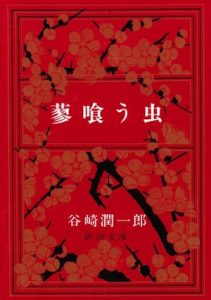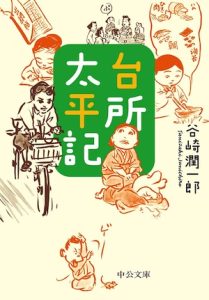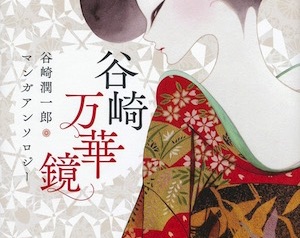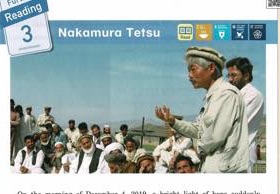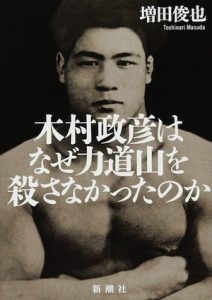日本文学史 近代・現代篇〈三〉
ドナルド・キーン著
中公文庫
大正時代の日本文学史
プロレタリア文学の動向が異色で面白い
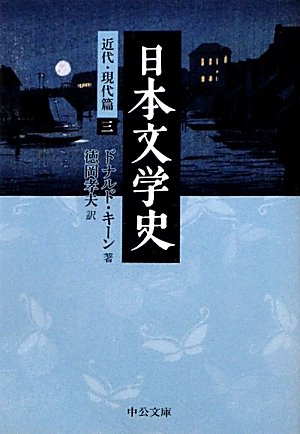
ドナルド・キーンの畢生の大作、『日本文学史』。これまで、『日本文学史 近代・現代篇〈二〉』まで読み進めていたが、やっと『〈三〉』を読み終わった。『〈二〉』を読んだのが2021年だったため、4年経って読了したわけである。このペースで読むと、死ぬまでに全部読み終えることはできなさそう。
それはともかく、『近代・現代篇〈三〉』である。本書は、「プロレタリア文学」、「芥川龍之介」、「永井荷風」、「谷崎潤一郎」の4章構成になっており、それぞれの章ごとに各テーマについて時系列で紹介される。『近代・現代篇〈二〉』でもそうだったが、著者が関心を示す特定の作家への比重が高いという印象で、そのために芥川龍之介より永井荷風みたいな偏りがある。もっとも芥川龍之介は世間的な評価が高いことから論じられることも多いため、永井荷風の方に紙面を割く方が価値があるとも言える。ただ永井荷風については、僕に対してアピールするものはあまりなく、「永井荷風」の章は、僕にとって本書でもっとも退屈な箇所になってしまった。
「プロレタリア文学」、「芥川龍之介」、「谷崎潤一郎」の章については、時系列で紹介されている上、内容もきわめて具体的で詳細であるため、非常にわかりやすく、しかも著者の主張もよく伝わってくる。日本文学研究者としての著者の水準の高さをあらためて感じる。
次の『近代・現代篇〈四〉』は、「モダニズム」、「川端康成」、「転向文学」がテーマで、あまり食指が動かない。『近代・現代篇〈五〉』が太宰治らの戦後派、『近代・現代篇〈六〉』が戦後文学と三島由紀夫というラインナップで、ここまでが『近代・現代篇』の一区切りになる。『近代・現代篇〈四〉』は今読んでいる最中だが、少し退屈しそうな雰囲気である。