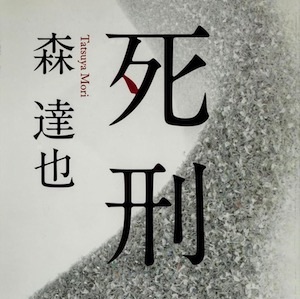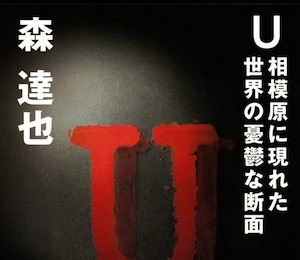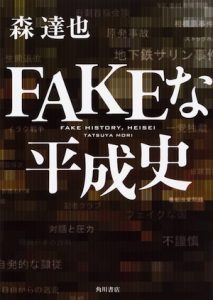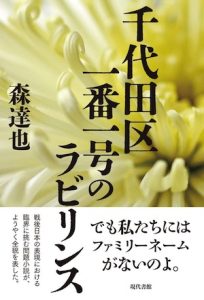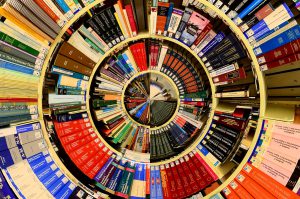たったひとつの「真実」なんてない
メディアは何を伝えているのか?
森達也著
ちくまプリマー新書
画期的な映像論
あらゆる教育現場で語られるべき

ドキュメンタリー作家の森達也による映像論。ちくまプリマー新書シリーズの一冊で、中高生などの若者向けに書かれた本である。したがって文章も学校の授業で話しているような語り口になっている。
基本的には、ニュースなどの映像は必ずしも真実を映しているものではなく、撮影者の気持ちを反映したものであるため、100%信用するのではなく、映像に対して批判的な目を常に向けるべきとする主張である。
映像は、その現場の状況を100%伝えるかのように見えるものだが、実際は、意図的ではないにしても、撮影者の一定の価値観に基づいてどこを切り取るかが決められている。ドキュメンタリーの場合は特にそれが顕著になるため、公正中立というのは、建前はともかく実際にはあり得ず、撮影者の価値観が如実に反映されるものであるという、ドキュメンタリー作家の率直な見解が示されている。さらに編集過程を取ってみても製作者の意図が如実に反映されると主張する。
本書では一例として、学校の授業の映像が紹介されている。ある学校の様子として先生の授業風景が映し出され、その間に真剣な顔で一生懸命聴いている生徒の映像がインサートされる場合と、あくびをしている生徒の映像がインサートされる場合で、視聴者の感じ方が違うということが示されている。前者の場合、その授業が白熱しているというメッセージになり、後者の場合は集中力を欠いた退屈な授業という印象を視聴者に与えることができる。作り手は、当然自分の感じ方に基づいて、そういう映像を挟み込むわけだが、その感じ方が客観的な事実であるかのように視聴者に伝わる。したがって見る方にはその印象がそのまま伝えられるわけである。だがそれは決して客観的な事実ではなく、作り手の印象に過ぎないため、それを額面通り受け取るのではなく、映像とはそういうものというような割り切り方が必要になる。それが本書のメッセージである。
一言で言ってしまえばメディアリテラシーの大切さということになるわけだが、学校でメディアリテラシーについて教わってもなかなかピンと来ない。たとえ分かったつもりでいても、実際にはよく把握しているわけではないわけだが、映像作成側からこうした明確なメッセージを受け取ることで、映像の本質に少しは迫ることができる。YouTubeやSNSなどのネット上の映像媒体を安易に信じる人間が増えている昨今、本書のような議論があらゆる場所で誠実に語られるべきであると感じる。今のような時代には、本書で紹介されているような事象について、誰もが本来知っていなければならないとも感じる。