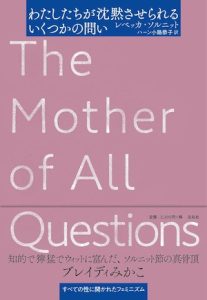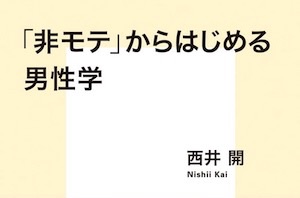私のいない部屋
レベッカ・ソルニット著、東辻賢治郎訳
左右社
「作家ソルニット」はいかにして誕生したか
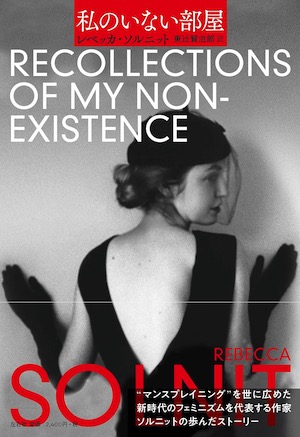
『説教したがる男たち』と『わたしたちが沈黙させられるいくつかの問い』を読んで、著者のレベッカ・ソルニットに関心が湧いたため、彼女の背景を知りたいと思いたって、「自叙伝」と紹介されていた作品を読んでみた。
実は、幼少時に経験したというDVが具体的に記述されていることを期待して読んだんだが、それについてはほとんど記述がなく、父が母に日常的に暴力をふるっていてそれを目にしていたことぐらいしかわからなかった。著者によると「世間にありふれたことであるため書く必要はない」ということらしいが、著者のその後の指向を決定づけた事例であるため、読むこちら側としては是非とも知りたかったことである。こういうことを考え合わせると、「自叙伝」というには物足りなかったという印象を受ける。もちろん「自叙伝」というキャッチフレーズは出版社側がつけたもので、本書の中にはそのような文言は出てこない。したがって、出版社側の責任またはこちらの勝手な思い込みが、今回の物足りなさに繋がったと言える。
本書は、著者の来歴について、一人称的な視点で語っている。特に17歳の時に家を出て、サンフランシスコ州立大学に入ってから後の精神的・思想的な遍歴についてはかなり詳細に記述されており、先住民の運動や環境問題に関わった経緯や、これまでの著書を書くに至った経緯なども事細かに書かれている。そのため、作家、レベッカ・ソルニットの背景はよく理解でき、そういう意味では「自叙伝」として十分機能している。
男から殺されそうになり危うく一命を取り留めた友人女性や、同じく男たちからいつ危害を加えられてもおかしくない自分の立場(若い頃の自身のアイデンティティ)などが率直に語られているため、そういう著者が、迫害・虐待されている人々に対して共感を抱いてきたのも、本書を通じてごく自然にイメージできる。さらには、自分の姿勢が変わるきっかけになった美術館での臨時職員の経験、出版社での勤務経験についても語られ、作家ソルニットが誕生するまでの過程も詳しく知ることができる。
それにつけても、僕にとっては、原体験の記録がもっとも興味があった部分で、それは何らかの理由で書けなかったのかも知れないが、その点が大いに不満の残る点ではある。それでも、先述したような理由から十分読み応えがある良書であるのは間違いない。一方で、ソルニットらしいかなり回りくどい表現も多く、多少読みづらさを感じたりもする。