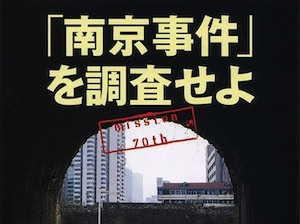西園寺公望 最後の元老
岩井忠熊著
岩波新書
1人の有力政治家の視点で
日本近現代史を俯瞰する
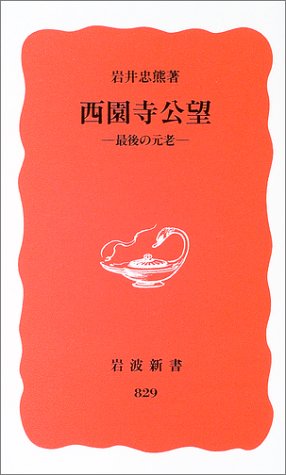
歴史を勉強しようと思うと、最初はどうしても教科書的な素材を探すことになる。日本の近現代史についてもしかりであるが、しかし、なぜ大日本帝国が英米戦という暴挙にのめり込んでいったかというその過程がなかなか見えてこないという現実がある。教科書の限界である。そこで今回少し変わったアプローチを考えた。要するに、当時生きていた特定の当事者の視点から、その同時代の歴史を捉えようという試みである。
で、いろいろ物色したところ、西園寺公望が適任ではないかという結論に達した。というのも、西園寺という人は、若い頃フランスに長期に渡りとどまっていたこともあり、当時としては非常に開明的で自由主義的なものの見方をする。そういう点で、多くの現代人の感覚に近いと言える。そのため、我々が西園寺の視点に立ってもまったく違和感がない上、そういう人間が軍部の暴走をどのように見て感じていたかは、現代人にとって大いに参考になる。しかも西園寺は、幕末からほぼずっと政権中枢に関わっており、首相も2回経験している上、その後は天皇の側近としての役割である「元老」の職に就き、戦前の歴代首相の指名にも大いに影響力を発揮している。したがって西園寺の歴史イコール日本の近現代史と言っても過言ではないという、その程度の力はあったわけである。
実際のところ、西園寺は、大陸への覇権拡大、日中紛争の拡大、軍部の台頭に対し一貫して反対の立場を取り続けていることが本書からわかり、結果的に彼の求心力の低下に伴って、政党政治の瓦解、軍部の暴走が進んでいったという印象を持つ。ちなみに、本書が底本にしているのは西園寺公望の秘書を務めてきた原田熊雄の手記『西園寺公と政局』である。西園寺自身が、死ぬ間際に自身の伝記や評伝を一切拒否しており、資料も処分するよう遺言しているため、記録は乏しく、そのあたりが悩ましいところであるが、側近であった原田の記録が、西園寺の考え方、行動をかなり正確に捉えているという可能性は否定できない。
著者自身も、戦後まもなくの1950年に、当時刊行されたこの本を初めて読んで、西園寺の開明的な視点に驚嘆したらしい。また、国民が政治過程について知らされていなかったことを痛感し、同時に西園寺が「大陸への新たな侵略戦争と軍部の政治的台頭に反対し、国際協調と平和を求めたことには、考え及ばなかった」(本書「あとがき」より)と感じたということである。
本書で見る限り、日本をファシズムに走らせた最大のターニングポイントは、張作霖爆殺事件の首謀者を正しく処分しなかった田中義一内閣の時代だったと思える。田中義一はこの件について昭和天皇から叱責を受け、そのショックで翌年死んでしまったらしいが、しかしその責任は非常に大きい(昭和天皇自身も田中の死について自分の責任を感じ、以後政局に口出ししないことにしたという。これも軍部の暴走を助長する結果になった)。ましてやこの田中義一内閣が、「憲政の常道」と言われていた時代の政党内閣であったことも重要である。問題の根源についてきっちり総括せず野放しにしてしまったことが、軍部の暴走を招くことになったわけで、このような事なかれ主義がどれほど危険であるか、この事例からもよくわかろうと言うものだ(現代の政治にも通じる問題である)。
また軍部、特に陸軍に大幅に譲歩した広田弘毅内閣、近衛文麿内閣にも大きな問題があったことは今さら言うまでもない。この辺は東京裁判でも明らかになっている。ただ、東京裁判自体は、「裁判」と呼ぶのも恥ずかしいぐらい、非常に政治的で恣意的なものである。もちろん、それまで隠されていたさまざまな事実を明らかにするという役割は果たしているが。結局のところ、先の愚かな戦争について真の意味で総括すべきなのは、現代日本に生きる我々一人一人なのではないかと感じる。そういう点から、陸軍の暴走軍人は言うまでもないが、田中義一、広田弘毅、近衛文麿が政治家として責任を負うべき存在なのではないかという結論を個人的に出したいと思う。もちろん、1920年代、30年代の政党が、ライバル政党に打撃を与えるためと言え、統帥権干犯などの愚かな議論を巻き起こしたり、利益誘導や腐敗の問題で有権者の不信を招いたことも大きい。しかも国民の多くも日中戦争や太平洋戦争の戦局拡大で狂喜乱舞していたというんだから、政治家や軍人だけではなく、多くの庶民、そしてそれを煽ったマスコミすべてが責を負うべきという結論になる。愚かな国民の元では愚かな政治体制しか生まれないということになるわけで、西園寺が晩年語ったという「いろいろやって見たが、結局、人民の程度以上にはならなかった」というところに結局落ち着く。これは、現代社会にもそのまま当てはまるんだから困ったもんである。