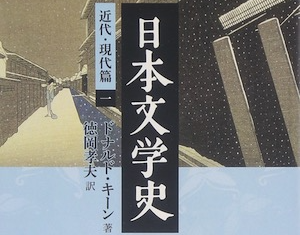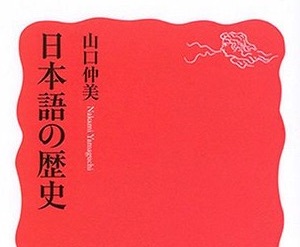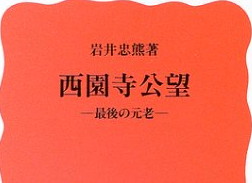日本語を作った男
上田万年とその時代
山口謠司著
集英社インターナショナル
無駄に長い!
しっかり推敲していただきたい
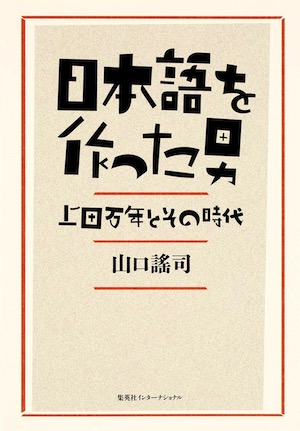
現在我々が文章を書くために使う日本語は、ほぼ話し言葉の口語体であるが、明治期の文学などを読むと、擬古文だったり漢文調だったりすることがあり、現代語とかけ離れているため非常に読みにくい場合がある。ではいつ明治文学が口語体で書かれるようになったかというと坪内逍遙や二葉亭四迷が推し進めた言文一致運動がそのルーツだと一般的には言われている。
ところが先日新聞を読んでいると、書かれたものが言文一致になったのは坪内や二葉亭の功績ではなく、上田万年という人の功が大きいという記述があって興味を抱いたのが始まりである。そこで紹介されていたのがこの本で、これはぜひ読まなければなるまいと思ったわけだ。
この本500ページを超える大著で、言文一致体の導入にそれだけのバックグラウンドがあるのかと最初は感心していたが、何のことはない、要はこの本の完成度が低いことが(長尺の)原因だった。とにかく引用がやたら多く、しかも話題があちこちに飛びまくって読みづらいったらない。大きく第1部と第2部に分かれているが、第1部は八割方読み飛ばしてもかまわないというような代物で、テーマに関係ない事項が次から次へと繰り出されてくる。もちろんここで紹介される明治期の文化的背景を知ることは大切ではあるが、読んでいる途中で、次々に新しい事項が現れると、どこに連れて行かれるかわからないような不安感に襲われる。しかもそれが、直接テーマに関係しない出来事であることがわかると、読み続けることに無意味さすら感じるようになる。はっきり言って第5、6、8、10、12、13、14、15、16章はなくてもよいし、他の章も半分くらいに削るべきだと思う。さながら(冗長な先生による)学校の講義であるかのように、テーマがどんどん逸れていくというのがこの本の特徴で、そういう点で「言文一致」を実現する必要もなかろうと思う。観念奔逸のように新しいテーマをどんどん盛り込むんではなくて、本として読ませるんだからテーマを一点に絞るべきで、それが良い本への第一歩である。少なくともそれが読者に対する配慮というものである。
またよくよくこの本を読んでみると、言文一致運動の功が上田万年にあるなどということはまったくもって言えない。上田万年という人は、東京帝大で言語学を教えていた人で、文部省の国語関係の審議会のメンバーも努めていて、書き言葉を言文一致体にすることを国の標準にするため力を尽くした人であるが、最終的に1908年の臨時仮名遣調査委員会では、(本書によると、森鴎外の強烈な反対によって)上田が進めていた新仮名遣いが不採用になっているし、結局のところ大した実績は残していない。坪内や二葉亭の功績の方がはるかに大きいし、言文一致運動もどうも文学界(本書によると、特に漱石の作品)を中心に進んでいったという印象しか残らない。つまりこれだけの大著を一生懸命読みながら、最後はこれかい!というようなオチで終わってしまうと、読む側としてはかなりの落胆を受けることになり、徒労感だけが残ることになる。「日本語を作った男 上田万年とその時代」というタイトルは、「日本語を作った男たち 上田万年の時代」と改める方が中身を正しく表している。結果、無駄にダラダラ長い本で、拾い読みに適した雑学本という結論に落ち着くのだった。