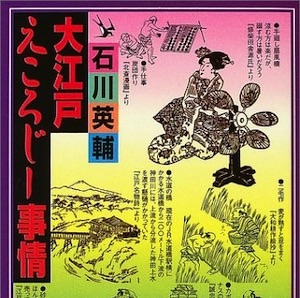森の探偵
宮崎学、 小原真史著
亜紀書房
森の巨匠が見たヒトと動物

森に入って動物写真を取りまくっている宮崎学が、動物写真から読み解く「現代日本の環境」論。
赤外線を使いカメラのシャッターが自動的に降りるようさまざまな工夫を重ねることで、森、林の生きた動物を撮影することをライフワークにしている宮崎学。彼の写真には動物たちの生々しい生態が記録される。宮崎自身が、森に入れば足跡や糞などからどんな動物が近くにいるかわかるようになっているらしいが(何せ森の生活が長いから)、彼によると動物が人に接近しているその近さはかつてないほどになっているということ。
実際、あちこちでツキノワグマに襲われたとか、イノシシが町に出没したとかそういったニュースはよく耳にする。「専門家」は、森林破壊によって山に食べ物がなくなったため、動物が命がけで里に下りてきたなどと語るが、宮崎によると山の食べ物がなくなったという事実はないらしい。むしろ人間が何気なく捨てたり放置したりするものが、知らず知らずのうちに動物たちの餌になっている、つまり人間が間接的(または直接的)に餌付けしていることが、野生動物を身近に引き寄せている……というのが宮崎学の実感らしい。
たとえば犬を散歩させる人々がよく通る公園の道などにカメラを仕掛けていると、人が通ったすぐ後にクマが出てきている様子が映っていたりする(しかも割合多いという)。つまりクマの方が身を潜め、人が通り過ぎるのを待ってから、出てきて用事をしているということになる。ヒトを避けているクマが誤ってヒトに遭遇し(一般には「人間が誤ってクマに遭遇する」と言われるが)、接触事故が起きるというのが本当のところではないかと宮崎は言う。
他にも動物たちには死体処理の役割を担っているもの(スカベンジャー)があり、そのために環境が浄化されるなどの興味深い話が展開される。野生のクマ自体がそもそもスカベンジャーであり、肉に対するこだわりがない(つまり事故で死んだ人の肉も普通に食べたりする)ため人の肉にも抵抗がないということが、「人喰い熊」の存在の説明になるらしい。宮崎の言葉は、実際に森や林の動物を写真を通じてつぶさに見続けている(野生に近い)人間から発せられるものであり、非常に説得力がある。動物写真もふんだんに紹介されており、そういう点では大変良質な本である。「目からウロコ」の話も数多い。
ただし、1つ大きな難点がある。この本は「キュレーター」という肩書きの小原真史という人と宮崎学の対談形式になっているんだが、この「キュレーター」がしゃべりすぎというか、知識をひけらかしたいのか知らないが蘊蓄を語りすぎである。これがかなり鬱陶しいレベルで、これさえなければ良い本なんだがと思うこと数知れず。話の聞き手に徹して、宮崎学という森の巨匠から実感に基づくいろいろな素晴らしい話を聞き出せば良いものを、自分が聞きかじったような知識を必要以上(!)に披露するその感覚が理解できない。はなはだ残念。