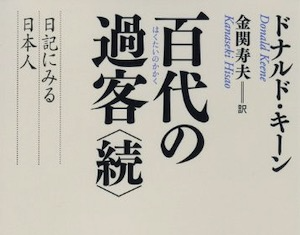日本文学史 近代から現代へ
奥野健男著
中公新書
ありきたりな歴史観に基づく評論

文芸評論家による近代日本文学史。
明治時代、言文一致体が擬古文に替わって日本に定着した過程を知りたかったんで今回読んでみたが、著者によると、言文一致体は江戸時代からすでに戯作の中に見られたため、それ自体はさして重要ではないし、それほどのエポックではないということだ。それよりもむしろ、明治の文学界にとって重要だったのは、江戸期から続く(低俗な)戯作から芸術への脱却にあったというのが著者の主張である。
それはそれで説得力はあるが、ただ全体としてどことなく著者の主張には芸術至上主義が感じられる。つまり純文学が是で俗な文学が非という感覚が伝わってくる。俗なものにもすぐれたものはあるし芸術指向のものにしても多くは駄作であると僕などは思うんだがな。
それにどことなく一種の唯物史観のようなものが見受けられるのも、歴史の記述という点では疑問符が付く。つまり、低俗な江戸期の文学がヨーロッパの(優れた)文学に追いつく過程がさも当然で必然であるかのような記述が多いんだが、歴史観という点で受け入れがたい。明治、大正期にヨーロッパの優れた文学に対する憬れがあったのは確かだろうが、それは当時の日本がそういう状態にあったというだけで、ヨーロッパ的な価値観で言う「文学」的な要素がないからといって、価値が低いとする考え方は近視眼的な印象を受ける。
現在から振り返っても、明治期、大正期の文学には独特なものがあり、決してヨーロッパ的な水準で見るべきではない。芸術作品の価値を云々するためには超時代的な見方をしなければならないと思う。そういったあたりがこの本の限界かなと感じる。
また、特に後半になると、作家名、作品名が羅列されるだけで面白味が感じられない箇所が多くなる。文学史ということになるとこういうことがよくあるが、こういうふうな紹介の仕方をするんだったらいっそのこと年表にでもした方が良い。また、取り上げられている作品の内容についても紹介してほしかったと思う。実際に原文に(少しでも)触れてみなければ、その作品を感じることはできない。そういう点でも物足りなさを感じた。
ただ、特に昭和の時代については、文学作品を取り巻く時代の空気みたいなものが伝わってきた。おそらく著者がその時代をリアルに生きたためだろう。そういう著者が膚で感じた部分というのが、本当のところ一番価値があるんで、本来であればこちらを中心に扱うべきだったと思う。頭でっかちで観念的な評論は、少なくとも僕にはあまり価値はない。