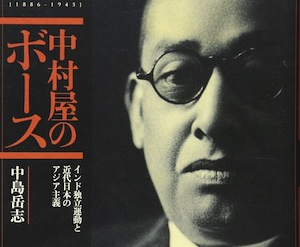チョコレートの世界史
近代ヨーロッパが磨き上げた褐色の宝石
武田尚子著
中公新書
ロウントリー社とその周辺の英国近代史が読みどころ

マヤ・アステカ文明で薬効のために珍重されたカカオが、その後、スペインのアメリカ大陸侵略によってヨーロッパに伝わって、ココアに加工される形で普及し、やがて固形のチョコレートに加工されるようになって、国際的な製品として定着することになった。その過程を時系列的に紹介した本。
タイトル通りで看板には一切偽りなく、しかも丁寧かつ律儀にカカオ史を追っているのであるが、なにしろ面白くない。教科書的というのであろうか、ともかく読むのに時間がかかる。文章も読みやすく図表も親切なのだが読むのに苦痛を感じる。ところが、記述が英国でのチョコレート・メーカーの話に移るあたりから読みやすくなり、内容も俄然面白くなった。特にロウントリー社(「キットカット」のメーカー)が、ココア生産で名を挙げやがてチョコレート生産に取り組んでいく過程が非常に面白かった。ロウントリー社の経営者たちが、社内および国内の福祉政策に積極的に取り組み、これがやがて英国の福祉政策に影響を及ぼしたなどという逸話はまったく知らない話で、目新しい事実であった。
著者が本書を書くに至った事情について「あとがき」で明かしているのだが、そもそもがシーボーム・ロウントリー(ロウントリー社の経営者)が行った英国での貧困調査の資料に関心を持ったことが始まりだったそうで、そこから「カカオの種類、ココアやチョコレートの製造、工場のしくみ、労働者の組織などについての知識が必要」と思い至ることになって、それが本書を生みだす遠因になったそうである。道理でロウントリー社以外の部分がつまらなかったわけである。すべて予備的な調査だからね。だが、当然のことながら、ロウントリー社やその周辺の英国近代史は非常に価値の高いものであり、読み応えがあって非常に興味深いものだった。また、ロウントリー社が生みだした「キットカット」に伺える同社の矜持(戦時中、原材料が十分得られないため質が落ちていることをラベルに明示し、赤ラベルの代わりに青ラベルを使うことでそのことを示した)、製造者・経営者としての気概や良心は、現代においても模範と言えるものであり、感動を呼ぶ。

ちなみに「キットカット」は、1973年に日本でも「マッキントッシュのキットカット」として不二家から販売されるようになった。「ここらで一服しませんか キットカット!」という歌に乗ったCMは当時非常に目新しく、僕などもキットカットをすぐに買ってみたクチであるが、その当時珍しいチョコレート菓子(ウェハースをチョコで包んでいる)だったこともあり、大変美味と感じた記憶がある。ロウントリー社がなにゆえ「マッキントッシュ」を名乗って日本で販売したかという事情も本書で簡単にではあるが紹介されている(今はネスレが販売元)。
なお本書では、終章の「スイーツと社会」という章で、第7章までの記述が非常にうまくまとめられている。つまり終章を読めば本書を全部読んだのとほぼ同じ知識が得られるということである。本書に興味のある方は、退屈な序盤・中盤を読み飛ばし、終章と「あとがき」(この部分もなかなか興味深い)だけを読めば、内容をほぼ把握することができる。さらに興味がわいた方は5章、6章、7章と進めば本書を十分堪能できるだろう。
付記
- ロウントリー社の良心が本書の中心になっていながら、現在のカカオ生産現場の児童労働などの問題がないがしろになっているのは、アンバランスさというか、ちょっと物足りなさも感じた。そのことだけ補足しておく。
- 日本にはいろいろな種類のキットカットがあるらしく、世界で100以上種類があるがそのほとんどが日本産ということである。興味のある方は『Wired Vision:日本みやげ、11種のキットカット食べ比べ』を参照されたい。