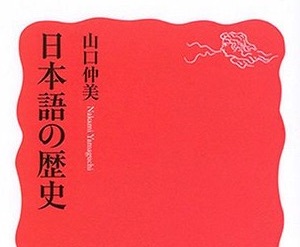読み書きの日本史
八鍬友広著
岩波新書
資料の寄せ集め

読み書き能力は、会話能力と違って自然に身に付くものではなく、一定の教育が介在して初めて成立する。したがって読み書き能力がどの程度社会に浸透しているかは、その社会の教育レベルを推し量るものさしになる。そういう見地に立って、読み書き能力が、日本の歴史の中でどのように発展してきたかを改めて検討しようというのが、この本の趣旨である。
本書では万葉時代から明治期に至るまでの日本人の読み書き能力を探るべく、さまざまな資料を寄せ集め、それを引用する形で記述している。特に鎌倉末期から明治初期まで使われた読み書きのための教科書、往来物(おうらいもの)について紙面を割いているが、これはおそらく往来物が著者の研究のテーマになっているためだろうと思われる。
それはそれとして、とにかく全編に渡って他書からの引用ばかりが続き、文字通り「寄せ集め」という印象を終始受ける。引用ばかりが続くため、読者側としては、著者が言いたいことは一体何なのかと問いかけることが続き、さながらネット上で見かけるキュレーションサイト(まとめサイト)を髣髴させる有り様で、書籍としての質の低さを感じさせる。いっそのこと最終章に「いかがでしたか。」とでも書いてほしかったと感じるほどである。あまりに引用が多いため、読んでいる途中で、これも昨今出回っている学位論文本(学位をとるための論文代わりとして機能させる書籍)ではないかと思ったほどだ(著者の経歴から考えるとその可能性は低い)。
最終的に著者は、江戸時代の識字率が世界最高レベルであったということに疑問を投げかけているが、ここで紹介される資料を見る限り、世界最高水準だったという結論もあながち的外れではないと感じてしまう。それを思うと、何のための資料の寄せ集めだったかすらわからなくなってくる。つまり著者の結論が、資料から類推される「仮説」から乖離していると感じられるわけである。さらに言えば引用している資料についても、疑問符が付くようなものがあり、そうすると資料も結論も非常に頼りないものだったと言うしかないわけだ。結局のところ、しょうもない本に長いこと付き合わされたという印象だけが残り、つまらない本だったという結論に落ち着くわけである。