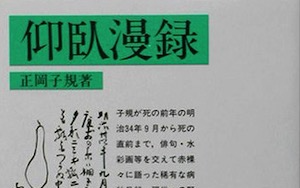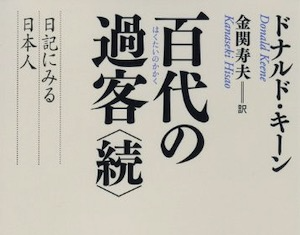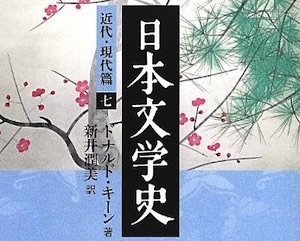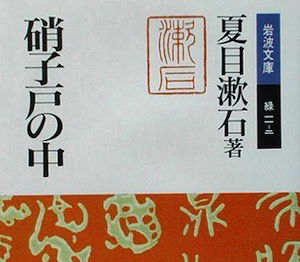飯待つ間
正岡子規随筆選
正岡子規著
岩波文庫
病床ものがやはり子規の真骨頂

正岡子規の随筆集。子規が生前、あちこちで書き散らした随筆を本書の編者(阿部昭)が拾い集めて、時代順に並べたものである(全部で29編)。初出誌は、前半は新聞『日本』、後半は『ホトトギス』が多い。子規が若い頃、新聞『日本』の社員であったことや、子規の晩年、弟子の高浜虚子が『ホトトギス』を編集していたことを考え合わせると、ある意味当然である。
年代順であるため、最初の方は軽妙なエッセイが多く、あまり目に留まるものはない。日清戦争の従軍記事(「従軍紀事」)が珍しいぐらいである。その後、脊椎カリエスが進行して闘病生活が始まり、やがて寝たきりになる。そのため、身辺を描いた記事が多くなり、病気や死を扱った記述も出てくる。このあたりが子規の随筆の真骨頂であるように思う。特に子規は筆まめで、しかも身辺のことを割合赤裸々に描写しており、しかもシンパの人(『ホトトギス』の読者)向けに書いたものが多いため、記述はきわめて率直で、生々しい。
自身の現在の境地が因縁のせいであるかのように描いた小説「犬」は、子規らしいユーモアを交えた一編であるが、最後の最後は痛々しさが漂う。なかなかの名編である。「初夢」は、方々を健常者のように訪れまわる自身の姿を夢に託して描いた一編で、こちらも読んでいて辛くなる。「死後」は自身が死んで墓に埋葬される様子を、こちらもユーモラスに描いた作品で、子規の病状を知っている読者にとっては「おもろうてやがて悲しい」という味わいがある。
「病牀苦語」は、『墨汁一滴』や『仰臥漫録』などに通じるテーマで、寝たきり生活の身辺や、その間に感じた思念をまとめた一編で、この随筆集の白眉と言える。また、死の三日前に、高浜虚子の口述筆記で書いた「九月十四日の朝」は、「死の三日前」であることを知っているだけに恐るべき迫力で逼ってくる。この2編だけで元が取れると思える逸品である。
総じてやや冗長で、前半は特に文語体が多く読みづらいが、後半の病床で書いた随筆は、他にあまり類がない経験でもあり、非常に読ませる。読みたいもの、興味のあるものだけをピックアップして読むと良い、という類の随筆集である。