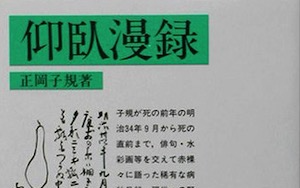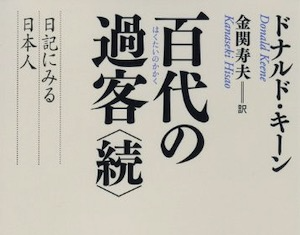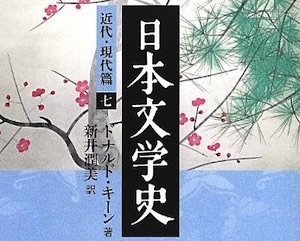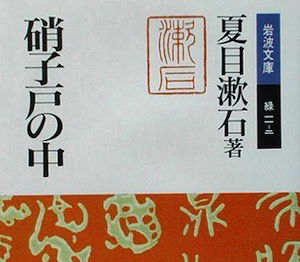墨汁一滴
正岡子規著
岩波文庫
寝たきりの詩人はヒマラヤに登る夢を見るか
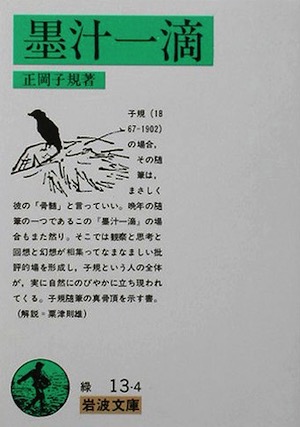
明治の歌壇、俳壇に革新をもたらした正岡子規は、晩年の3年間、脊椎カリエスのために寝たきりの生活を余儀なくされた。だがその間も随筆を毎日のように新聞『日本』に発表していた。明治34年(1901年)1月16日から7月2日までに発表した分をまとめたのがこの『墨汁一滴』である。それ以前の分は『松蘿玉液』、それ以降の分は『病狀六尺』としてまとめられている。
内容は自身の病気のこと、他人の俳句や短歌のこと、世間のことなどで、もちろん自作の歌、句も紹介している。しかしやはり、だんだん身体の機能を失いつつある自らの身辺を綴った記述がもっとも心を打つ。特に1月31日の
〈 人の希望は初め漠然として大きく後漸く小さく確実になるならひなり。我病牀における希望は初めより極めて小さく、遠く歩行き得ずともよし、庭の内だに歩行き得ばといひしは四、五年前の事なり。その後一、二年を経て、歩行き得ずとも立つ事を得ば嬉しからん、と思ひしだに余りに小さき望かなと人にも言ひて笑ひしが一昨年の夏よりは、立つ事は望まず坐るばかりは病の神も許されたきものぞ、などかこつほどになりぬ。しかも希望の縮小はなほここに止まらず。坐る事はともあれせめては一時間なりとも苦痛なく安らかに臥し得ば如何に嬉しからんとはきのふ今日の我希望なり。小さき望かな。最早我望もこの上は小さくなり得ぬほどの極度にまで達したり。この次の時期は希望の零となる時期なり。希望の零となる時期、釈迦はこれを涅槃といひ耶蘇はこれを救ひとやいふらん。〉
という記述は、今の自身の姿を客観的に眺めた冷徹な筆に心を打たれる。この随筆の中の白眉と言って良い。
それ以外は、他の歌人が詠んだ歌(『明星』に発表された落合氏の歌)をケチョンケチョンに批判しているあたりが、今読むと面白い。平賀元義という江戸期の歌人をべた褒めした箇所もあるが、こちらはあまり面白いとは思えなかった。他者に対する痛烈な批判がやはり子規らしいということだろう。
とは言え、やはり身辺を描いたものがもっとも興味深い。俳人らしい詩情溢れるもので、特殊な環境で生き永らえる一人の人間の世界が見事に描き出されている。この随筆も子規の大きな仕事の一つと言って良かろう。