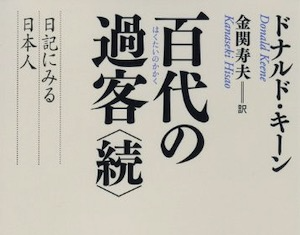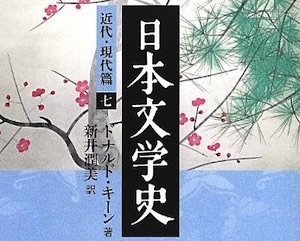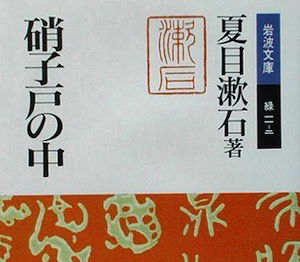仰臥漫録
正岡子規著
岩波文庫
一人の詩人そして重病人のドキュメント
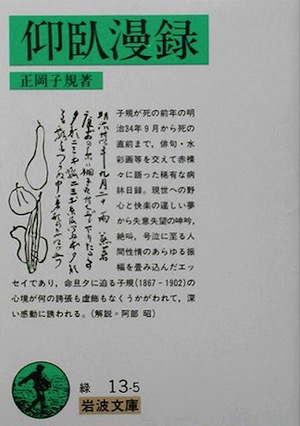
明治の歌壇、俳壇に革新をもたらした正岡子規、晩年の日記。
正岡子規は、死去までの数年間、寝たきりの生活を余儀なくされたが、その間も随筆や評論を発表し続けた。先日紹介した『墨汁一滴』も、当時新聞『日本』に発表したものだが、その間未発表の日記を書き綴っていた。何を食べたとか、誰が来たとかの日常雑記が主だが、俳句の草稿や人物批評などもあって、当時の子規の心情を探る上で最良の素材になっている。
なんと言っても、寝たきりの生活であるにもかかわらず、食べる量がすごく、飯三椀程度は当たり前で、菓子パンや果物も追加で食べたりする。食事の内容も、刺身だったり肉だったりで割合豪華である。ただし、正岡家がリッチだったというわけではなく、看病に当たっていた妹の律と母は粗食で済ましている。子規自身、寝たきりで楽しみが少ないため、食事に異様なほどの情熱を燃やしていたということらしい。しかも大量に食べては吐いたり、あるいは何度も便通したりということを繰り返す。便通は寝たきりであるため、身体に相当負担がかかるようで、それを考えると少食の方向に進んでもおかしくないが、子規は食うのである。
毎日の包帯交換も非常な苦痛であったようだ。ただ、こういった苦しさを、記述で直接訴えることはあまりない。だが文面から生活の辛さは伝わってくる。自殺を試みようとしたことも記録されている(明治34年10月13日)。一方で、寝たきり生活の病人とは思えない前向きさもあちこちに見える。弟子の虚子や碧梧桐、伊藤左千夫らが始終出入りしていたことも、その理由なのだろうと思う。
日記は毎日のように書かれているが、明治34年10月29日以降、しばらく途切れる。次に出てくるのは明治35年3月10日で、3月12日まで記述が進んで、その後の6月20日以降は1、2行のメモ書きになる。このあたりは、弟子たちが当番として付き添っていた様子が窺われる。弟子たちが引き継ぎを兼ねてメモを残していた(つまりこのあたりの「日記」は弟子の手によるもの)のではないかとも推測される。これが7月29日まで続き、9月3日まで散発的に(こちらは自筆と思われる)メモが出てくる。死去したのは9月19日ということなので、死の間際まで記述を残していたことになる。
簡単なスケッチもあちこちに描いており、本書にはそれも収録されている。一人の詩人そして重病人のドキュメントがそこに残されており、生きることの意味を考えさせられる。そういう部分が、本書の最大の魅力だと思う。