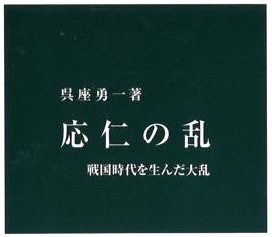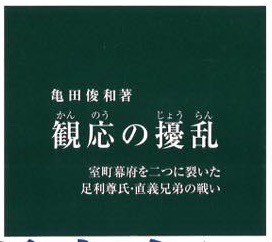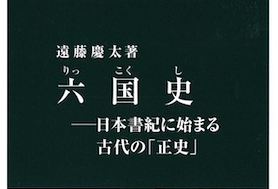荘園
墾田永年私財法から応仁の乱まで
伊藤俊一著
中公新書
ホントのところが見えてこない
中公新書の歴史物の限界か

学校で教わる日本史は、大事なところが省略されていて、本質が見えない部分が多い。
たとえば鎌倉時代になったら、それまでの国司・群司が支配していた地域社会が、突然守護・地頭が支配する社会になるかのように(少なくとも中学までは)教えられるが、実際のところ国司は室町時代までずっと存続していたし、高校の教科書には、鎌倉時代には下地中分や地頭請など、国司と地頭のせめぎ合いが出てきたりする。じゃあ、それまで教わっていた、国司・群司から守護・地頭への転換はどうなったのかと感じたりする。
要は、古代から近代に至るまで、日本では、田んぼから上がる米を、生産者以外の誰かが、税という名目で懐に入れていたわけだが、誰の懐に入っていたかがしっかり教えられないのである。下地中分と地頭請も、税を荘園領主(貴族)がとるか地頭(武士)がとるかという争いの結果生まれたもので、それがわかってくると、歴史の背景がもう少し見えるようになる。こういう内容は、政治史に比べると重要性が低いと考えられるかも知れないが、武士の台頭、貴族の没落、守護大名の登場など、すべてが経済力を背景にしているわけで、結局のところ、税を誰が手に入れるかという問題に帰着するため、税制度、それに伴う土地制度は、実は日本史の要なのである。
だからと言って、高等学校の日本史で土地制度の変遷が教えられるかというと、実のところはないがしろになっていて、その割には用語だけがたくさん出てきて、生徒を混乱させる原因になっている。用語を教えるというのであれば、その背景についてもしっかり記述すべきと思うのだ。
特に平安時代の土地制度が複雑で、班田収授の時代から荘園の時代に移り変わりはするが、荘園制度がわかったようでよくわからない。誰かが土地を私有してそこからの収益を奪っていたのはわかるが、国に対する税はどうなっているのかとか、あるいは国司などの役職との関連とか、わからないことが多すぎる。国衙領などという概念も、わかったようでわからない。とにかく学校日本史において、土地制度自体が相当曖昧な扱いになっているのである。
この本では、班田収授の時代から戦国時代まで、土地制度がどのように変遷したかを「荘園」制度を軸にして解説していく。公地公民制の建前が西暦743年の墾田永年私財法で崩れ、有力者が土地を開墾し、それを自身の所有物にしたのが荘園。もっとも荘園であっても税はついてまわり、国司を経由して国庫に収められることになる。なお、このような種類の新たな荘園(自墾地系荘園)の場合、最初は当然耕作者がいないため、実際の耕作については周辺の農民にバイトさせたらしい。その後、平安時代中頃になると、国有の田も国司などが横領したりして荘園化していき、今度はその荘園を他者(寺社や有力貴族)に寄進したりして、収益がどこに流れるのかがわかりにくくなる。とにかくいろいろな人間が、収穫物に群がる状況が出てくる。この本では、このあたりについてひととおりの説明はあるが、本質的なところがよく見えてこない。読み直してみたが、やはりわかりにくい。どこか代表的な荘園を取り上げて、税や貢納分がどこに収められていたか、細かく紹介してくれたらわかりやすかったのかも知れないが、この本全体を通じて、同じようなわかりにくさ、物足りなさが残るのである。要するに説明が通り一遍で、教科書的であるということ。「これを〜という」などという記述も頻繁に出てきて、まさしくそれを体現しているようである。もっと本質的なことを知りたいのだが(史料が少ないのかも知れないが)、結局はよくわからないままだった。
鎌倉、室町期以降は比較的具体性が出てくるが、この頃になると武士が支配力を強めて、かつてのようなややこしい関係が少なくなっていく。ということで、このあたりになってくると、わかりにくさは少なくなる。だが、一番知りたい部分が結局わからずじまいという何とも物足りない読後感になってしまった。
高校の教科書に出てくる土地用語については、本書で随時説明されているため、そういった用語の意味はわかったが、同時に、現在のように、土地用語だけ高校日本史教科で取り上げることに意味があるのか疑問に感じた。先ほども言ったようにこの本も中途半端だと感じたが、高校の日本史教科も実に中途半端だと、この本を読んで実感したのだった。