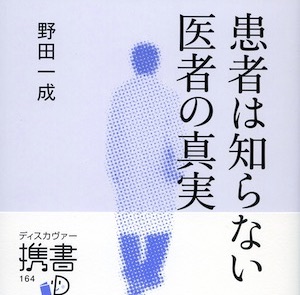村上朝日堂の逆襲
村上春樹、安西水丸著
新潮文庫
巨匠になる前の軽口エッセイ

村上春樹による『村上朝日堂』というエッセイは元々80年代に『日刊アルバイトニュース』に連載されていたもので、その後、その続編みたいなものが『村上朝日堂の逆襲』というタイトルで『週刊朝日』に連載されることになった。僕は、連載時からときどき読んでいたし、その後単行本になったときも買ったような記憶がある(処分したようで今はない)。今回、実に30年ぶりに読み直すことになった。
著者の村上春樹は、今こそ大巨匠になってしまったが、当時はそこいらの雑誌にエッセイを書くようなライターだった。彼が書く軽い感じの語り口が当時の雑誌で受け入れられていたのである。内容は、とりとめのない身辺雑記に、若干の鋭さ、ひがみ、自虐ネタなどを混ぜ込んだもので、気楽に読める類のエッセイである。映画や本などを話題にしたものも多く、今だとこういうネタはなかなか売り物になりにくいんではないかと思う。というのも内容がブログみたいなものだからである。もちろんそれなりに面白い話もあり、読んでいて十分楽しめる。
今回この本を読み直したのは、「小津安二郎監督の映画『東京物語』をドイツのテレビで見た」話(「ベルリンの小津安二郎と蚊取り線香」)をふと思い出し、もう一度読んでみようと思ったためである。要は、ドイツを旅行したときにホテルのテレビでドイツ語吹き替え版の『東京物語』を見たんだが、「そうかね」「そうですよ」「やはりそうかね」「そうじゃありませんか」「やはりそうだね」「そうですよ」などという会話が、ドイツ語になった途端に「そーであるのか」「そーであるのだ」「そーであるべからざることなきか」「そーであるべからざることなきなり」「そーであること、然り」「然り」みたいに哲学的な色彩を帯びてくるというような話なんである(小津映画に出てくる縦型の蚊取り線香についても考察している)。旅行の土産話みたいなたわいもない話だが、クスッと笑えるような、いかにも(当時の)村上春樹らしいと思えるようなエッセイで、今まで僕の記憶に残っていたのだ。
その後村上春樹は随分エラくなっちゃったが、実は彼の小説については、僕は読んでもあまり感じるところはない。むしろこういった軽妙なエッセイの方に味わいを感じるんだが、世間様と僕とでは認識に開きがあるようだ。こういうエッセイがノーベル賞候補などということになると世の中も随分変わったなと感じるんだが(実際は選考対象になったのは当然、小説)、だがしかしかつてこういうエッセイを書いていた人がノーベル賞候補であるということも、考えてみるとタイヘンなことである。このようなことを考えていると、なんだか当時にタイムスリップしてしまうような感覚さえ起きるんで不思議である。
なおこのエッセイ、すべての回に安西水丸(画伯)が味のあるイラストを沿えている。最後の最後に村上と安西の対談も付いていて、こちらもなかなか楽しい。文庫本であるが、お決まりのアホみたいな解説がないのもよい。
どの回も概ね水準が高く楽しめるが(くだらないネタが多いが)、「インタビューについて」、「植字工悲話」、「山口下田丸くんのこと」、「バビロン再訪」あたりが特に僕の好みだ。いかにも軽いエッセイであるが、こういう軽さが当時の軽薄短小時代によく合っていたんだろうなと思いつつ、僕は時代を遡っていったのだった。