食べものから学ぶ世界史
人も自然も壊さない経済とは?
平賀緑著
岩波ジュニア新書
マルクス経済学的な分析は新鮮
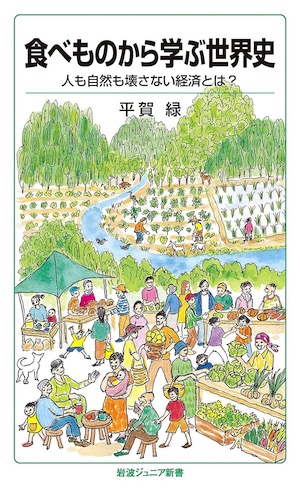
『岩波ジュニア新書』の1冊であるため、中高生向けという立場で書かれた本であると思われる。
前半部は、食品が本来自給自足的な身辺調達物質であったにもかかわらず、資本主義経済の進展とともに商品になり、価値の交換がなければ手に入らないものになったなどという記述がそれなりに新鮮であった。また、「宗主国の食品を調達する植民地」という図式が作り上げられ、各地域に昔から存在した食料調達システムが破壊されてきて、帝国主義経済の枠組みに取り込まれてしまったせいで、彼らは食料面での自立ができなくなった(そして場合によってはその地に飢餓を招いた)などの分析も鋭い。こういう捉え方はマルクス経済学的な分析ではないかと思うが、僕にとってはなかなか新鮮であった。また、20世紀に世界中で進んだ「緑の革命」が、途上国の農業をアメリカ型の資本主義経済システムに取り込むための戦略だったという記述も面白い。
ただ、途中から出てくる記述に目を疑うようなものもあり、たとえば「江戸時代まで、コメは年貢(税)として納めるものであり、当時大多数を占めていた農民が日常の食として食べる食料ではありませんでした」(102ページ)などと書かれていると、今でもこういう歴史観を持っている人がいるのかと思ったほどで、こういう話が出てくると、途端に他の箇所の記述も信頼性が怪しくなってくる。元々、大学で行った講義の内容を発展させたのがこの本らしいので、講義の場でそういう表現が出てくるのはある程度致し方ないが、こういう話題については書籍化の段階でちゃんと検討した方が良いのではないかと思う。また、これに前後するあたりから記述内容が途端につまらなくなったのも事実(聞き書きみたいなもの〈つまり他書からの引用〉が多い)で、第5章(「日本における食と資本主義の歴史」)と第6章(「中国のブタとグローバリゼーション」)は割愛した方が本としての質を高く維持できたように思う。
全体的には、内容がやや浅めという印象で、本文中で紹介されている参考文献にしてみても、『砂糖の世界史』や『デブの帝国』などの一般向けの書籍であり、それを考えると、本書自体が入門者向けの基礎知識紹介本であることが窺える。もっとも大学での新入生向けの講義の内容であると考えると、これはこれでありかなとも思える。
ただ、全体的に作りが丁寧という印象で、総じて前半はそれなりに読み応えがあった。気付きに繋がるような記述もあり、高校レベルの知識を持つ人が読めば、得るところは非常に大きいんじゃないかと感じた。






