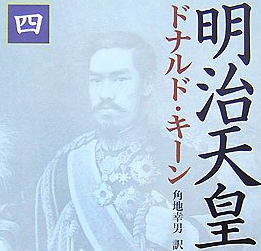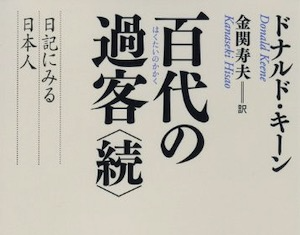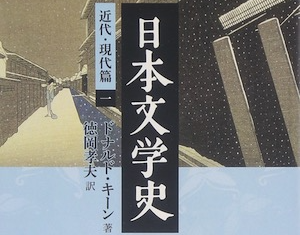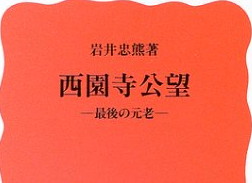明治天皇〈二〉
ドナルド・キーン著、角地幸男訳
新潮文庫
歴史を膚で感じる
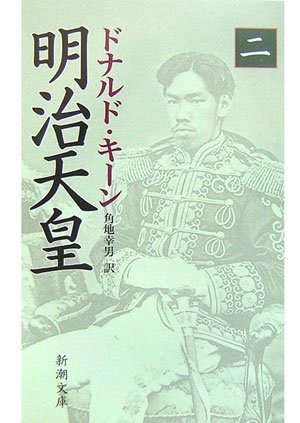
明治天皇の生涯に迫るノンフィクションで、文庫版全4巻構成の第2巻が本書。明治維新から明治14年の政変、自由民権運動あたりまでがその内容になる。
新しい政体になって、政治機構が徐々にできあがり(紆余曲折はかなりあるが)、政府が少しずつ機能するようになる。やがて廃藩置県を断行し、中央集権体制に徐々に移行していく。
外交的には対朝鮮政策(いわゆる征韓論争)で揉め、政府内が二分されるような議論になる。その上、政府要人の江藤新平、西郷隆盛、板垣退助らが下野するという異常事態になる(明治六年の政変)。しかもその後、彼らが地方で反乱を起こし(佐賀の乱から西南戦争まで)、国内は一部内戦状態になる。結局は、徴兵制で富国(はともかく)強兵を果たしつつある政府軍が、反乱軍を抑え込むことに成功し、政府直属の正規軍の力が証明されることになった。そのため、以後国内に大規模な反乱はなくなる。同時に士族の処分も(政府側からすると)無事に終わることになる。
さらに台湾問題、琉球問題も現れ、このあたりは清国やヨーロッパ諸国と牽制し合いながら乗り切るが、領土問題については、このときの中途半端な処理が現在にも一部禍根を残す結果になった。
また、各地で反政府運動が起こってくるのもこの時代。そういった時代に、新政府の新しい顔として、各地域を積極的に行幸してまわったのが明治天皇。民衆に対する顔見せ(実際に顔を見せたかどうかはともかく)、それから各地域の教育や産業の状況を視察するというのがその名目だったが、少なくとも当時の民衆からの受けは良かったようで、天皇の存在価値を民衆に植え付ける結果になった。
その後、旧士族を中心に政治参加を求める動きが現れ、政府も立憲政体樹立の方向に舵を切る。そのあたりまでがこの第2巻の内容である。
第1巻同様、割合ゆったりと話が進むが、ゆったりだからか、読んでいると、歴史のミクロ的な側面に触れられるような気がしてくる。特に現代から歴史を見る場合、どうしてもその後の体制から遡って物事を考えがちであるが、その時代にいれば先が見えないわけで、それを考えると、遡って考えるという帰納的な歴史認識が必ずしも正しくないということが実感できる。たとえば西南戦争などは、現代の視点から見れば「不平士族の反乱」で済むが、当時の感覚では内戦に近かったわけで、政府軍が物量で圧倒していたとは言え、鹿児島で持久戦になって、各地の不平士族がこれに呼応して立ち上がったりしたら、それこそ明治政府が転覆していてもおかしくなかったという状況だったらしい。そういう歴史の側面を感じられる点が、この本の大きな魅力である。記述は平易だが、分量が多いせいか読むのには結構時間がかかっている。