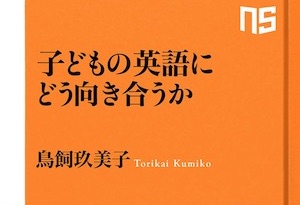AI vs. 教科書が読めない子どもたち
新井紀子著
東洋経済新報社
論理の飛躍がはなはだ多い
特に後半は読むに堪えない

AI(人工知能)の研究をしているという数学者が、現在いろいろと物議を醸しているAIの真の正体をさらす本。「AIが神になる」、「AIが人類を滅ぼす」、「シンギュラリティ(AIが人間の知性を超える点)が到来する」などと世間で言われていることは現状ではあり得ないというのが著者の意見。しかしながら、近い将来、現在人間が行っている多くの仕事がAIに取って代わられる可能性は非常に高いという。そのために、私たちはAIに取って代わられないような技能を習得し、AIに仕事を奪われないようにすべきと主張する。ところが、AIにとって一番苦手な技能である読解力を、今の日本の若者の多くが持っていないため、しっかり勉強させて読解力を付けさせるべきというのがこの本の主張である。
前半は、AIの専門家の立場から、AIの限界について語っていて、なかなか有意義である。特に昨今、AIは、将棋や囲碁など、さまざまな分野で人間より優れたパフォーマンスを示しており、しかもアメリカではクイズ王になるAIすら登場していることが注目を集めている。そのため現在、AIの無限の可能性があちこちで語られるようになっているが、現実的には、人間の能力にはまったく及ばないらしい。そもそもAIに仕事をさせるためには、そのために人間がプログラムを書いたり、さまざまなデータを教え込んだりしなければならず、しかもそれはすべて数学的な知識が基になっているため、数学的に解明されていないさまざまな事象については、機械で肩代わりさせることは不可能である(著者によると)。つまり、脳の働きを含む、自然界の事象のほとんどはいまだに未解明であるため、機械に人間の脳の働きをさせることはできないと言うのである。そのため、人間の智を超えるような機械を、現時点で人間が作り出すことは不可能ということになる。実際、普通の人間がごく簡単にできるようなことでさえ、機械にやらせることには多くの場合多大な困難がつきまとうらしい。
現在AIが過剰に注目されているのは、ディープ・ラーニングなどの手法で、機械自体が自身で学習できるようになったたためであるが、実際のところ、これは過大評価に過ぎないというのが著者の主張である。著者によると、数学は、現在「論理」、「確率」、「統計」の3つの方法で表現されているが、現実的には機械で「論理」を行わせるのは困難を極める。そこで「確率」、「統計」により、あてずっぽうで結果の正解率を上げているというのが現状らしい。このあたりが前半部分で、こういう専門家による体験的な理屈にはなかなか説得力があって、なるほどね……と思う。
ところが後半になって、現代の日本の若者の読解力の問題や、AIに仕事を奪われないよう読解力をつけさせるべきなどという主張になると、ツッコミどころが満載になってくる。このあたりは、科学や統計の体裁を取っているが、ほとんどが著者の直感だけの議論で、論理性が著しく欠如している。したがって説得力がなく、読むに堪えないというのが、僕の感想である。
まず、今現在の子どもたちに読解力がないということを示していく。そのために、自らが開発したリーディングスキルテスト(RST)なるものが紹介される。そしてこれを、いくつかの学校で実施させた結果、結果が芳しくなかったということが、子どもの読解力のなさを証明する有力な証左だというのだ。このあたりがさも事実であるかのごとく、ダラダラと紹介されていく。だがこのRST自体、僕が見るところかなり怪しい代物であると思う(内容は中高の受験教材みたいなものであるため、ある程度の基礎知識がなければ誤解するのも免れないと思える)。これができたから読解力がある、できないから読解力がないなどというのは、一つの(宗教がかった)見方に過ぎないと感じる。著者によると、このテストは、素材自体、教科書から採用したものであるため、「これを誤解すること」=「教科書が読めない」と結論付けられるそうだが、教科書を読む場合でも、通常は、その文章の理解の前提となる基本的な知識を身につけた上でなければ内容がわからないことは往々にしてある。したがって、同じ学年の生徒が同じ学年の教科書の文章を見せられて誤解したとしても「教科書が読めない」と断定することには無理がある。よしんばそれで「教科書が読めない」ということになったとしても、そうであれば、その教科書の記述に問題があるという結論の方が正しいのではないか。
また、たとえ教科書が読めないからといって、それでAIが苦手な仕事を行うことができないという結論も論理が飛躍しすぎている。この本で紹介されている「10〜20年後まで残る職業」の中には、学校の国語の成績と関係ないようなものもたくさんあるし、読みづらい教科書が読めなくても問題はないと感じるものも多い。
先ほども言ったが、RST自体、高校や大学の受験の国語の問題で出てくるような形式の問題が多く、結局これができたということは受験の問題が解けるという程度の証明にしかならないように思う。進学校の生徒の成績が良かったというような結論も示されているが、当たり前である。進学校ではそういう勉強ばかりやってんだから。
著者は現在「教育のための科学研究所」という社団法人の代表をやっており、RSTもここが開発したものだそうで、このRSTを全国の中学・高校に普及させたいと考えているらしい。しかもRSTを採用した学校、およびその教員については、意識が高いなどとべた褒めしている。僕には、この著者の主張は、結局のところ、日本の受験ヒエラルキー擁護者〈あるいは学歴至上主義者〉によく見られるような議論、言い換えるならば難関大学(入学難易度の高い大学)に行った人がエラいみたいな受験至上主義のように映る。このRSTというテストも、受験勉強至上主義のあだ花のように見える。そのため個人的には、このようなバカバカしいテストをありがたがって採用したりする学校がこれ以上現れないことを切に願う……ということになる。
この本の後半部分から受ける印象は、自分が設定した結論に持っていきたいがために、いろいろな都合の良い題材を集めてその裏付けに使っているというものである。これを勘案すると、この著者の愛読書がデカルトの『方法序説』だというのも十分頷ける話である(このことは、本書で紹介されている)。デカルトは、同様の帰納的な方法論を採用して、神の存在を証明してしまった人だ(もちろん『方法序説』の中で「我思う故に我あり」という画期的な発想をしたことは評価に値するし、それがこの著書の価値を決定しているわけだが)。
またこの著者は本を年間5冊程度しか読まない(だが自分には読解力がある〈これについてははっきりとは書いていないが〉)などとも豪語しているが、読解力をつけるには、ある程度の数の本を読むのは必要条件だと個人的には思う。著者は、本の数と読解力には関連性がないことがデータで示されているみたいなことも書いているが、詳細については書いていない。そのあたりについても、本当にそうなのか、どうやってそのことを証明したのか、その証明方法に説得力があるのかということについて、この本の後半部でデータを示しながら紹介してほしかったところである。僕としてはむしろ、この著者の読解力、文章作成能力、論理力の方を疑問視したいところである。
このようにこの本の後半部分は、科学の体裁を取っているが、論理の飛躍がはなはだ多く、本当にこの著者は数学者なのかと感じるほど、論述が非論理的である。そのため、著者が出しているいろいろな未来予想が、どれもデタラメに思われ(実際にそうなんだろうが)、結局は自分が直感的に思ったことを並べているだけではないかと感じる。こういう展開にしてしまうと、せっかくある程度説得力を持つ前半部分(AIの真の姿をさらした部分)の価値も著しく低下してしまう。
要するに、自分の専門に絞って、できれば周りの人が面白いと感じるような専門的な知識を披露すべきではないですか……というのが、一読者としての僕の考え方である。