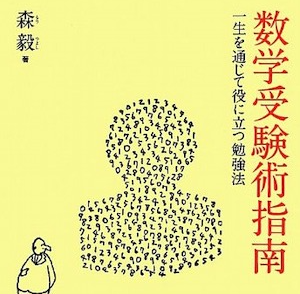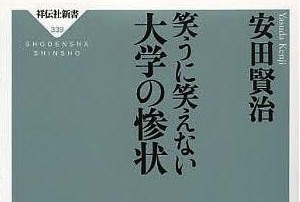子どもの英語にどう向き合うか
鳥飼玖美子著
NHK出版新書
迷走する小学校英語教育に疑義を呈す

昨年から小学校に英語科が本格的に導入されたが、現実的には、子どもにとって大して役に立っているようには思えず、むしろ教育現場に混乱を巻き起こしているだけではないかと思ってしまう。小学校の教師に英語を教えろと言ったって、今の小学校教師は、教師になったときに英語を教えることを求められていなかったわけで、言ってみれば、英語教育については素人である。素人が子どもに英語を教える、しかも英語で教えろなどということを文科省は言っているんだが、無理に決まっとる、そんなもん!
文科省は、ここ10年ほど、大学入試制度の改変をはじめとして、おかしな政策ばかり打ち出して、世間を混乱の渦に巻き込んでいるが、結局そのしわ寄せは教員や子どもたちのところにやって来る。
著者が、本書で小学校の英語教育の問題として挙げているのもそのあたりで、結果的に英語嫌いの子どもを量産することになりはしないかと危惧している。そこで改めて、小学校の英語教育導入や、中高校の「4技能」(読む、書く、聞く、話す能力)推進政策について問題点を検討してみようというのがこの本である。第2章では、日本の英語教育の歴史を振り返り、歴史的に見て現在の政策にどのような意味があるのかについても検討する。
歴史を振り返ると、小学校英語は、1886年から都市部を中心に始まっており、諸々の理由で1912年に廃止されたという経緯がある。小学校に英語を導入しようとした動機は現在の状況と同様で、廃止された理由も(たとえば英語学者の岡倉由三郎によると)、教師の確保が難しいとか、日本語の習得すらできていないのに英語を導入しようとしてもうまく行かないとか、現在、小学英語反対論の中で言われていることが挙がっている。また、現在文科省が推進している、「教師が英語だけを使って英語を教える」授業形式も、明治時代から散々行われており、その弊害が大きいため取りやめになったという経緯がある。こういった歴史を振り返ると、現在の英語政策に「何を今さら」感を抱いてしまうのは僕だけではないと思うが、返す返すも、英語が嫌いな子どもが増えないことを願うものである。
第3章では、実際に小学校で展開される英語の授業について取り上げ、その実態を紹介している。正直、こんな授業だったらやらない方が良いんじゃないかと思うようなレベルであるが、それがよくわかるようになっているのは本書の魅力の1つである。
終章では、英語教育に対する著者、鳥飼玖美子(専門は英語教育学)の考え方を紹介し、英語学習(会話学習)では、単に英語で挨拶が交わせることを目指すんではなくて、内容の伴うことを英語で伝えられるようになることを目指さなければならないという見解を示す(挨拶を交わせたところでその後まったく話ができないんでは無意味なのだ)。そのためには、話す能力や聞く能力を早急に育成しようとするよりも、読む能力、書く能力の育成を第一にした方が良いという見方を示す。要は、従来型の英語教育は、必ずしもうまく行っていたわけではないにしても、英語ができる人材を育成するという意味で一定の役割を果たしており、その点から、現在のような軽薄な行政に対して異論を唱えているわけである。
僕個人としては、基本的に著者と同じスタンスでいるが、本書にはところどころ気になる箇所があるにはある(AIに負けない「読む力」を養おうと訴えている節など。ちなみにこれは『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』の受け売りである)。それでも、第2章の英語教育史は読み応えがあったし、全体的に、著者の体験を交えながら、著者の主張をわかりやすく説いていて、しかもそれが正鵠を得ているため、読む価値は十分にある。子どもの英語教育をどうするか悩んでいる方々にぜひ読んでほしい本である。