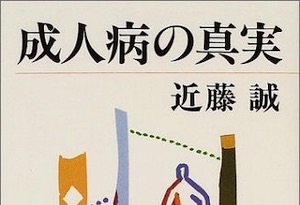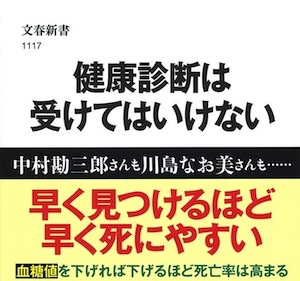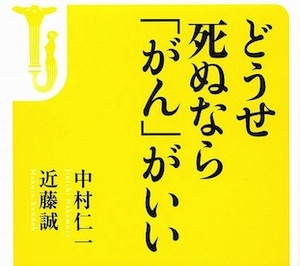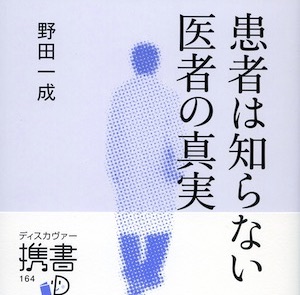がん放置療法のすすめ
患者150人の証言
近藤誠著
文春新書
がん放置の実例集
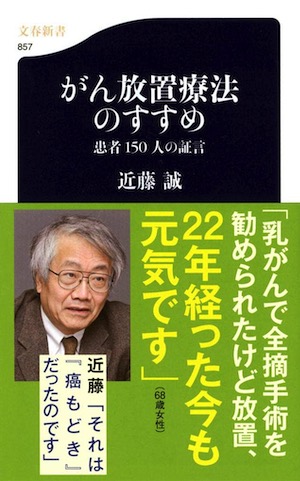
『がんは切ればなおるのか』や『患者よ、ガンと闘うな』でお馴染みの近藤誠の著書。
近藤誠は、慶應大学医学部で講師を勤めていた人(すでに退官)。90年代にがんの外科手術および抗癌剤の不毛さや有害さを告発して、かなりのセンセーションを巻き起こした。当然、既存の医学界勢力はこれに反発し、著書や著者をこき下ろすような言論があちこちで発表されるようになったが、それでも、医者に頼りっぱなしの従来型の医療が誤りであるという認識はおそらく多くの日本人の間に浸透したはずである。少なくとも僕は、がん治療のほとんどはまがいものであると感じるようになった。
近藤誠の論は、がん(と思われているもの)には転移する「本物のがん」と転移しない「がんもどき」があるというものである。「本物のがん」は、目視で見つかった時点ですでに(発見されないほどの小ささであっても)何度も分裂を繰り返しており、身体のあちこちに転移している可能性が高いため、見つかった部分を切り取ったところで転移した部分はそのまま残っていることから、治ることはない。「がんもどき」(著者はこれを「おでき」と表現したりする)であれば、切っても切らなくても転移しないため変わりない。むしろがんであろうとがんもどきであろうと、切ることでQOL(生活の質)を著しく落とすことに繋がるので、がんに対するほとんどの外科手術は必要ないとする。また抗癌剤も同様の理由で無意味であり、むしろQOLを大幅に低下させる要因になるため、使わない方が良いというものである(ただしこれについては、がんの種類によって一部例外がある、つまり抗癌剤が効くものもあるとする)。
これ以上ないくらい明解で、「がんは転移を繰り返すうちに悪性または良性に転化するため、早期に切れば良い」という従来の説よりよほど説得力があると思うがどうだろう。またこのような従来型の主張が反論できにくいというのも納得がいく。なにしろ証拠が残らない。つまり、手術した後そのがんで死んだら「手遅れでした」で済む(つまり患者側が早く医者にかからなかったせいということになる)し、手術の後がんが進行しなかったら「成功でした」となる(つまり医者のおかげ、手術のおかげということになる)。結局のところ患者側の過失か外科手術の御利益かのいずれかに落ち着くのである。だが、手術のおかげで助かったように見えても、実際のところは分からないままで、手術をする前から助かるかどうか(つまり「がん」か「がんもどき」か)が決まっていたと考えても説明できる。もっとも、そう考えてしまうとがんの外科手術自体が徒労で無意味なものになるため、外科医がそう考えることはないというカラクリである。で、結局本当のところはわからないまま闇の彼方へということになる。
こういう状態が続いているため、近藤の「がんもどき」理論が正しいかどうかはなかなか検証できない。というのは、現代医療ではがんが見つかったら外科手術をするケースがほとんどで、がんを放置した事例についてのデータがあまりないためだ。そこで実際に放置したらどうなるかということを、著者自らが直接診た患者のデータを利用して検証しようというのがこの本である。著者のところに来る患者は、当然のことながらほとんどががんの外科手術に懐疑的な人たちで、ほとんどがQOLを改善するための手術以外受けていない。つまりがんを放置したらどうなるかという実証例になっている。データは150件ほどあるらしいが、この本で具体的に紹介されているのは前立腺がん、子宮頸がん、乳がん、肺がん、胃がん、腎がん、膀胱がんなど、数例のみである(総合的なデータは掲載されている)。それでも全体的には放置した方が良いのではないかと感じさせるだけの説得力はある。あるいは反対派の人々が言うように、近藤誠のデータに恣意性があるのかも知れないが、少なくとも(抗癌剤で)数年に渡って苦しみ続けるとか、(人工肛門などで)QOLが著しく低下するなどということは、がんを放置しているケースではない。がんで死ぬことが分かっていて余命が予測できればそれなりの準備もできるし、痛みもかなりのレベルで緩和できる(しかも死ぬまでそれほど長引くわけではない)というんだから、普通の思考をすればどちらを選ぶか一目瞭然ではないだろうか。もちろん、どちらを選ぶかは人それぞれであるが、少なくともがんを放置するという選択肢があることぐらいは、すべてのがん候補者である日本人は知っておくべきではないかと思う。著者の言う「がんは老化現象」という発想も面白い。