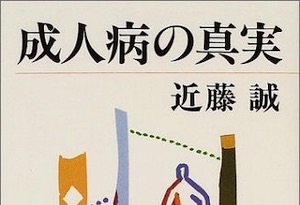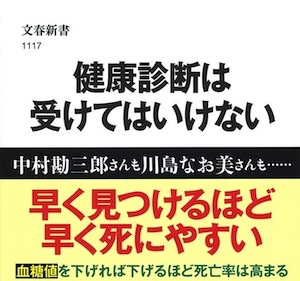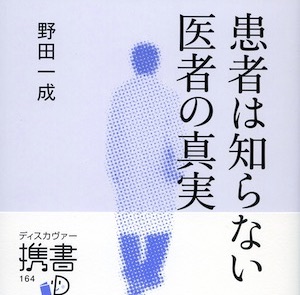大学病院が患者を死なせるとき
私が慶応大学医学部をやめない理由
近藤誠著
講談社+α文庫
病院で何が行われているかを
疑似的に目の当たりにすることができる

近藤誠の半生記。なぜ彼が、外科医たちと対立するようになったか、なぜ無益ながん治療を告発するようになったかが、近藤のキャリアから窺われるようになっている。
著者は、特段の目的を持たずに慶応大学の医学部に入り、どこの科に行くというような明確な意志もなく慶応病院でインターンをすることになるが、いろいろ考えたあげく放射線科に進むことになる。これも定時に帰れそうだからという消極的な理由である。
だが、当時の放射線科は、他の科で処置できなくなった患者が送り込まれるような部署であったこともあり、徐々に自ら末期がん患者と向き合わざるを得なくなる。患者のための適切な治療は何かということを考えると、現行の治療が必ずしも患者のためになっていない、またがんであることを知らせないのも患者のためになっていないということに気づき始め、少しずつ自分の周辺から状況を変えていくようになる。
特に乳がん治療では、当時海外で常識になりつつあった乳房温存療法を日本でも取り入れ、知り合いの外部の外科医と協力して、この治療法を積極的に推進していくようになる。乳房温存療法が少しずつ日本でも認知されるようになった頃、あるとき、近藤の乳房温存治療を希望して慶応病院にやってきた患者が、勝手に外科に回され乳房温存療法ではなくハルステッド法(乳房だけでなくその下の筋肉やリンパ節までごっそり取り除く手術)を強行されようとするという事件があり(手術直前に近藤の耳に入り結局ハルステッド手術を回避)、これがきっかけとなって外科や大学病院当局と対立し、対決姿勢をとらざるを得なくなる。
その後、ハルステッド法の無益さ(乳房温存療法と死亡率が変わらない点など)を指摘した文章を『文藝春秋』に発表した結果、外科医たちと決定的に対立することになってしまう。外科医からは近藤の上司である教授のところにクレームが来るなどして、上司とも関係が悪化し、結果的に(教授職に繋がる)出世の道が完全に途絶えてしまう。
こういういきさつを経て、ともかく自分の良心に基づいて、間違ったことを間違ったこととして主張していこう、そのためには論文を読み込むなど自分なりに勉強して、理論武装しなければならないという結論になり、その後の近藤の活動に至るのである。
文章は、他の近藤誠本と同じく非常に読みやすく、スリリングな点もあちこちにあって、読者を引き付けてやまない。患者との生々しいやりとりなどもあって、大変面白い本である。当然、大学病院の閉鎖性や保守性も紹介されており、日本の大組織はどこもまあ似たようなものだろうが、彼らが、「正論を主張することで秩序を乱す」者に対してどういう対応をとるかは、大変興味深いところである。この種の保守的な集団が変化しにくいのは当然なんだろうが、そういった保守性・閉鎖性が、患者や周囲の人々に多大な迷惑を与えているわけで、そのことについては少しでも反省してもらいたいものである。
このような状況は、近藤誠のような反逆者が出て来ない限り、なかなか変わらないものだが、実際、この種の反逆者は闇に葬られてしまうのが普通である。近藤によると、彼のような反乱が、許されないにしても野放しにされていたのは、慶応大学という環境によるところが大きいということで、他の病院だとこうはいかなかったかも知れないと言う。実際、近藤も、クビになることを覚悟して、司法試験の勉強をしていたという(その後、一次試験は合格したらしい)が、結局、大学に講師としてだが居座ることができ、患者を診続けることができたわけである。同時に社会に外科手術の問題性を発信し続けることもできたわけだから、慶応様様ということなるのだろうか。