ブルシット・ジョブの謎
クソどうでもいい仕事はなぜ増えるか
酒井隆史著
講談社現代新書
現代の社会システムの歪みをあぶり出す
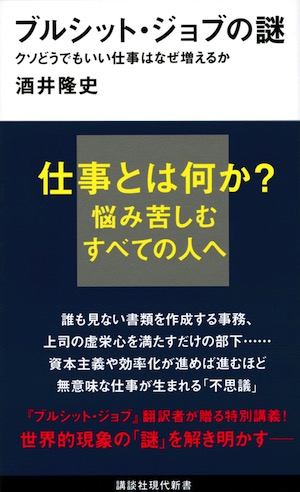
デヴィッド・グレーバーという人類学者が発表した『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』という本の解説本である。この本について解説をしている人、つまり本書の著者は、社会思想史が専門であり、同時に『ブルシット・ジョブ』の翻訳者の1人である。したがって同書の解説本を書く人材としては最適と言って良い。
さて、ここで語られている「ブルシット・ジョブ(クソどうでもいい仕事)」とは、「完璧に無意味で、不必要で、有害でさえある雇用の形態」と定義されるもので、要するに、世の中に対して何の役にも立たない仕事であり、なおかつそれに従事している本人がそのことを理解しているような仕事を指す。言ってみれば、「穴を掘った後その穴を埋める」というような類の仕事である。実際には、誰も目にすることのない書類の作成作業(日本の役所仕事などはこういうものが多いと感じる)や、愚かな上司が作った無意味な企画の尻ぬぐい(日本の企業にこういうのが多いように思う)などがこれに当たるらしい。こういった仕事が大多数を占めるのが現代社会だと言うのである。労働者に対して行われたある調査によると、調査対象の3分の1が、自身の仕事がこういう仕事に該当すると回答したらしいし、別の調査では、こういう仕事に従事していると回答した人々が4割を超えているという。
早い話、機械化が進んだ現代社会では、やるべき仕事自体がそもそもそれほど存在していないというのが究極の原因ということになる。にもかかわらず、何もしなくても良い状況でも何かをしていなければ怠け者と見なされる風潮が世間に存在するために、こういう歪んだ状況が生み出されているのだというのである。
人間の生活様式というものは元々、集中的に仕事をして、他の時間は何もしないというのが自然な状態であるにもかかわらず、近代化・工業化に伴い、労働者が時間単位で雇われ拘束されるというシステムが当たり前のものになった。つまり雇用の対象である時間帯は怠けてはならないとされるようになった。こうして、する必要のない仕事が作り出され、それが増殖することになったというのだ。同時に、こういう潮流と軌を一にして、本来生活上必要なエッセンシャルワーク、つまり非ブルシット・ジョブが軽視されるようになり、ブルシット・ジョブの方が素晴らしい仕事であるとされるような価値観(「社会的価値と市場価値の反比例」)が蔓延して、家庭内労働(これもエッセンシャルワークであるが)の価値までが低く扱われるようになったのだとする。さらに言えば、ネオリベラリズムや官僚制もブルシット・ジョブを増殖させる役割を果たしている。その上で、こういう状況を抜本的に変えるには、ベーシックインカムこそが有用だという結論を出しているというのが、グレーバーの主張、ひいては本書の主張であるということらしい。
本書の著者によると、グレーバーの原著(『ブルシット・ジョブ』)自体面白く有用な書ではあるが、ややとりとめがなくわかりにくい箇所が多いことから、この本を通じてその内容を著者なりにまとめたということで、それを考えると、本書では、原著の内容が概ね反映されているのではないかと思う。実際、ここで語られている内容は非常に興味深く、もう少し深掘りしてみたい気もしてくるため、著者の意図はかなり実現されていると考えられる。
ただし本書についてもわかりにくい箇所が割に多く、それに説明のために使われた例が必ずしも適切ではないと感じることもままあった。著者の専門が社会思想史ということで、あまり身近でない思想家や思想も頻繁に出てくるが、結果的にわかりにくさを助長させてしまう結果になっている。一方で、近代の社会思想の変化にグレーバーの主張を絡ませていって説明を加えるというのも、アプローチとしてはそれほど悪くなかったのではないかとも感じる。少なくとも、本書を通じて知ったグレーバーの仕事については、僕自身かなり関心を持ったのは事実で、それを思うと、本書は初期の目的を果たしているとも言える。



