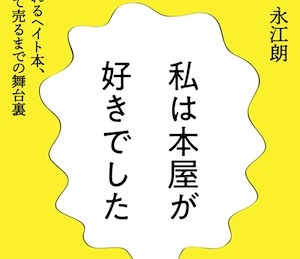負債論
デヴィッド・グレーバー著、酒井隆史、高祖岩三郎訳
以文社
完成度が著しく低い本
だが読みどころがそこここにある

『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』の著者、デヴィッド・グレーバーが、それに先立つ数年前に出版した書。原始から現代に至るまでの経済の歴史を、これまでの常識的な見方とまったく異なる視点で描き出す本である。
アダム・スミス以来、物々交換による交換経済の時代があり、やがて貨幣が発明されて、その上で信用取引が生み出されたと考えられているが、著者は、これはまったくの神話であり、貨幣のような標準的な価値基準がなければ物々交換は成立し得ないとする。そもそも一定の価値基準がないと交換は生じ得ず、結果的に発生するのは物々交換ではなく、暴力的な収奪になるという。人類学者である著者は、これを先住民族に対するフィールドワークや古代文献などから解き明かす。
そもそも人類史を振り返ると、原始共産制によって必要なものを融通し合う社会があり、それに続いてツケによる取引、つまり信用経済が生まれたというのが著者の考え方である。貨幣が生まれたのは、暴力的な侵略行為が行われた時代、つまり敵から収奪した財産を兵士に分けるために、収奪した貴金属を融かして分配し、それを一種の符牒として流通させるようになったことが始まりで、言わば支配者から兵士への借用書みたいな役割であったとする。貨幣や紙幣は本来的にそのような役割を持ち、中世以降のヨーロッパでも、侵略戦争の資金調達のために、借用証書としての紙幣が登場するようになったという。
また負債に付けられる利息についても、イスラム社会などでは原則禁止されていたもので、その後、返済が遅れたことの罰則としての意味で利息が付けられる例が出てきたとする。同時にこういった利息や負債により、個人の自由までもが取引され、奴隷として自身の家族や自分自身まで身売りするような暴力的な事例が多発したのが古代社会である。つまり負債には、暴力的な側面が常につきまとっている。同時に、現代に生きる我々にも、生まれたときから社会に負債を負っており、それを返していくことが市民としての務めみたいな思い込みや枠組みが強制される。したがって我々は働き続けなければ、生きていくことができないのである。現代の社会は、まさに負債によってがんじがらめにされ、債務者が債権者によって暴力的に脅迫され、自由を奪われていくというシステムに基づいて構築されているというわけだ。
本書は、800ページを超える大著で、大きく前後半に分かれている。前半が負債や経済についての考察で、後半が、前半の理論に基づいた紀元前3500年から現代までの歴史の経済的な解釈である。書かれている内容は、先ほど書いたようなものかと自分では思っているが、なにしろ内容が雑多で、全体を通した一貫性も見えてこない。『ブルシット・ジョブ』同様、とにかく読みづらいし、読み続けるのが苦痛になる。ただあの本と同様、ところどころ目を引くような記述があって、それが本書を読むインセンティブになる。読めばいろいろな発見があり、目からウロコみたいな箇所も非常に多いが、とにかく読むのに苦労するのである。
そしてそれに拍車をかけるのが、翻訳文のまずさである。量が多かったせいだろうが、何を言いたいのかわからない文章が頻繁に出てきて、しかもろくに校正していないんじゃないかと思わせるほど誤植が多い。これほど誤植が多い本も珍しい。なんせ320ページの4行目は句点(。)で始まっていると来ている(ちなみに僕が今回読んだのは初版第1刷)。こんな本を見たのは初めてだ。誤植は2~3ページに1つ以上の割合であって、誤植ではないにしても用語に一貫性がないなどの部分もあちこちに見受けられる。「訳者あとがきにかえて」という節に「アレクサンドリア大王」という用語が出てくるが、本文内では「アレキサンダー大王」、「アレクサンドロス大帝」という訳語が使われている。そもそも「アレクサンドリア」は都市名である。総じて本書はゲラ・レベルで、完成度が恐ろしく低いと言わざるを得ない。
訳者も「あとがきにかえて」で漏らしているが、原文自体がかなり厄介なのも事実である。テーマがあちこちに行ったり来たりする上、修辞もわかりにくい箇所が多い(翻訳のせいばかりとも言えないと思う)。その上、原注が135ページ(!)、参考文献の一覧が66ページもある。この著者に対しては理解に苦しむ部分が多いが、しかし先ほども書いたように、目を引くような箇所も本書には散在するのである。決してないがしろにできないが、資料として読むような忍耐力が必要な本である。本書自体の存在についても、あくまで「参考資料」という位置付けに落ち着くのではないかと思う。