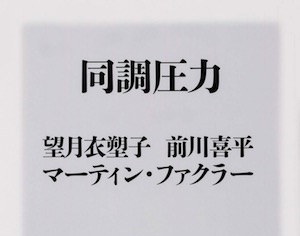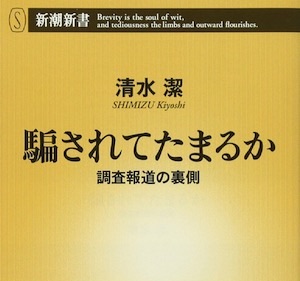魂の退社
稲垣えみ子著
東洋経済新報社
ジャーナリストでさえも会社に守られているという
いびつな社会

在職中から一部で人気を集めていたらしいアフロ記者(髪型がアフロの新聞記者)、稲垣えみ子氏の退職体験記。
著者は、50歳で朝日新聞社を辞めフリーになったが、そこに至るまでに10年間の準備期間があったという。30代のときに一生会社勤めをすることに疑問を感じ始め、50歳になるまでに退職することを決意する。結果的に約10年準備期間が生じることになり、十分に熟考を重ねた上での退職になったわけである。
ただし日本で脱サラしてフリーになることがどのようなものかは具体的にイメージできていなかったらしい。途端に周囲の扱いが変わり、不動産屋でもうさんくさい目で見られるようになった上、クレジットカードさえ作れなくなったという。つまり会社という後ろ盾を失った途端に社会的信用を失ったかのような扱いを受け出した……と本人は感じたらしい。
さらには、それまで会社支給だった携帯電話も自分で契約しなければならなくなり、こちらも、料金システムを含め何も知らずに今まで使い倒していたために、いざ自分で契約するとなると、店舗の販売担当者からあれやこれやよく知らない用語で言いくるめられ、結局毎月8千円の料金がかかる「プラン」によくわからずに加入することになった。しかもわからないことであるにもかかわらず「お得」だと押し切られて加入したために、この業界自体詐欺まがいではないかと感じたらしい。実際それに近い業種だと思うが、そんなこと今ごろ知ったんかいと突っ込みたくなるような話ではある。
さらに言うと、健康保険料や年金も、それまでは会社負担であまり省みることがなかったが、自分で手続きと支払いをしなければならなくなり、健康保険料の異常な高額さに今さら驚くという有り様で、こっちも今ごろそんなこと知ったんかいとツッコミを入れたくなった。大新聞の新聞記者がそんなことさえ知らなかったのかと驚くことが多く、それでよく「社会の木鐸」が務まるなと感じたのが本書の一番の収穫だった。著者がこのあたりをカミングアウトしたのは一種の英断ではあるが、偉そうなことを語っているマスコミの人間は、所詮「大会社」という組織に守られた存在であることがこういう部分から窺われる。要するに彼らはマジョリティにしか目が行かないわけで、それは社会問題を取り上げる立場からは致命的な欠陥である!とあえて言わせてもらう。
この人が退社で経験したことの多くは、本来であれば学校を卒業して社会に出るときに自ら経験すべきことであり、新卒で企業に入ってそのままであれば、多くの人が知らないままになってしまう。定年を迎えて初めて知るという人々が出てきてもおかしくなく、そのことを考えると、日本は世間を知らない「寄らば大樹」の人々だらけという状況があるわけだ。道理で現状維持を望む保守主義が日本社会に蔓延しているわけである。
著者は、新聞社を辞めてから、そういうことに気付いたらしく、日本が「会社」を背景、前提として回っている「会社社会」であったことを思い知ったという。それは確かにすばらしい気付きであったが、僕などにしてみると「今さら」感が強い事例である。
その後著者は、会社から離れても幸福を追求する生活を送れるということに気付き、新たな道を模索する方向に進んだ。僕にしてみるとこのあたりが一番新鮮だったとは思うが、全体的に世間知らずのエリートの告白みたいな話で、悪いが少しばかりイタさを感じたのであった。