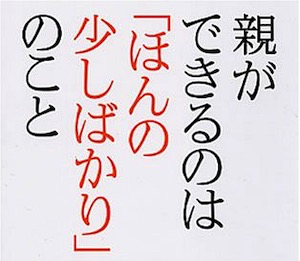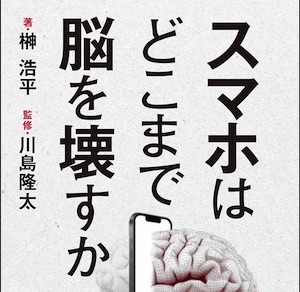客観性の落とし穴
村上靖彦著
ちくまプリマー新書
主張には全面的に共感するが
論証には疑問を持つ

著者は現在大学で教鞭を執っている人だが、普段接している学生から「先生の言っていることに客観的な妥当性はあるのですか?」と訊かれることがあるらしい。この著者は、医療現場や貧困地区で聴き取りを行ってそれを授業で紹介したりしているんだが、そのときにこういう発言が出てくるというのである。要は、この学生をはじめ、多くの現代人に、客観性への過剰な信奉があると感じるというわけだ。そこで、現代人の客観性への信仰を問い直し、個人の経験にこそ真実が含まれることが多いということを紹介するのがこの本である。
著者は、本書の前半部で、科学的手法としての客観性が登場してからそれが金科玉条のように判断基準として席巻していくようになり、それに伴って人間の疎外が起こってきた過程を紹介する。このことが少数者の排除を引き起こすことにつながり、多数派の状況を数字的に捉えることしかできていないことから、内在している真の問題が把握されなくなってしまうのだと主張する。
このような問題を克服する上で必要なのは、少数者の「生」の声であり、そのための手法の拠り所としてフッサールやハイデガーらの現象学を引用している。このあたりが非常にわかりにくかったが、ともかく著者の主張は極力「生」の声をそのまま再現することが重要ということで、現にそういう活動を著者は現在行っているわけである。著者の活動の正当化と言えなくもない。
「はじめに」の章で、各章のテーマを紹介している他、すべての章の最初にその章で何について語るかも要約して紹介しているなど、非常に構成が丁寧な本で、また著者の主張にも全面的に賛同するが、著者が採るミクロ的なアプローチと現象学との関連については、先ほども書いたようによく飲み込めず、このあたりが本書のネックになっているように感じる。もちろん現象学についてよく理解している人が読んだらまた違った感触があるのかも知れないが、いずれにしても門外漢にもわかるように紹介しないと、あまり有用な論拠にはならない。
そもそもマクロ的なアプローチですべての問題が把握できるわけがないのは明らかで、ミクロ的な視点が必要なのはこういった論証を待つまでもないのではないだろうか。著者が最初に提示した「客観的な妥当性」については、あった方が良い場合もあるし、そうでない場合もある。ましてや人の語りを紹介する際になぜ客観性が要求されるのか、その時点で随分ピントがずれているような気がする。結局のところ、著者の活動について「客観的な妥当性」を要求したという例の学生が、短絡的な思考しか持ちあわせていない愚か者であるという結論で良いのではないかと思うがいかがだろうか。