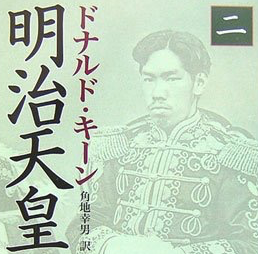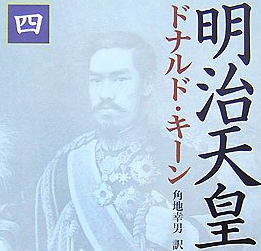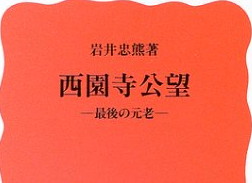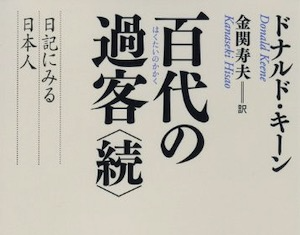明治天皇〈三〉
ドナルド・キーン著、角地幸男訳
新潮文庫
「目からウロコ」が続出
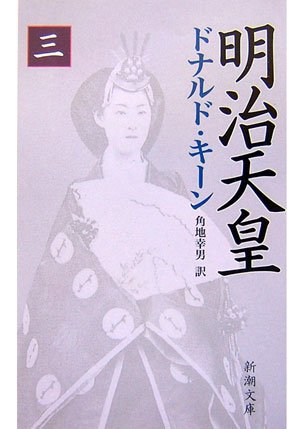
明治天皇の生涯に迫るノンフィクションで、文庫版全4巻構成の第3巻が本書。朝鮮情勢、条約改正交渉、憲法発布、衆議院議員選挙実施、日清戦争、閔妃暗殺、北清事変などが扱われる。日本にとっての富国強兵の時代である。こういった数々の事績は、明治天皇が「大帝」と呼ばれるゆえんにもなっている。
だが実際は、必ずしも学校で教わるように計画的かつ漸進的に進んだわけではないことがわかる。実際の政策は、結構行き当たりばったりで、憲法や民会にしても時期尚早とする声が政府関係者の間には大きく、そのせいでなかなか進まない(民会開催まで結局15年かかる)。実際始めたら始めたで、選挙には暴力や賄賂がつきまとい、民会(衆議院)側も政府と敵対して、何も決められずという状態が長く続く。まあ、それがリアルな歴史ということだろう。
一番驚くのは日清戦争で、この戦争も司馬遼太郎の小説や学校の歴史では、大日本帝国が東洋の覇権を握るべく着々と準備してきたというような描かれ方だが、実際のところは、開戦2カ月前くらいまで、政府の誰もが清国との戦争を想定していなかったというのである。全然「着々と準備」という感じではない。本書からの印象では、大敗北しなくてラッキーぐらいの感覚に近かったようだ。また、日清戦争中の旅順での大日本帝国軍による虐殺事件もあまり教科書で触れられることはないが、世界に「野蛮な劣等国」の印象を与えるのではないかということで、政府関係者が汲々としたなどという事実が語られ、非常に新鮮である。司馬遼太郎の『坂の上の雲』によると、当時の大日本帝国の軍隊は(列強諸国から非難を受けないようにするため)国際法を厳密に遵守すべく、違法行為が見られない規律正しい軍隊だったという風に描かれていたと記憶しているが、実際のところ、当然だが、決してそんな軍隊ではなかったことがわかる(そんな軍隊があったらお目にかかりたいもんだ)。後の関東軍の風はこのときから芽生えていたということである。
もう一つ新鮮だったのは大津事件(来日中のロシア皇太子ニコライ2世が大津で暴漢に襲われた事件)に際して、死刑を求める政府関係者に対して、法による支配を断固主張し一歩も譲らなかった大審院長、児島惟謙の行動で、今より政府権力が強いあの時代に、この地位の判事が今では考えられない主張を展開したことにあらためて驚く。このあたりの政府関係者とのやりとりも真に迫っていて、非常に読み応えのある箇所である(第四十二章「ロシア皇太子襲撃」)。
明治天皇自身は、この時代、政治にも積極的に関与するようになっており、政治に口を出すことも頻繁ではないがやっている。基本的には、政府のトップ(太政大臣や内閣総理大臣など)に政治を任せるというスタンスではあるが、岩倉具視や伊藤博文などは、天皇に詔勅を出すよう求めたりもしていて、明治天皇と国のトップとの関係性がなかなか面白味を感じさせる。何より驚くのは、近代体制ができた後、首相に就任した人々がことあるごとに天皇に辞意を示して慰留される(結局辞めるんだが)ということがたびたびあることで、何か気に食わないことがあるとすぐに辞めようとする首脳には心底あきれかえってしまう。明治天皇もこういった連中にはさぞかし頭を悩ませたのではないかとこの本を読みながら感じる(明治天皇自身は、自分は辞めようと思っても辞められない……と漏らしていたこともあるらしい)。こういう連中をうまいこと使いこなしたんだから、やはり明治時代の帝国の発展は、管理者としての明治天皇の業績と言うことができるかも知れない。