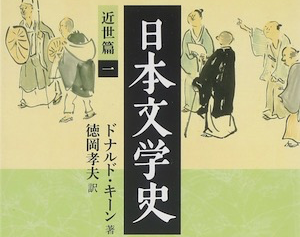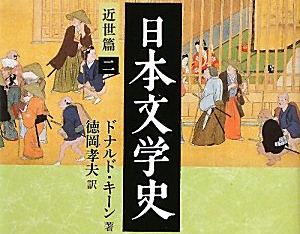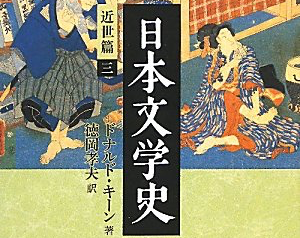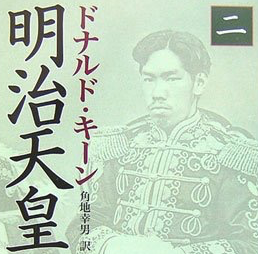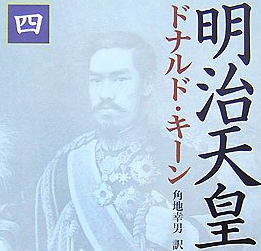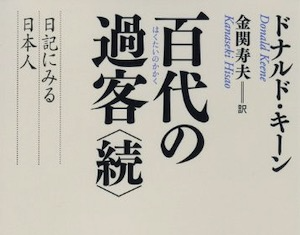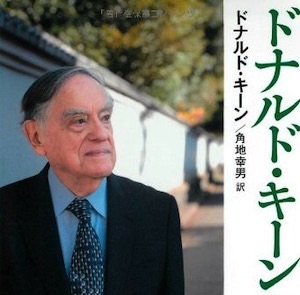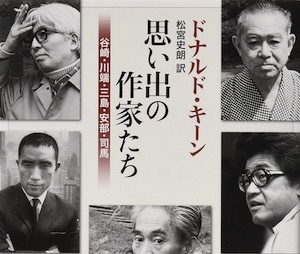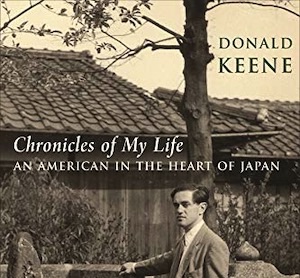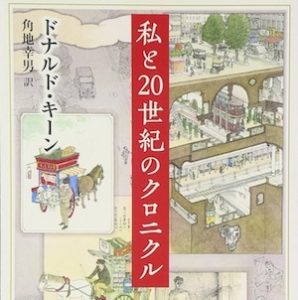日本人の美意識
ドナルド・キーン著、金関寿夫訳
中公文庫
ドナルド・キーンの仕事を俯瞰する
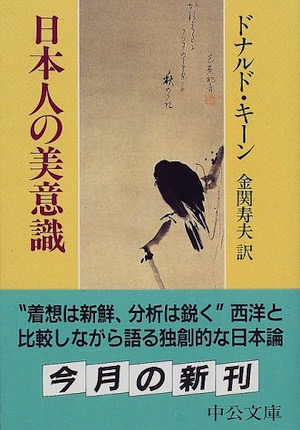
日本文学者、ドナルド・キーンの9本の論文(またはエッセイ)をまとめた書。論文は1960年代から70年代初頭に渡って書かれたもので、内容が広範に渡っており、どれも興味深い。
掲載されているのは「日本人の美意識」、「平安時代の女性的感性」、「日本文学における個性と型」、「日本演劇における写実性と非現実性」、「日清戦争と日本文化」、「一休頂相」、「花子」、「アーサー・ウェーリ」、「一専門家の告白」の9本。最後の「アーサー・ウェーリ」と「一専門家の告白」がエッセイ(初出は〈おそらく〉雑誌とニューヨーク・タイムズ)で、前者が、著者が敬愛する東洋文学の翻訳家、アーサー・ウェーリ(『源氏物語』の英訳が有名)との想い出を語ったもの、後者が、「日本文学が専門」と口にしたときの他者の反応に対するボヤキみたいな内容のエッセイ。特に後者はエスプリが効いていて面白い。
残りはすべて論文である。「日本人の美意識」は、タイトルの通り日本人の美意識を分析した書で、内容は非常に興味深い。日本文化論であるが、これだけの鋭い視点、分析力はなかなかお目にかかれまい。日本文化の学界はこれだけの研究者を得られたことを感謝すべきである。
「平安時代の女性的感性」は、優れた(と著者が感じている)平安文学に、どれも女性的感性があるとする平安文学論。「日本人の美意識」とも通じる内容である。
「日本文学における個性と型」は、簡単に言えば元禄ルネサンス論で、井原西鶴、近松門左衛門の作品をモチーフにして、彼らの文学(そしてそれは長い間日本文学の底流になるのだが)に、登場人物の内面を深く探るのではなく、彼らを「様式」的かつ「定型」的に描くという特徴があると指摘する。おそらくその後の著者の大作『日本文学史』に繋がる内容なのではないかと思う(実際、『日本文学史』は近世文学から始まっている)。
「日本演劇における写実性と非現実性」は、能、文楽、歌舞伎におけるリアリズム・非リアリズムについて論じる。こういった演劇は、その形態を見ても明らかにリアルではないが、描かれる対象として常にリアリズムが紛れ込んでいる。同様に日本の演劇には、こういったリアリズムと非リアリズムがいろいろな点で混在しているというような論。これはおそらくその後の『能・文楽・歌舞伎』に連なる論なのではないかと思う(この書については未読)。
「一休頂相」は、一休宗純の異色性、破天荒さをその漢詩から辿るという内容で、あの異色の頂相(肖像画)に一休の特徴が反映されているとする論。
「花子」は、20世紀初頭、ヨーロッパとアメリカで人気を博した女優、花子についての論。花子は、当時なぜだかわからないが、その舞台が突然ヨーロッパで大当たりした。決して美しい女性ではなく、しかも舞台自体に芸術性があるわけでもなく、それでも大受けし、そのために各地を巡業して、どの地でも人気を博したと言う。あのロダンも結構花子に入れ込んでおり、花子の肖像をいくつか作成している。著者は、サラ・ベルナールなどをはじめとする当時の大女優崇拝現象の一環で、そこにエキゾティシズムに対する関心みたいなものがうまく融合して、人気を得ることに繋がったと分析しているようだが、基本線は、この「花子」現象を比較的客観的に紹介するという論である。花子については名前ぐらいしか知らなかったため、大変興味深く読んだ。
そしてこの書の目玉と言えるのが「日清戦争と日本文化」で、ページ数も全体のほぼ三分の一が割かれている。日清戦争を通じて、日本の対中国観が、崇拝・尊敬から蔑視へ大きく劇的に変わったことを当時の印刷物から論じるもので、これも非常に興味深い。ただしこれについては、先日読んだ『明治天皇〈三〉』でも何度も引用されていた内容であるため、僕にとってはそれほど目新しさはないが、しかし斬新な論考であるのは確かである。
今見てきたように、それぞれの論はその後の著者の著作に繋がっているものも多く、それを考えると、本書は著者の著作群のダイジェストという言い方もできる。内容が多岐に渡っているのは先ほど書いたが、同時に取り上げる内容も斬新である。論理も飛躍や矛盾がないため、どれにも説得力がある。地味な本ではあるが、ドナルド・キーンの仕事を見渡す上で優れた案内書になっていると言うことができる。得るところ(特に新しい視点)が多い良書である。