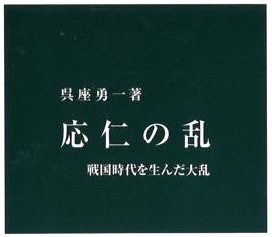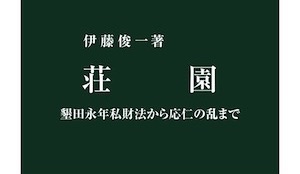戦国大名と分国法
清水克行著
岩波書店
歴史の「事実」を見直す潮流の一つ

日本史の世界では、かなりいい加減で荒唐無稽な見解が「事実」として認定されていることが多い。古代史の多くの「事実」もそうだし、そういった、思いつきが定着した「事実」は近世に至るまで数々ある。今では当たり前のように喧伝されている「竪穴式住居」の姿も、元々はある大学の先生が描いた想像図がそのまま「事実」であるかのように定着したものだという話を聞いたこともある。
分国法についても、高校の教科書では、戦国大名の独立過程の法整備の象徴としてまことしやかに取り上げられるが、本書では実際には必ずしもそういう種類のものではないということが紹介される。ちなみに分国法とは、戦国大名が自身の領国内で定めた独自の法律のこと。
こういう説が定着したのは、石母田正という歴史学者による『日本思想体系 中世政治社会思想 上』の「解説」が遠因になっているのではないかと著者は言う。この論では、戦国大名が、独立した「国家権力の歴史的一類型」であり、独自の法(つまり分国法)を持っていたことがその証左であったとしている。この論文の影響は大きく、やがて「分国法が戦国大名の自律性の指標と位置付けられる」ようになったというのが著者の見解である。
しかし実際の分国法は、その多くが、法体系というより領主が書き殴ったようなまとまりのないものであったり、子孫に書き残した家訓のようなものに過ぎなかったという。この本で紹介されるのは結城氏の「結城氏新法度」、伊達氏の「塵芥集」、六角氏の「六角氏式目」、今川氏の「今川仮名目録」と「仮名目録追加」、武田氏の「甲州法度之次第」で、この中で、ある程度まとまりがあるものは今川氏と武田氏のもの程度らしい。武田氏のものについても「今川仮名目録」をモデルにした痕跡があり、それを考えると決して法体系などと呼べるようなものではないということで、要は、分国法というものが、領内の紛争やもめ事を解決する際の基準として、その時代の常識的な判断や非成文法を書き留めたものであるということらしいのだ。中には「六角氏式目」のように大名自身の横暴を制約するような「マグナ・カルタ」的なものまで存在する。つまり分国法とひとくくりに言っても、それぞれで制定の事情が異なり、内容も異なる。決して近代的な成文法という種類のものではないということなのだ。
本書の主張はよく理解できるし説得力もあるが、内容が少々冗長な感じもある。ただ紹介される分国法はすべて現代語訳されており、記述も平易であるため、読みやすいのは確かで、そういう点では読んでも損はないと思う。いずれにしても、日本の歴史学にいい加減な要素が数多く残っているのは確かで、それを正していくのが現世代の歴史学者である。そういう点では価値のある研究成果と言える。