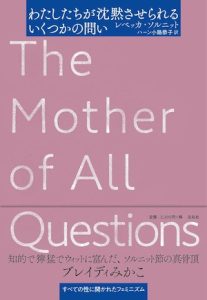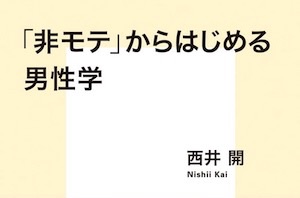説教したがる男たち
レベッカ・ソルニット著、ハーン小路恭子訳
左右社
女性が置かれている現状は
これほど厳しいのかという驚き
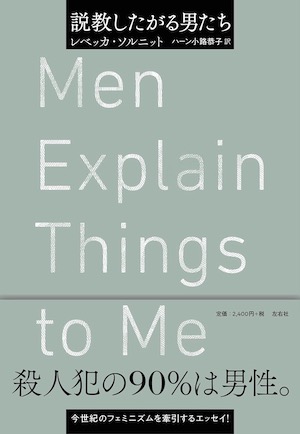
作家、歴史家、アクティビストという肩書きを持つレベッカ・ソルニットのエッセイ集。
全部で9編のエッセイで構成されており、最初のエッセイのタイトルが本書のタイトルになっている。このエッセイは、著者のかつての経験を書いたもので、あるパーティで同席した年配の男が、著者(女性)がマイブリッジの本を出していることを知って「今年出たばかりのマイブリッジ関連のとても重要な本を知っているかね」と言いながら、その本の内容を滔々と語って聴かせた(その内容はニューヨークタイムズの書評の受け売りだったようだ)というエピソードが元になっている。しかもその本は、実は著者が出したまさにその本だったというオチが付く。こういう風に、専門外の事項であるにもかかわらず、男が女に対して説教したがるという状況は多いらしい。著者もこれまでこういう経験を重ねてきているようで、そういった男たちには、男が女より優れた存在で、何もわからない女は口をつぐんでいるべきだという偏見があるというのが著者の見立てである。
実際、こういう類の男たちが数多く存在するのは周りを見回せば察しが付くが、現在では男が女に説教したがる現象は「マンスプレイニング」と呼ばれているらしい。ちなみにこの言葉も、著者の別のエッセイから派生したもののようである(著者はこの言葉をあまり気に入っていないようであるが)。こういう類の行為は、女性が劣っているという偏見に基づくもので、それは言うまでもなく世界中に蔓延している。このような偏見が女性の社会進出を阻害し、閉じた世界に女を閉じ込めようとする風潮に繋がっていると著者は見ている。実際、女性がSNSで政治的なメッセージを出すと、それだけで、脅迫や殺害予告を含む反対の意見が押し寄せられるという(実際同じような話は知り合いの女性から聞いたことがある)。そこにはこのような偏見が根付いており、それが女性に対する性的犯罪の蔓延にも繋がっているというのである。
僕が本書で一番驚いたのが、米国人女性の5人に1人が性的暴行の経験がある(つまり性的暴行被害のサバイバーである)という話で、軍の内部を始め、高校や大学の構内でも性的暴行は多発しているらしい。男が女を殺傷する事件もきわめて多いのが実情で、つまるところ女性は、常に身の安全に注意しながら生活することを余儀なくされることになる。こういう話を訊くと、近年の#MeToo運動の高まりも頷けるというもので、状況は、直接的な暴力を伴っている分、日本よりひどいと言わざるを得ない(日本が相当ひどいのは言うまでもないが)。
そういうわけで、本書の記述は僕にとって新しい視点を開くきっかけになった。知らず知らずのうちに男性性の間に蔓延している女性蔑視(ミソジニー)を直視する結果になり、女性が置かれている現状の把握にも繋がった。そういう点で「目からウロコ」のレベルの好著であると言って良い。
ただし、9編のエッセイ中、5番目(美術評論)と6番目のもの(バージニア・ウルフについての評)は、他のエッセイからややかけ離れているという印象で(もちろん女性問題の視点から離れることはないが)、あまり面白味を感じなかった。美術評論とバージニア・ウルフが著者のライフワークの1つであることはわかるが、それでも本書のテーマからはやや外れているという印象で、他の箇所のインパクトが大きかったために余計それが目立った。異なるテーマのものは別の本に収録した方が結果的に良かったのではないかと思う。著者には興味が湧いたので、他の著書にも少し当たってみようかと感じている。