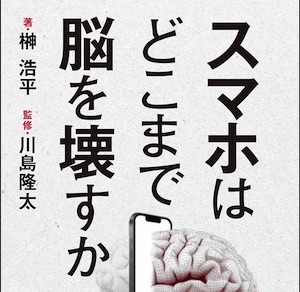もっと!
愛と創造、支配と進歩をもたらすドーパミンの最新脳科学
ダニエル・リーバーマン、マイケルロング著、梅田智世訳
インターシフト
途中から「無理から」な論証に走ってしまった

脳の中のドーパミンの働きについて語った本。
人が何か新しいものを欲しいと感じるとき、脳内で化学物質、ドーパミンが分泌されている。ドーパミン刺激が、新しいものに対する欲求という形で人の心の中に現出するというわけだ。ただし新しいものを手に入れると、ドーパミン刺激はたちどころになくなる。そしてまたさらに新しいものが見つかると、ドーパミン刺激が現れるという工合に、ドーパミンは動物が新しいものを開拓する際の原動力になるというのである。
著者によると、このドーパミン刺激は、人によって出やすい傾向、出にくい傾向が異なっており、それがその人の性格に反映するという。天才的な仕事をした人は、ドーパミン刺激によって動かされ、新しい分野を開拓しているし、ドーパミン分泌の異常が依存症や精神病にも繋がるらしい。
ドーパミンに対抗する物質が、著者のいわゆる「H&N(Here and Now:今ここ)」の化学物質(セロトニン、エンドルフィンなど)で、これは現状に満足感をもたらす脳内化学物質である。ドーパミンとH&Nのほどよいバランスが、人間にとって良好な状態を作り出すというのが、本書を貫く著者の主張になる。
まあそのあたりまでは十分納得できるが、後半になると、ドーパミン刺激の多寡が、政治的な志向(保守かリベラルか)にまで影響しているとまで言いのけてしまう。いろいろな調査データがさもそれを裏付けているかのような記述があるが、そもそも、そのデータの前提となっている条件(保守=共和党、リベラル=民主党という決めつけ)自体が相当怪しいと感じる。そもそも政治的に革新的であっても、食べ物やファッションの指向が保守的ということは十分あるわけで、それを一概に一つの原因に結びつけるのは無理があるってもんだ。そのくらい、ちょっと考えたらわかるだろうと思うが、著者は気が付かなかったんだろうか。というわけで、このあたりはこじつけにしか見えず、逆に本の価値を損ねる結果になってしまった。後半はこういった少し「トンデモ」な記述ばかりが目立つようになる。
こういうこともあって、前半はある程度しっかりした記述が多かったにもかかわらず、後半で一気にくだらない本に成り下がってしまったという印象である。そのため途中から読むのが苦痛になった。科学的アプローチを取るのであれば、専門領域に特化した記述を心がけるべきで、何にでも適用させて論理付けしようというのは似非科学にしか思えない。そういう意味で残念な本であった。