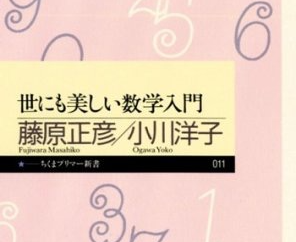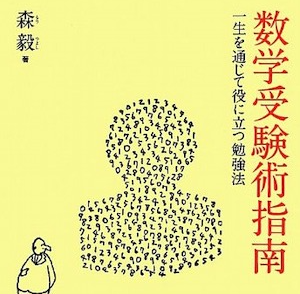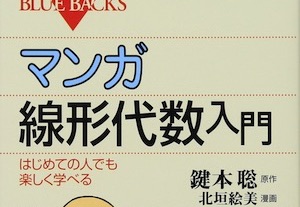数学の世界史
加藤文元著
KADOKAWA
終わりの方はまったくついていけなくなった

数学史の本を読んでみたいと常々考えていたところに出会ったのがこの本である。数学は、世界史レベルで考えると元々ローカルなもので、それぞれの地域の特色を孕んだ体系を持っていたが、それが近現代にヨーロッパで統合されて、現在のような体系的数学ができあがったというのが本書の主張である。
これを説くため、古代メソポタミア、古代エジプトの数学から始まり、インドに始まる位取り記数法(0の概念化によって実現)、古代ギリシャ数学(幾何学の発展と論証指向が特徴)と話が進んでいく。次に、ヘレニズム期のユークリッド幾何学の体系化について述べた後、インド、中国の数学を簡単に紹介し、中世アラビアの代数学からヨーロッパの代数学と進み、ヨーロッパでの微分積分法の発見で、本書のハイライトを迎える(という印象)。
その後は日本での数学(つまり和算)について紹介し、近代の非ユークリッド幾何学、現代の数学へと繋がるが、近現代の数学については、(高等数学から逸脱しているために)基礎的な概念がこちらにまったく存在しない上わかりやすい説明も本書にまったくなかったため、正直内容がほとんど理解できず、それ以前の箇所で感じられたような知的好奇心はまったく湧かなかった。この箇所、記述がおざなりであることから、現代の数学に触れないわけにいかないために取って付けたように付け加えたのか……というような印象すら受ける。そういうこともあり、和算以降の箇所(第13章、14章、15章)は読むのが苦痛で、おかげでこの本も永らくそのまま読まずに放っておいたほどである。このあたりの記述については各論に当たれということなのかも知れないが、もう少しわかりやすい記述があっても良かったのではと思う。結果的に、和算と近現代の部分がむしろ足を引っぱることになって、本書の価値を低下させることになった。やはり数学の通史となると、読む方にとっても書く方にとっても難易度が高いのかも知れないなどと考えたのだった。