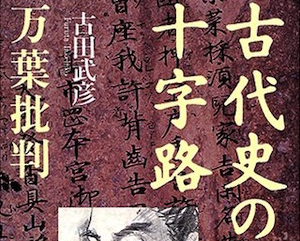日本列島の大王たち
古代は輝いていたⅡ
古田武彦著
朝日文庫
日本列島の古代の姿がぼんやりと浮かんでくる

これも、古代史に新解釈をもたらした歴史学者、古田武彦の著書。
例によって、これまで提唱してきた多元史観に基づく書で、日本列島の各地に存在していたと考えられる古代王朝について、遺跡や史料に基づいて個別に論じてく。好太王など、朝鮮半島の大王についての記述も含まれている。
日本列島の古代遺跡については、弥生時代から古墳時代にかけては銅剣文化圏、銅戈・銅矛文化圏、銅鐸文化圏に大きく分けることができる他、縄文時代についても土器の分類で5〜6程度に分けることができる。こういう事実から、それぞれの地域に別個の文化圏、つまり政治組織が存在していたことが窺われるわけで、それに基づいて多元史観(古代の日本に複数の王朝があったとする考え方)を提唱するのはごく自然である。ただ日本の歴史学では、明治期から一貫して、政治の中心は古代から近畿天皇家であるとする考え方(思い込みに近い)がはびこっており、著者が常に主張しているのも、その「一元史観」の思い込みを排除すべき……というものである。
本書では、存在していたと考えられるそれぞれの政治組織、つまり大王の国について、遺跡と史料を基に解明していき、新しい古代史観を打ち立てようとする。本書で論じられるのは、銅鐸文化圏の国家(『魏志倭人伝』に登場する東鯷国)、そこに侵入した神武天皇によって大和盆地に打ち立てられた国(後の近畿天皇家に連なる国)、その天皇家の国の内部での継体天皇による王朝簒奪、さらには高句麗の好太王、(当然のことながら)九州王朝(倭国)、関東の大王の国(「埼玉県稲荷山古墳出土鉄剣」に出てくる斯鬼宮を中心とする政体)まで多岐に渡っており、この論述によって、日本列島の古代の姿がぼんやりと浮かんでくる。その姿は、これまで伝えられてきた既成の一元史観とは大いに異なる、実に自然な様相である。
本書の論は、著者の他の書とほぼ一貫しており、他の著書同様、非常に説得力がある。もちろん著者の主張のすべてが正しいとは思わないが、論述が丁寧で、出される結論が、当時の極東情勢に照らし合わせて実に自然であるため、まったく無理がないのである。たとえば本書で論じられる「埼玉県稲荷山古墳の鉄剣」の銘文についても、出てくる大王の名前(「加多支鹵大王」という記述)を「カタシロ大王」などと(自然に)読み、その地の大王と見なす読み方をしている。この銘文については、「獲加多支鹵大王」と書かれている部分を強引に「ワカタケル大王」と読む読み方が一般的であり、これが雄略天皇の権勢が関東まで及んでいた証拠とする主張が主流になっているんだが(高校の教科書にまでそう書かれている)、本書では、そういった読み方を恣意的であるとして退けている。雄略天皇については、『古事記』で「大長谷若建」、『日本書紀』で「大泊瀬幼武」と書かれていて、それを根拠に「雄略=ワカタケル」とされているわけだが、この名前についても、雄略を特定する名前は「大長谷」、「大泊瀬」であり、「若建」と「幼武」は一般名詞に近いものと考えられるため(若い王を示す称号)、たとえ「獲加多支鹵大王」を強引に「ワカタケル大王」と読んだとしても、「獲加多支鹵大王=雄略」とはならないと言うのである。実に自然な論述で、論にまったく無理がない。
他にも『古事記』や『日本書紀』の記述で、極悪非道のように書かれた天皇は、決して「極悪非道」だったとは限らず、後の代の王者が自身を正当化するための方便だったという論も新鮮で、しかも説得力がある。ともかく、先ほども書いたように、本書を通じて古代の日本列島のありようが窺われるのである。結果的に、この新しい歴史観を通じて、これまでの歪みきった「歴史」が修正され、新しい古代史観が作り出されるという予感が感じられる。もっともこういった著書群がありながら、いまだに旧態依然とした一元史観がはびこっているのが、保守的な日本の歴史学界の現実である。いつになったら山が動くのか、まったく見えてこない。