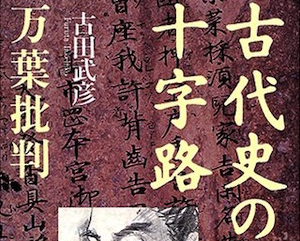法隆寺の中の九州王朝
古代は輝いていたⅢ
古田武彦著
朝日文庫
新しい歴史解釈の広大な地平に驚嘆
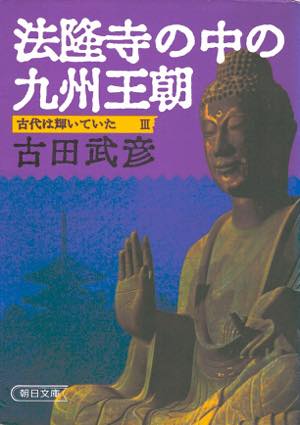
古代史に新解釈をもたらした歴史学者、古田武彦の著書。
著者によると、古代の日本に存在していた倭国は、九州を拠点とする九州王朝であり、その王朝は白村江の戦い(西暦662年)で敗北し、それが原因となって、その後、近畿に存在していた天皇家の王朝に取って代わられた。著者のいわゆる「九州王朝」説である。
前にも書いたように、現在の古代史界ではまったく受け入れられておらず無視されている。言ってみれば異端の説であるが、しかし古田が展開する議論はいちいちもっともで、読み進めると、その壮大な構想に度肝を抜かれてしまう。本書では、法隆寺金堂に安置されている釈迦三尊像が元々九州王朝で作られ、その後、法隆寺に移されたものであり、その光背にある金石文が九州王朝の大王、上宮法皇についてさまざまなことを語っているという主張が主要なトピックである。これまでこの金石文は、解読が割合いい加減で、「上宮法皇」=「聖徳太子」とされてきたが、そういう無理やりな解釈ではなく、「上宮法皇」は上宮法皇という名前の大王と解釈するのが古田流ということである。素直な解釈であり、説得力がある。
他に、九州王朝が律令と年号を持っていたとする説(九州年号については驚嘆の一言)、仏教が非常に早い段階で倭国に到来していたとする説(現在は6世紀とされている)、白村江の戦いの結果九州王朝が滅亡し列島を代表する王朝が近畿天皇家(「日本」)に入れ替わったとする説、さらには「郡評論争」に対する解釈なども紹介されている。内容は非常に多岐に渡り、しかも分析もかなり詳細である。途中、なかなかついていけない箇所も出てくるが、参照されている箇所を読み解けば理解できる。ただし時間はかかる。また、「古代は輝いていた」シリーズ(本書はこのシリーズのⅢ)の前著2冊に対する引用が随時出てくるため、これを読んでいないとわかりにくい箇所もある。僕自身は20年以上前に読んでいて内容は概ね把握しているつもりだが、それでもわかりにくかった。今回も、あちらの2冊を先に読むべきだったと少し後悔している。
今回、この本に当たったのは、「筑紫国造」とされている磐井君(著者は九州王朝の王者とする)について勉強し直したかったのと、上宮法皇についてもう一度把握し直しておきたかったためだが、やはり古田武彦の著書は順番に読むべきとあらためて感じることになった。なんといっても古田説は、その地平が広大で、どう考えてもないがしろにすることはできない。現在の日本の考古学者は無視を決め込んでいるようだが、決していい加減な説ではない。今回も史料批判がメインではあるが、史料だけでここまで読み解けるのだということがわかり、驚くばかりである。逆に他の歴史家たちは史料をどのように読んでいたのか、そちらに大いに疑問を抱くことになった。この本を読むと、学術は偏見から離れたところで進めなければならないということがよくわかる。特に古代史学については、現状を見る限り、近畿天皇家一元史観から離れることが肝要という、古田武彦の主張が十分に頷けるのだ。