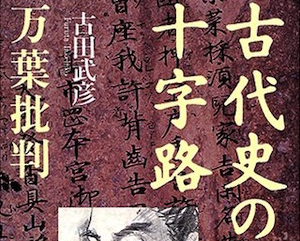倭人伝を徹底して読む
古田武彦著
朝日文庫
「邪馬台国」研究の流れが見えてくる

『「邪馬台国」はなかった』の古田武彦が、1984年から2年間、朝日カルチャーセンターで行った講演をまとめたもの。
講演といっても侮るべからずで、内容はかなり詳細で突っ込んだものである。古田武彦の著作をかなり読んでいなければ、講演もよく理解できないのではないかというくらいのレベルである。
もちろん、基本的にはそれまでの研究のまとめのようなものであるが、『魏志倭人伝』だけでなく、さまざまな文献の記述を引用しながら、それについてどう解釈すべきかなどが紹介され、その方法論はかなり専門的である。同時に、古田説が単なる思いつきではなく、文献による詳細な分析で裏打ちされたアプローチであることが窺える。
第1章では、倭人が中国の歴代王朝でどのように認識されていたかという話で始まる。つまり『尚書』の周の時代の記事に倭人の記述が出ており、その後も『礼記』や『論衡』に周代記事として倭人の記述が出てくることから、倭人の存在自体は、中国の歴代王朝では常識であったと言うのである。その上で、『魏志倭人伝』の記事は、その倭人の実際の状況について報告している。つまり倭人の状況を詳細に語ることで、魏の(これまでの王朝ではなしえなかった)東方への勢力圏を誇るという意味で、この『魏志』の中でも『倭人伝』の条がハイライトになっているのではないかというのが著者の主張である。そしてこれは、漢の時代に西方の勢力圏を誇ったのと好対照をなすとする。
後半になると、発掘物の解釈が出てきて、考古学的な専門性が高くなる。ただ、銅剣、銅矛、銅戈の区別が(本来は剣、矛、戈は別物であるにもかかわらず)、日本の考古学では、実は恣意的に行われたものであり、実質的には形状以外違いがないに等しいという指摘は興味深い。要は、元々、柄を差し込む形状になっているのを「矛」、茎が柄の方に差し込まれるようになっているものを「剣」ということにした(高橋健自「日本青銅文化の起源」)ということらしく、あくまでも仮につけた呼び名だったものが、その後、定説のように流布して、現在では教科書でもそういう分類をしているというのである。古代史には(だけとは限らないが)、こういう妙な分類や思い込みが多いということがよくわかる。
巻末にある「研究論文摘要」という章では、これまでの代表的な「邪馬台国」研究が紹介されており、なぜ、1) 『魏志倭人伝』に出てくる「邪馬壹国」が「邪馬台国」にされ、大和に存在することになったのか、2) 「漢委奴国王」が「かんのわのなのこくおう」というように三段細切れ読みされるようになったのか、3) なぜ卑弥呼の墓が箸墓とされることになったのか、などの事情が紹介されている。どれも古田武彦に言わせればデタラメな比定であるが、1) は、江戸時代の松下見林『異称日本伝』が発祥で、明治時代の内藤湖南らがそれを補強した(なお、邪馬壹国の女王、壹与は「台与」が正しいとしたのも内藤湖南が最初らしい)、2) は、大正時代の三宅米吉『邪馬台国について』に最初に登場し、それが定説化した、3) は、笠井新也『卑弥呼の冢墓と箸墓』で最初に提唱され、こちらもそれが定説化したというもので、そういったいきさつがわかると、どれも立派な根拠があったというわけではないことがよくわかる。何となくの説が定説化し、常識化した事情がよくわかるが、ただ、そういった「定説」を無批判に受け入れるのは、学問的な視点では問題ありで、古田が再三指摘しているのもそのあたりの問題なのである。
本書は内容的には少し細かく、一般向けとはなかなか言いがたいが、古田の研究アプローチがよくわかるという点では参考になる。また『魏志倭人伝』の全文(南宋紹熙本)と、その(古田流の)読み下し文が掲載されているのも役に立つ。