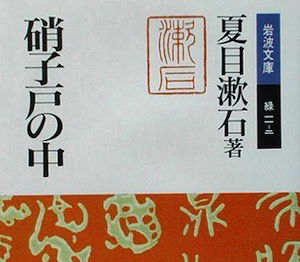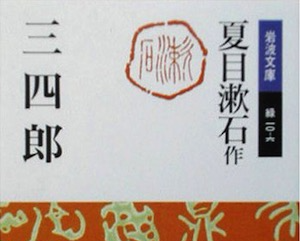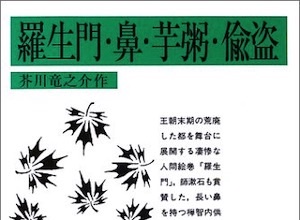漱石の印税帖 娘婿がみた素顔の文豪
松岡譲著
文春文庫
文豪たちが活き活きと蘇る
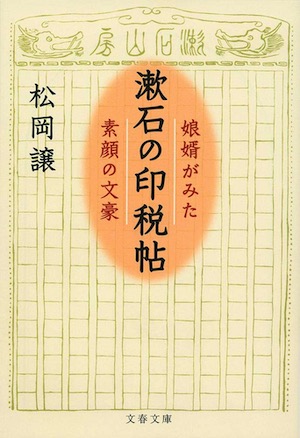
夏目漱石の弟子の1人で新思潮派のメンバーでもある松岡譲が、漱石や新思潮派の同人たちとの想い出を語った短編集。
著者の松岡譲、漱石の弟子ではあるが、同時に漱石の長女、筆子の夫、つまり漱石の娘婿でもある。もっとも松岡と筆子が結婚したのは漱石没後である。しかも結婚に際して、(松岡の友人にして『新思潮』同人の)久米正雄が筆子に猛烈にアプローチしていたにもかかわらず、筆子の方で松岡を選んだといういきさつがあって、このあたりちょっと『こころ』を彷彿させる話である。このいきさつについては本書収録の「回想の久米・菊池」という一編に詳しい。久米正雄は当時かなりの遊び人で、漱石の兄弟子たちからは筆子に近づくなとしきりに警告されていたというような存在で、しかも筆子に振られた後は、筆子と松岡をモデルにして、彼らがひどい人間であるかのように自身の小説で描き続けたという、ちょっとしたろくでなし人間である。だが久米は、結果的にこういったスキャンダラスな小説で名前を挙げていき、一方の松岡はこの事件後、小説執筆を断つなどということをやった(このあたりも漱石の小説のようだ)ため、小説家としての名声は久米の方が上がっていった、というんだから人生はわからないものだ。またこの一編には、若き日の(全然売れていない頃の)菊池寛が出てきて、これがまたすごいいい人なんだ。久米、菊池についてはこれまで持っていた印象と大分違う上、この小説では、彼らの人間像が活写されていて、内容的にも大変興味深い作になっている。
他に、『新思潮』同人の芥川龍之介について書かれた「二十代の芥川」もよくできた小説で、こちらも芥川が活き活きと現れてくる。最後の方の
「彼の死ぬ前年の十二月九日、漱石の十三回忌の時雑司ヶ谷の墓前で久々で逢った時には、その顔に死相といってもよさそうな、まるでポオの小説の挿絵みたいなものが現れていてびっくりした。岡本かの子が「鶴は病みき」で書いた、電車の中の子供が「オバケッ」と泣き出したというあの顔なのだ。」
という記述は迫力がある。
漱石について書かれた「宗教的問答」や「『明暗』の頃」でも、人間・漱石が活写されている。著者の小説に出てくる文豪たちは、どれも友人だったり先輩だったり師匠だったりで、読者も彼らを一人の人間として身近に感じられるのは、著者の筆力のせいか。鈴木三重吉について書かれた「三重吉挿話」も良い。
本書は、基本的には漱石について書いたものの方が数が多いが、タイトルにもなっている一編、「漱石の印税帖」については小説というよりレポートみたいなもので、漱石作品の出版歴をまとめたという類の話であり面白味はまったくない。なぜこの一編をメインに据えたのかよくわからない。「贋漱石」と「漱石の万年筆」は、漱石死後の遺物についての話でこちらはエッセイみたいな内容。
やはり本書の目玉は、先ほども言ったような、直接の知人である文豪たちの有様を描いたものであると思う。そして、若き日の彼らが活き活きと描写されていることから、著者を含む新思潮派の人々の一種の青春記になっているとも言える。雑多な内容の短編集だが、そのあたりが一番の魅力ではないかと思う。
また同時に、エライ人の娘婿になるということが結構つらいことだということもわかる。なお、作家の半藤一利は、この松岡譲の娘婿で、漱石の義理の孫ということになる。この人もつらかったのか知らん。