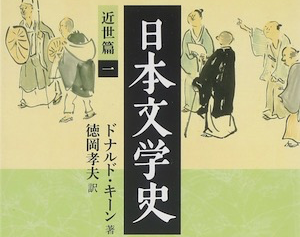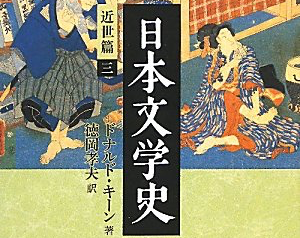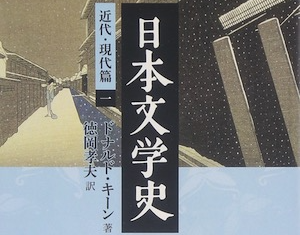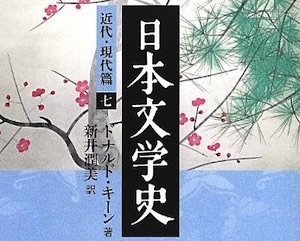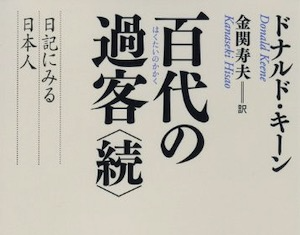日本文学史 近世篇〈二〉
ドナルド・キーン著、徳岡孝夫訳
中公文庫
元禄三文人完結

ドナルド・キーンの畢生の大作、『日本文学史』の第二巻。『日本文学史 近世篇〈一〉』に続く書である。第一巻では松尾芭蕉とそれに至るまでの俳壇が主要なテーマだったが、第二巻は、元禄三文人の残りの二人、つまり井原西鶴と近松門左衛門が柱になっている。
内容は第一巻同様、非常に濃密で、西鶴や近松の魅力が存分に語られる。またそれ以外にも、それに連なる文学潮流の他、西鶴以降の浮世草子や近松以降の浄瑠璃作家(竹田出雲や近松半二)についてもかなり詳細に語られるため、歴史における西鶴や近松の位置付けみたいなものも見えてくる。
その他に、芭蕉以降低迷した俳句界についても紙面が割かれていて、こちらも興味深い。芭蕉と芭蕉の弟子たちが死んでから蕉風俳諧の潮流は去り、以前の貞門派や談林派のような芸術的価値の低い俳句が多くなったが、同時に職業人としての俳人が登場するという現象も現れる。そんな中、芭蕉の俳句を見直そうという動きが少しずつ高まり、そういう折に登場したのが与謝蕪村。あわせてこの時代に、蕉風が江戸時代の文学界に確固とした地位を固めるようになってくるという流れである(まさしく「不易流行」)。
また国学の流れについても一章が割かれている(「国学と和歌」)。国学自体が、現代人にとってはわかりにくい存在で、僕自身は日本の国粋主義のルーツ程度にしか思っていなかったが、本書では本居宣長の業績、特に源氏物語や古事記に対する科学的分析について多大な評価が与えられている。「日本が生んだ最も偉大な学者」と形容されているほどである。
僕は特にこの時代の文学史については疎い方だったこともあり、どの稿、どの論も新鮮に感じた。実際、これがきっかけで西鶴の作品(『世間胸算用』)あるいは関連作品(『ぬけ穴の首 西鶴の諸国ばなし』)を読んだりしたのだが、ただ一方で、このシリーズの刊行が、なぜ江戸期の文学から始まったのかはなかなか見えてこない。僕自身は、日本文学の全歴史から俯瞰すると、江戸文学は比較的マイナーな位置付けだと感じていたし、今もあまりその印象に変わりがないのである。もちろん、歌舞伎や浄瑠璃、俳句など、現代へと通じる文化的影響を考えると、それなりの重要性があることはわかるが、やはり平安時代や近代の方が、僕にとっては関心が高い。この近世篇は第三巻で完結で、その次は近代篇ということになる。僕にとってはむしろ近代篇の方が楽しみなんだが、それでも第三巻をいい加減に読んでしまってはもったいないんで、そのあたりは注意しながら読み進めたいと思う。なお第三巻は上田秋成と歌舞伎が目玉のようである。