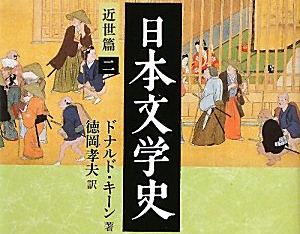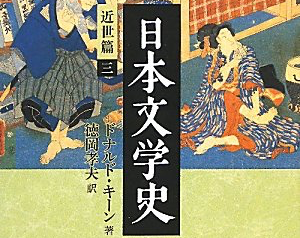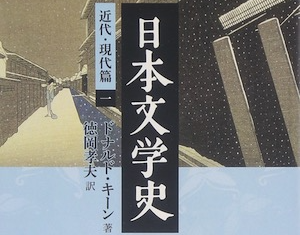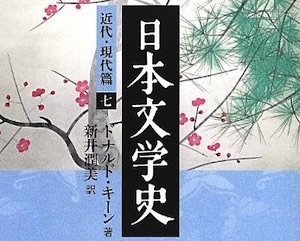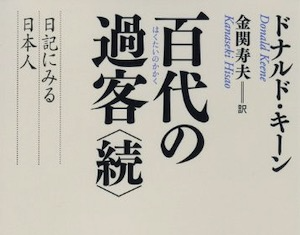日本文学史 近世篇〈一〉
ドナルド・キーン著、徳岡孝夫訳
中公文庫
キーン先生畢生の大作
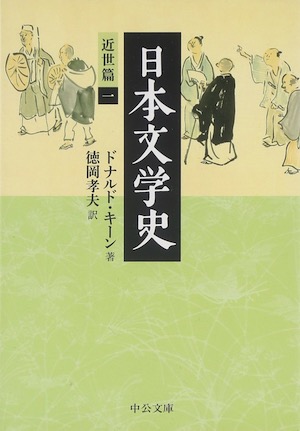
ドナルド・キーンの日本文学史。この『日本文学史』は、1976年から、近世、近代・現代、古代・中世の順に刊行が行われたらしい。結果的に相当な大作になって、文庫版でも近世篇3巻、近代・現代篇9巻、古代・中世篇6巻の全18巻構成になっている。いくらなんでもたかだか日本の文学史に長尺過ぎるだろう、決して手を出すことはないだろうと僕などは思っていたが、ついに手を出してしまったのだ。だが近世篇第1巻を読む限り、内容が非常に充実していて面白いと言わざるを得ない。当初は日本の文学史でこんなに書くべきことがあるのかと思っていたが、この1冊だけでも相当濃密であり、これまで僕なりに考えていた「日本文学史」の概念が覆されるような思いさえする。確かに、これだけしっかりしたものを書こうと思えば大著になるのも当然と感じるようになった。ドナルド・キーンの傑作であり力作である。この後も続けて読みたいと感じる。
この近世篇第1巻は、室町時代後期の連歌から書き起こされる。室町時代以降盛んになった連歌が、どのような経緯で近世の俳諧連歌、ひいては松尾芭蕉に繋がるかが歴史的な側面から描かれる。この第1巻のテーマは、あえて言うならば江戸前期韻文史(特に俳句)ということになる。
まず最初に登場する重要人物が松永貞徳で、同時にこの貞徳から始まった貞門派の俳諧が語られる。続いて、江戸時代にそれに対抗するユニークな流派として上方に登場した談林派に話が移る。貞門派や談林派の特徴が紹介されて、それが松尾芭蕉の蕉風俳諧にどのように影響したかが示され、第1巻の目玉(と思われる)松尾芭蕉へと筆は進むのである。その後、芭蕉の弟子たちの活動が紹介され、そして第1巻の最後は仮名草子(江戸初期の仮名書きの出版物)で締められる。第2巻はこれに続いて、仮名草子の流れを汲む井原西鶴に話が進むというわけである。
俳句にはそれぞれ英訳が付けられている(元々はアメリカで出版された本のようである)。当然、著者の解釈に基づく英訳で、俳句は(一般的に韻文はそうだが)元々解釈が難しいものが多いため、著者の解釈が示されることで逆に理解しやすくなっている。日本語への翻訳は徳岡孝夫という人が担当しているが、文章が非常に読みやすく優れた翻訳になっている点も評価に値する。
ともかく、先ほども書いたように、内容が濃密であり、冗長な箇所が一切ない。もしこれが講義であれば、一言も聞き漏らしたくないと感じるような密度である。キーン先生の畢生の大作と言える著書で、『百代の過客』もそうだったが、読者である自分にとって新発見が目白押しの快作である。
実は近代と中古・中世を先に読みたかったんだが、刊行順に読むのが良さそうと感じたせいで、『近世篇』から始めてしまった。もちろんこの『近世篇』もここまで書いているように非常に興味深く面白いのではあるが、僕にとっては優先順位は低かったのだ。おかげで近代と中世を読むのが待ち遠しいというのか、あっちを先に読んでおいたら良かったかななどと多少の後悔が残るのである。