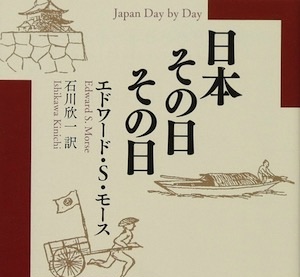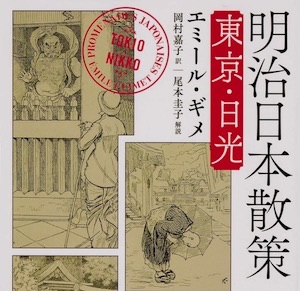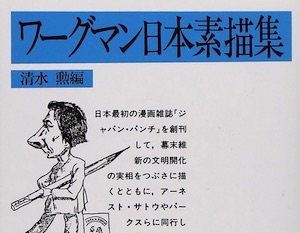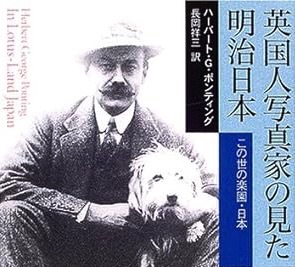シュリーマン旅行記 清国・日本
ハインリッヒ・シュリーマン著、石井和子訳
講談社学術文庫
あのシュリーマンは江戸日本も訪れていた
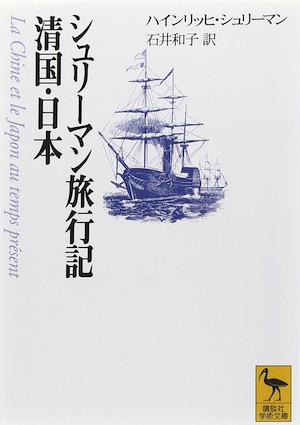
トロイ遺跡の発掘で有名なシュリーマンが、トロイの発掘に先立つ数年前に世界旅行に出ており、その際、清国と日本に立ち寄っている。立ち寄っていると言っても、日本を訪れるのが彼にとって最大の目的だったようで、そのため1カ月近く滞在し、(当時の開港地だった)横浜だけでなく江戸市中でもあちこちを回っている。なおシュリーマンが来日したのは1965年6月1日だが、その時点で江戸市中は、基本的に領事以外、外国人立入禁止だった。幕府に申請すれば、領事の関係者は立ち入りできたようだが、少し前に英国公使館が焼き討ちに遭ったり、アメリカの通詞のヒュースケンが殺害されたりしており、決して外国人の安全が保証される場所ではなかった(そのためほとんどの領事は横浜に転居していた)。シュリーマンは、民間人であるにもかかわらず、アメリカ代理公使のポートマンのつてで江戸に入ることができたが、行動の際は江戸幕府から派遣された数人の護衛が常時警護していたという有り様である。幕府も(外国人であるためか)随分気を遣ったものだが、当のシュリーマンは、護衛について煩わしく感じているフシがある。このような背景を考えると、シュリーマンの江戸訪問は1人の金持ち西洋人実業家のわがままにも映り、そういう点ではあまり良い気分はしない。
本書は、シュリーマンによる清国と日本の訪問記であり、元々の著作は1869年にパリで刊行されている。清国にも1カ月間滞在しており、天津から北京に入り、万里の長城に上っている(万里の長城が清国訪問での最大の目的だったようだ)。シュリーマンの目に映る北京の有り様はひどく、街は不潔で、貧民に溢れているという状態で、落日の清王朝を反映しているようである。清国の栄華の跡も見受けられるが、そういうものも崩壊寸前の状態になっており、万里の長城についてもすでに岩山と化した状態で、上るのが命がけみたいな有り様であったことが窺われる。
その後、上海経由で念願の日本にやって来るわけだが、清国の状況と打って変わって、江戸日本については平和で豊かという印象を持つ。また、著者は、日本人の生活自体にも大いに関心を示しており、それがために江戸の社会や文化の有り様が活き活きと描写されている。
明治期になると来日する外国人が多くなり、当時の日本社会に関するヨーロッパ人の記述も増えてくるが、江戸期に関して言うと来日した外国人は比較的少なく、そういう点を考えると本書の記述は貴重なドキュメントと言うことができる。しかも、シュリーマン自身に文化的な偏見がなく、そのため江戸の社会や体制を比較的客観的な目で見ることができており、その点でも価値は高い。江戸の社会については全般的にかなり好ましい印象を持っていることが窺われるが、シュリーマンが最初から日本訪問を楽しみにしていたことを考えると、おそらく当時のヨーロッパに日本に対する好ましい評判があったのではないかと思われる。1969年に出版されたというシュリーマンのこの原著も、その後のヨーロッパ人の好ましい日本(江戸)観に影響したであろうことは想像できる。
滞在が清国と日本でそれぞれ1カ月足らずであるため、それぞれの制度や社会に対して誤解があるように見受けられる箇所もあるが(特に第7章の「日本文明論」)、当時の社会を覗き見る覗き窓のような役割は十分果たしている。江戸期の日本が、当時のヨーロッパ人には不思議の国のように映っているようで、そのあたりも非常に興味深いところである。