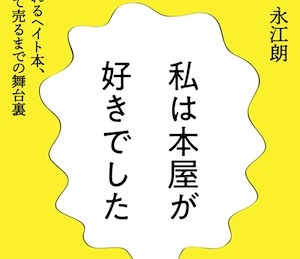13坪の本屋の奇跡
「闘い、そしてつながる」隆祥館書店の70年
木村元彦著
ころから
書店に巣くう取次の悪弊

町の本屋は、今どこも大変な状況だが、そんな中、独自路線で健闘している、売り場面積13坪の隆祥館書店(大阪、谷町)を紹介した本。
創業者だった先代の書店主の確固とした理念を引き継いだ、現在の書店主、二村知子の顧客志向の経営方針が印象的で、こういう方針で仕事を続けていけば、顧客にそっぽを向かれることはないというのがよく伝わってくる。さらにこの二村氏、毎月2回以上、自身が著書を読んだ上で気に入った作家を呼び、その作家と読者を取り持つ会(「作家と読者の会」)を開催しており、良書を顧客に伝えていこうとするスタンスがこういう部分にも反映されている。
中でも本書で注目すべきは、取次会社(出版者から仕入れた本を書店に配本する問屋。日本の場合トーハンと日販が主力)の悪弊を指摘した箇所で、小規模の書店はあれやこれやの方策により、彼らの圧迫を受けているという。要するに、頼んでもいないのに強制的に数々の本が送られ、しかもそれに対してしっかり代金を支払わされるというシステムが存在するらしく、僕自身はこういったことについてよく知らなかったため、非常に驚いたのであった。本書によると、取次会社が書店にヘイト本を多数送りつけてくるらしく、ヘイト本が書店に溢れる理由はこれだというのである。隆祥館書店ではこういった本については拒否して送り返すが、しかし代金はしっかり取られる。返却本に対する代金は後に返却されるが、その間にタイムラグがあるため、その間の資金繰りが大変になる。このような旧弊なシステムが存在することから、哲学を持って経営している書店ほど苦しむ……という変な構図が生み出されているというのである。だが、こういう妙な配本システムのために小規模書店が経営を辞めざるを得なくなれば、結局商売が成り立たなくなるのは取次会社であって、そのあたりがなぜわからないのか疑問である。もちろん取次会社でも、一部の社員はこういう現状に危機感を抱いて活動しているらしいが、状況が改善しないところを見ると、経営側には届いていないようである。こういった話がが第1部で展開される。
後半(第2部)は、ネタがなくなったのか、これまで開催された、先述の「作家と読者の会」の記録で、藤岡陽子、小出裕章、井村雅代、鎌田實の回の講演録。埋め草みたいな印象も受けるが、実はこちらの方が読みやすく面白かった。