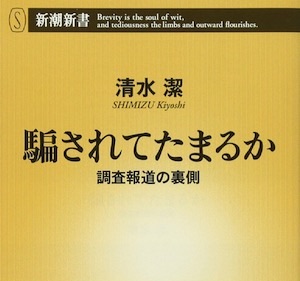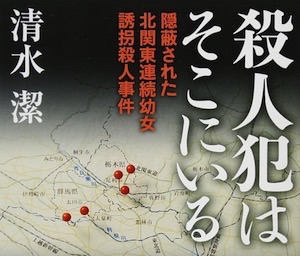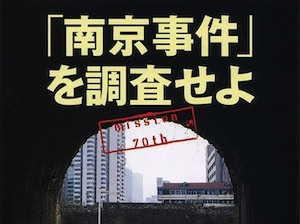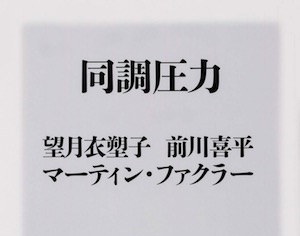裁判所の正体
法服を着た役人たち
瀬木比呂志、清水潔著
新潮社
日本の司法の状況は独裁国家並み

『騙されてたまるか』の著者であり、桶川ストーカー殺人事件や足利事件などの調査報道に関わってきた記者である清水潔と、元裁判官の法学研究者、瀬木比呂志の対談。対談といっても、その多くは清水潔が瀬木比呂志に現在の日本の司法の状況を訊く(というか伺う)というもので、最初から最後まで一貫して、現在の日本の司法の状況が紹介されるわけである。
元裁判官で法曹界にどっぷり浸かっていた瀬木から語られる日本の司法の現状は驚きの連続で、そのあまりのひどさに暗澹たる気持ちになってくる。そもそも、司法の現場でエリートコースみたいなものがあって、出身大学(当然東大に一番価値が置かれている)や司法試験の合格成績(つまり不合格回数)によってその後のルートが最初からほぼ決まってしまうなどという事実からして驚く。司法の現場は、他の役所と違って実績主義・実力主義だとばかり思っていたが、そんなことは決してなく、国家公務員などの役人の世界と同じらしい。しかも、下位の裁判所の裁判官が、日本の司法界のトップである最高裁判所の意向に従わない(画期的な)判決を出したりすると途端に出世コースから外れ、待遇の低い地方の家裁などに飛ばされたりする。そのため、提灯持ちみたいな人間ばかりが上層部に集まるというのが現状らしい。
さらに、最高裁自体が、政権の意向を受けた存在であり、それが先ほども書いたようなシステムで下位に位置する裁判所に影響を及ぼすため、政権に配慮した判決ばかりが出るような仕組みになっている。その上、裁判官が国の弁護を担当するようなことも制度上許されているらしく(というよりそういう制度なのだ)、民意を反映した判決はますます出にくくなる。
このように、日本は憲法上、三権分立の体裁をとってはいるが、実質的に司法が行政に従属している状況で、しかも司法当局自体がそれを良しとして受け入れているらしいのである。さらには、近年になって(最高裁による統制の結果)名誉毀損裁判の方針が変わり、権力者が裁判で名誉毀損を訴えることで勝訴しやすくなったために、スラップ訴訟(恫喝訴訟)を起こしやすくなっているという現状もあるらしい。ますます行政の意向ばかりが大事にされる国に日本は転換しており、まさしく独裁国家への道をひた走りというのが司法の現状から窺われる。
しかも、そういう体質であることから、検察や裁判所などの司法権力が、己のメンツを守るためだけと思われるような判決も頻繁に出される。足利事件でDNA鑑定の結果に疑問符が付いたにもかかわらず、同時期のDNA鑑定について証拠としての価値が破棄されないのもそのせいだという(たとえば同時期の飯塚事件などではDNA鑑定がもっとも有力な証拠であり、そのDNA鑑定自体、足利事件と同種の方法で実施された相当怪しいものだったが、再審請求の中ではDNA鑑定の疑義が採用されなかった。ちなみに飯塚事件は異常なほどの速さで判決が出され〈無実を主張していた〉被疑者は死刑に処された)。
ともかく現在の日本の司法の状況は、独裁国家と同程度で、近代国家の司法とはとうてい言い得ないということが本書から窺われる。ほとんどの箇所では、清水が聞き役に徹していて、そのために瀬木が率直に滔々と語り続けるため、瀬木の司法に対する思いが吐露されている。ただあまりに自由に語らせているせいか、「左翼系裁判官」というような言葉も頻繁に出てきたりする。「左翼系」という言葉が何を意味しているのかよくわからないが(青法協などにもところどころ言及しているのでそのあたりを指しているのではないかと思う)、何となく選民的というか差別的なニュアンスを漂わせていて、瀬木自身が高慢な「俗物」(瀬木の裁判官評)に見えてしまう。それにいろいろなことに決めつけが多いのも難点である。
とは言え、清水が非常に上手く話を引き出しているために、司法の問題点についてはよくあぶり出されており、本としての価値は高い。もっともこの本を読むと、日本の行政、立法だけでなく司法の世界まで腐りきっていることがわかり、絶望感に襲われるのは必至で、瀬木の言うようにジャーナリズムが現在の司法の問題を世に問い続けて一般に周知させていかなければ改善される見込みはない。それにもかかわらず、ジャーナリズムも近年、保身のために本来の仕事をしないという超保守主義がはびこっているようで、それを思うと日本の先行きは暗いとしか言いようがない。