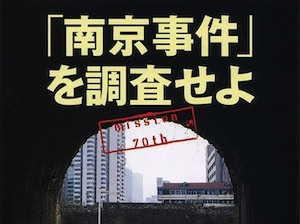日本軍兵士
アジア・太平洋戦争の現実
吉田裕著
中公新書
責任者出てこい!と言いたくなる
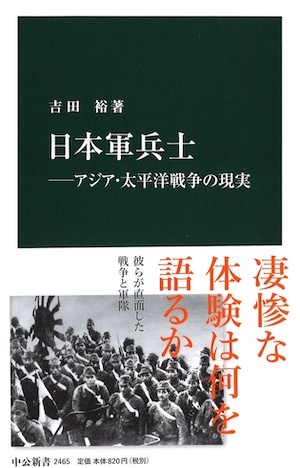
証言記録や統計を基にして、太平洋戦争における日本軍の活動をミクロ的な視点で描いた本。ミクロ的という点がミソで、それがこの本の大きな特徴である。マクロ的に見た太平洋戦争は、大日本帝国軍が連合国軍に対して当初攻勢をかけていたが、米軍の物量と作戦によって徐々に敗勢が強まった……という見方になるが、ミクロ的に検討してみると、決してそういうレベルではなく、当初から敗戦の要因が日本軍にあり(というより勝てる要素がまったくない)、無能かつ無責任な上層部による無謀な戦略であったことがよくわかる。
当初連戦連勝だったのは、連合国軍に戦争の準備がなかったため(特にヨーロッパ諸国についてはドイツ軍との戦いが進行中だった)で、それなりの対策をとってくれば端から勝負にならないことは火を見るより明らか……という印象である。本書ではいくつかに分けて日本軍の状況が描かれていて、軍隊内での非合理性や無秩序さ、兵士に対する人権無視、上層部の間違った思い込みによる兵士への虐待などが紹介される。多くは、戦後作られたさまざまな映画や小説などで紹介されていることなので、こういった事実にそれほど新鮮さは感じないが、しかし戦闘集団として見た場合、これが大きなマイナス要因であることにあらためて気付かされる。
また日本軍の装備の貧しさも紹介される。たとえば自動車がきわめて少なく軍馬が多用されていたことや、無線通信より有線通信が重視されていたために爆撃でワイヤーが破損すると途端に通信手段がなくなった(伝書鳩まで使われていたらしい)などという事実は驚きである。よくこんな装備で、世界最大の工業国と戦争をしようなどと考えたものだと思うほどである。特に自動車が無かったために、兵士が自ら運ぶ装備が非常に重くなり、そのために兵士の疲弊(ひいては行き倒れ)を招いたなどという指摘は、一兵卒の憐れさを感じさせる。装備が足りない分は根性で何とかしろという発想のようである。
軍隊内の医療の不備もひどかったらしく、歯科医がほとんどいないために虫歯が多発した他、医薬の不足、病人をサボタージュとして扱う軍隊内の気風など、少なくとも総力戦を闘うための部隊とは言えなさそうである。水虫も致命的なほど蔓延し、それがまた士気に大いに関わるレベルで、兵士の間に大きな問題を生み出す。なぜこれだけのマイナス要素を放置するかなと思うが、そもそも日本軍には軍団内の問題を解決するという発想自体がないようで、そのために問題のある(犯罪歴のあるような)兵士がいても放置され、軍隊内の秩序が維持できなくなっても対策がとれない。一方で、問題のない兵士に対して平気でリンチしたり虐待したりして、結果的に死なせたりする(戦闘死として処理される)らしいから、まともな集団とは思えない。
装備が足りていないのは、そもそも戦争を始めた政治の上層部に、近代戦が総力戦であるという認識が著しく欠けていたためで、「不都合なことはないことにする」という場当たり的な発想で始めた戦争であることがこういう事実から窺われる。軍の指導者達についても、無計画で行き当たりばったりの作戦を次々と展開し、いたずらに兵力を犠牲にする。特攻作戦(あれを作戦と言えるかどうかわからないが)なんかその良い例である。
とにかく、大日本帝国軍の至る所に問題があり、それは日本人の悪い特質にも関連するようだが、それが明確な形で現れたのが太平洋戦争だということ、それがよくわかる。しかも当時の責任者のほとんどは、その後責任を問われることもなく、のうのうと生きてきた。こういった無責任主義、それから正論(と本人が信じていること)を他人に押し付ける教条主義、強い立場の者が弱い立場の者を圧殺する権威主義など、帝国軍にはびこっていた悪弊が、現在の日本国に生きる我々にもそのまま踏襲されている。このことは、今の世の中、周りを見てみたらすぐにわかる。こういう誤った指向は、社会に悪弊をもたらすだけでなく、生産性や合理性を阻害することにも繋がる。問題点を直視することでこういった悪弊を少しでも改善していくのが理想であるが、残念ながらそういう発想は現在の日本では必ずしも多数派ではない。戦後ずっと、歴史問題をないことにする風潮があるが、それ自体が日本の悪弊であることを認識した上で、改善したいものだ……とそういうことを考えるきっかけになったのが、この本である。
第30回アジア・太平洋賞特別賞受賞