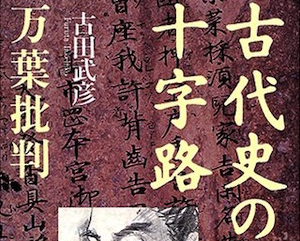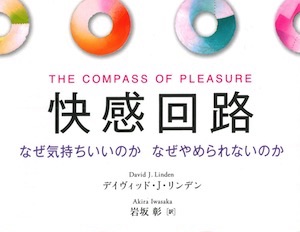吉野ヶ里の秘密
解明された『倭人伝』の世界
古田武彦著
光文社カッパ・ブックス
邪馬台国論争にトドメは刺さらなかったが
興味深い事実が多数紹介される

古代史に新解釈をもたらした歴史学者、古田武彦の著書。吉野ヶ里遺跡の発見から数年後の1989年に出版された本である。
古田武彦は、かねてより大和王朝以前に九州王朝が存在し「倭」と称して大陸の王朝と交流を続けていたことについて、さまざまな書を通じて主張してきた。一方で、古田のこの多元史観は日本の古代史学界からは受け入れられず、完全に無視されていた。
そんな折に佐賀県の吉野ヶ里遺跡が1986年に発見され、大規模な環濠集落の存在が証明された。吉野ヶ里遺跡からは古田説や『魏志倭人伝』の記述を裏付けるような証拠が次々と現れたために、これで固陋な古代史学界もついに九州王朝説を受け入れざるを得なくなったと古田氏も感じていたようで、本書にもそういう自信満々な論調が多い(実際、帯にも「邪馬台国論争にトドメを刺す!」と書かれていた)のだが、実際には、21世紀の現在になっても九州王朝説は定説になっていない。
本書では、九州王朝説の視点による吉野ヶ里遺跡の解明が試みられており、どの説にも非常に説得力がある。本書でも紹介されているが、邪馬台国近畿説を主張していたある有力学者も王権の中心地がこの付近にあったことを認めざるを得なかったという。ではあるが、その後の古代史学界の様子を見ると、以前とまったく変わった様相はない。結局、今の古代史の世界では吉野ヶ里は一地域の遺跡に過ぎないということになり、大局的な歴史との関連が語られないことになった。要するに、従来の歴史観からはこの遺跡の重要性について説明することが難しいということなのである。スッキリした形で説明できるのだから素直に多元史観を受け入れたら良いのにと思うが、彼らの保守性は、利害関係もあるんだろうが一筋縄ではいかない。
それはともかく、本書で展開される論はどれも魅力的で、吉野ヶ里は、古代の首都圏(今の福岡市周辺)の一部であり、同時に海に繋がる港湾都市であり防衛拠点であったとする説は説得力がある。言わば、東京と横浜のような関係というのである。遺跡から出現した墳丘墓や多数の甕棺についても分析が加えられ、ここに葬られているのは、その出土品から検討すると、倭の天子クラスではなくその下の大王クラスであって、甕棺に入っている骨はそれに仕える人々と庶民のものであると結論付ける。他にも、吉野ヶ里遺跡についてかなり詳細に説明があるため、その全貌とまでは行かなくてもアウトラインはよくわかるようになっている。
一般的にどの遺跡でも、そのほとんどが一般人の目に触れることがなく、結局は、発掘に基づいて学者が出した結論のみがひとり歩きするため、多くの場合、そこに介在する人の独断的な見方で支配されてしまう。そういう意味では、本書のように、書籍を通じてその本来の姿が明らかにされるのは大いに価値のあるところである。
なお、本書は、光文社のカッパ・ブックスという、少しばかり怪しげな新書シリーズの中に入っていて、一般向けの読みやすい本になっているのはまだ良いんだが、扇情的な表現が目に付くという欠点がある。また記述についても、話し言葉風の妙な言い回しが多い。たとえば「クイック・リターン・トゥ・吉野ヶ里。」などというフレーズが唐突に出て来て、読みながら思わず苦笑してしまう。それから体言止めがやけに多く、こちらも違和感を感じる。例を挙げると、
読者は、そう思わないか。 最初にも、のべた、「環濠集落」という言葉。これは、はじめにのべたように、住居(集落)を「濠」で囲んだもの。 ところが、この吉野ヶ里は、本当は「環濠集落」ではない。「環濠、墓地・集落」だ。 最初は、墓地だけ。あとで、住居が入り込む、墓地のどまん中に。こういう話があるのか、どうか。」(138ページ)
みたいな記述が、とにかく多い。
著者が悪ノリしたせいか、編集者が手を加えすぎたせいかわからないが、こういう浮かれた軽薄な記述は、せっかくの書の価値を大いに損ねる結果になる。歴史学の上で意義のある立派な主張なのに、軽薄な記述のせいでキワモノ扱いになりかねない。もったいない限りである。