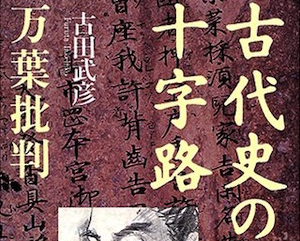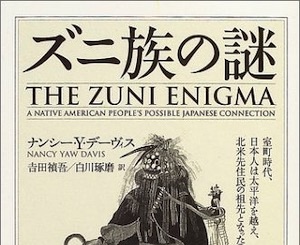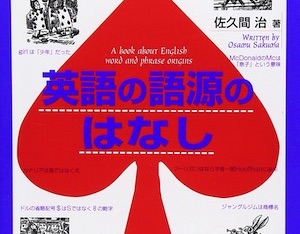「邪馬台国」はなかった
古田武彦著
朝日文庫
日本の歴史学における画期

日本の歴史学の世界で大きな問題になっている話題に邪馬台国論争がある。つまり、日本の古代に存在していた(とされている)「邪馬台国」が九州を拠点としていたか、大和を拠点としていたかについて、さまざまな学者、あるいは歴史愛好家が侃々諤々の論争を繰り広げ、いまだに決着が付いていないというアレである。こういう論争が出てくるのは、基となっている中国の歴史書、『三国志』中の「魏書」にある「倭人条」(いわゆる「魏志倭人伝」)の記述の解釈が各人で別れているためで、中には「魏志倭人伝」の記述自体が誤りとするものさえある(と言うより、ほとんどがそう)。もっともそんなことを言ってしまうと、論拠となる「魏志倭人伝」自体信頼できないものになり、「邪馬台国」が存在していたという前提さえも疑ってかからないといけないわけで、論理矛盾のような気もするが、そういうことにお構いなしで、自身の(希望的)解釈に合わない部分を誤りとするのは日本の古代史界では常態化している。
本書はその邪馬台国論争に一つの決着を付けようという意図で1971年に刊行されたものである。もっとも「邪馬台国論争に決着を付けようという意図」で刊行される本はいまだに後を絶たないが、単なる思いつきに基づくような駄本が多い。だが、そういった駄本と異なり、本書の論証はかなり緻密(少なくともそう思える)で、しかも解釈も非常に単純明快である。無理やりにいじくり回したりした形跡がなく、出てきた結論も至ってシンプルで自然。僕にとってはこれが決定版じゃないかと思える。実際、刊行されたときはかなりのセンセーションを巻き起こし、歴史学界からの反論、反発があったようだ。だがその後、彼らは無視を決め込んだようで、現在では黙殺状態という按配である。
簡単にまとめると、原典(つまり「魏志倭人伝」)の記述を誤りとしてむやみに改変しないで、素直に読もうというアプローチである。もし誤りとするのであれば、その根拠を明確にしなければいけないとするきわめて真っ当で科学的な主張である。
『三国志』は元々が古い書物であって、現存する最古のものは明代のものである。しかも版がいろいろあり、著者がもっとも信頼できるとする紹熙版(信頼性についての論考も本書にはある)では、「邪馬台国」という記述自体が存在せず、「邪馬壹国」と表記されている。室町期から江戸期、明治期に至るまで、大和に比定するため、つまりヤマトという読みをするために、「壹」の字を「臺」の誤りであろうと決めつけ、それで「邪馬臺国」(つまりヤマト国)と呼ぶようになっているという驚愕の事実が、冒頭から紹介されるのである。つまりかなり恣意的な方法で「邪馬台国」が出現したわけである。ちなみに「邪馬台国」の「台」の字も、「臺」から変更されたものである。原典の記述をこうやって「誤り」として勝手に変えてしまうのは、これまでの古代史界でよく行われた方法論であるが、本書では、まず手始めにそういう方法自体について疑義を呈している。まさしく目からウロコである。
その後、この『三国志』の特徴、つまり著者の陳寿が、当時の状況をきわめて正確に描写していることなどが紹介され、しかも『三国志』の中で「臺」が天子の宮殿(またはそれに準ずるもの)の意味で使われていることから、当時野蛮人とされていた周辺諸国に「臺」の字が使われるとすること自体がおかしいという風に論が進んでいく。原典を適宜引用しながら自身の論理を論証していくため、非常に説得力がある。ただし原典が頻繁に出てくるため、面白いにもかかわらず途中眠くなるが、これは致し方あるまい。
このように緻密な分析を重ね、「魏志倭人伝」を正確に後追いすれば、「邪馬壹国」は博多湾岸にあったことが判明するというのが著者の分析である。これまで解釈がなかなか定まらなかった「水行十日、陸行一月」という表現については、帯方郡から邪馬壹国に至るまでの総里程という解釈で、しかもそれを裏付ける計算方法も説得力がある。
「倭人伝」の記述をそのまま素直に解釈するというのが著者のアプローチだが、そういう解釈をすると、「倭人伝」に出てくる「黒歯国・裸国」は南米大陸になってしまうという大胆な説も提示している。ただしこれはあくまで試案として提示されているに過ぎない。とは言え、縄文土器と似た土器が現地で出土しているという事実もあり、この説を荒唐無稽として退けることはできない。僕自身、日本人と同じDNAを持つ人が南米に存在しているという話を以前聞いたことがある(近現代の移民ではなく先住民に)。
本書で展開される壮大なロマンは非常に魅力的で、発表当時、多くのアマチュア歴史家を魅了したのも頷けるというものである。また、歴史学の問題点を逐一紹介し、それに対して自身の見解や反論を紹介しているという点も評価に値する。アマチュアが著者の古田氏の説を支持する一つの理由になっている。
本書に対しては、歴史学の「専門家」たちから少ないながら反論が出て、中には、所詮素人の戯言に過ぎずセンセーショナルだから素人に支持されたのだ、と捉えている者もいるようだ。だが現在主流となっている(多くの歴史学者が支持している)多くの「古代史的事実」を俯瞰してみると、その論証はかなりいい加減で、ほとんどの説は「ある学者がそう思っている」というレベルの珍説の類である。背景となる歴史と整合性が取れていない上、説明のつかないことが異常に多いという印象で、古田説のような説得力があるものはほとんどない。古田説からは、古代から大宝年間に至るまでの倭国(九州北部を拠点とする大国)の歴史の断片が窺える。つまり、弥生時代から古墳時代にかけて日本列島の代表者として君臨していた(北部九州を拠点とする)倭国が、662年の白村江の戦いで唐と新羅の連合軍に大敗北を喫し、やがてそれが原因で滅びて、近畿を拠点とする「日本」に列島の代表権を取って代わられたという歴史が見えてくる。一つの王朝が滅びて他の王朝に取って代わられるというのも、当時の大陸の歴史を見てみるといかにも自然な印象を受ける。そして、そういう前提で遺跡などの出土物を解釈すれば、「真実」(と考えられるもの)が見えてくる。そういう意味でも、この本は日本の歴史学にとって画期的な本だったと考えられる。今回改めて読み直し、その思いを新たにしたのだった。